「職能給って何?」「基本給やボーナスとの関係は?」など疑問に思ったことはありませんか?職務給との違いがよく分からない人もいるかもしれません。職能給の意味から計算の方法、メリット・デメリットまで詳しく解説していきます。
職能給とは?
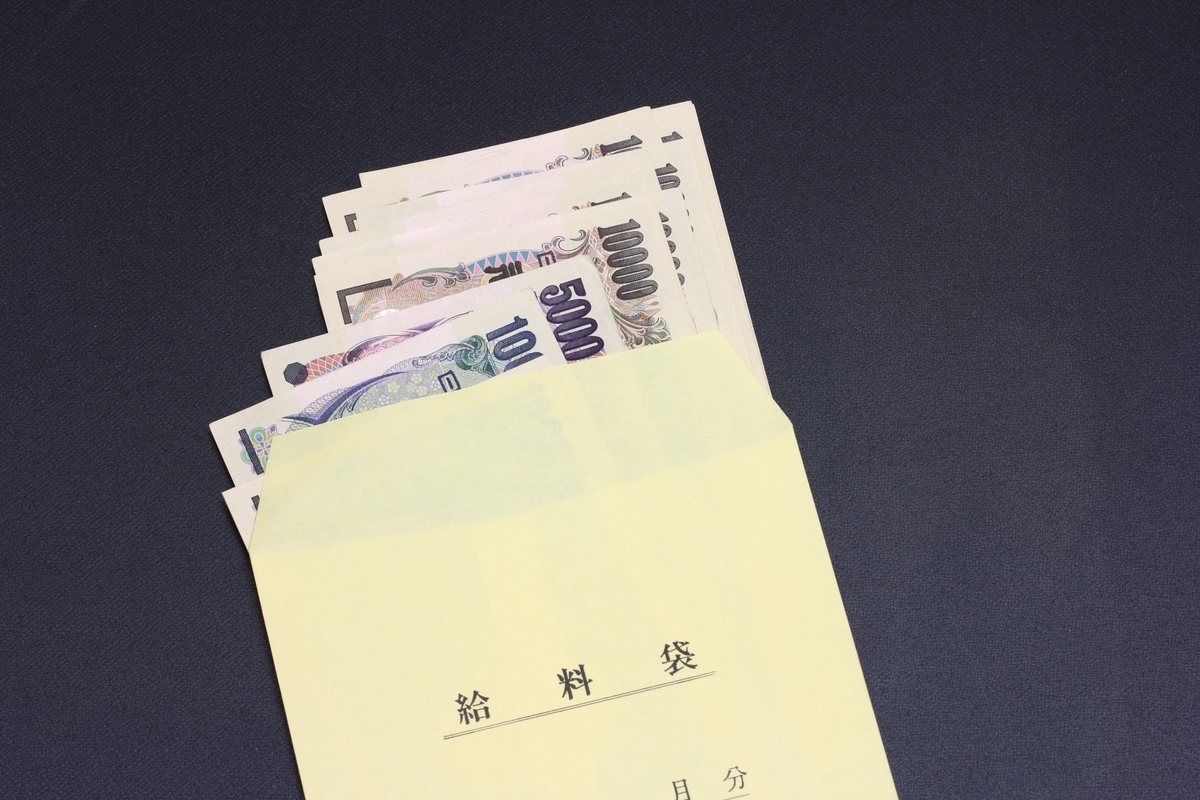
求人広告の給与欄で「職能給」という言葉を見かけたことはありませんか?特別な制度ではないかと考えている人もいるかもしれませんが、多くの企業で取り入れられている賃金体系の1つです。
自分の給与がどのように決まっているかを知るためにも、職能給についての正しい意味を理解しておきましょう。
職務遂行能力に応じた給料
職能給は、基本給の種類の1つです。職能給の金額は、職務遂行能力で決まります。しかし、仕事をやり遂げる力を正確に測って数値化するのは困難です。
そこで、職能給は勤続年数の長さや保有資格によって決まるものではありません。実際の仕事の成果は、職能給の金額に影響しません。
個々人の職務遂行能力で決まる「属人型」であるところが 、職能給の大きな特徴といえるでしょう。以前から日本では、職能給による給与体系を取り入れている企業が多く見られました。
ただ、近年は終身雇用を前提としたスタイルが揺らぎつつあり、仕事の成果で給与が決まる「成果主義型」の賃金体系を採用する企業も増えている傾向にあります。
職務給との違い
職務給は勤続年数や資格ではなく、職務(ジョブ)の難易度等を給与額に反映した制度です。外資系企業を中心に採用されている給与体系で、最近はジョブ型賃金制度として脚光を浴びています。
職能給では属人的な要素で本人の能力を評価する一方、職務給では仕事そのものが評価の対象となる点が大きな違いです。日本でも従来のいわゆる年功序列型の職能給から、成果を重視する職務給へとシフトしている企業が少なくありません。
「等級」と「号」で算出
職能給の金額は、企業が独自に設定した「職能給表」をもとに決められます。
職能給表には大きく分けて4種類ある中で、多くの企業で使われているのは昇進・昇格で決まる「等級」と、勤続年数や査定の評価などによって格付けされる「号」を組み合わせた「号棒表(ごうほうひょう)」と呼ばれるものです。
号棒表の横軸には1等級から順に等級が書かれており、縦軸には1号・2号というように号が振り分けられています。従業員は、勤続年数の長さや昇格によって「3等級12号」といったように格付けされます。
入社時の等級は1等級からスタートしますが、最終学歴によって号の格付けが異なったり、同じ年に入社した社員の間に賃金格差が生じたりすることもあるでしょう。
号には毎年1号ずつ上がる方式と、人事考課の結果を反映させて進み具合を決める方式があります。ただ、どのような決め方をしているかは人事担当以外には開示されていないのが一般的です。
ボーナスや退職金の額に影響する
ボーナスの決め方は企業によって変わるものの、多くの企業が採用しているのは「基本給〇カ月分」というように金額を定める「基本給連動型賞与」です。退職金も同じように、退職時の基本給をベースとしている企業が多いでしょう。
職能給は基本給の1つなので、基本給をもとにしたボーナスや退職金の計算に影響します。
ただ、ボーナスが業績連動型だったり退職金が勤務年数だけで決められたりと、企業によって制度が違います。在職中・転職予定の企業でどうなるのか気になる場合は、就業規則や面接で確認しておきましょう。
職能給のメリット

職能給には、もらう従業員側にとってどのようなメリットがあるのでしょうか?金銭面だけでなく、スキルアップの面からも考えてみましょう。
業務が変わっても給料が下がらない
職能給は、基本的に勤続年数や保有資格といった属人的な要素によって決まります。異動・出向などで業務内容が変わったとしても、給与が大きく下がる心配は少ないでしょう。
勤続年数と連動して上がっていくので、役職に就くことなく賃金がアップしていくケースも多いでしょう。
給与が段階的に上がっていくことから、将来の資金計画を立てやすかったり、生活を安定して保てたりといった安心感もあります。
長い目で見た育成が期待できる
職能給は原則として長く勤務するほど給与が高くなる仕組みなので、企業側も長く勤めてくれることを前提に人材を募集していると考えられます。
職能給制度を採用している企業の中には、長期的な人材育成の計画を用意しているところが少なくありません。じっくり腰を据えてスキルアップを目指したい人におすすめです。
業務内容による給与の変化がほとんどない分、戦略的に部署異動させる企業も見られます。さまざまな業務の経験を積むチャンスが多いでしょう。
職能給のデメリット

職能給のデメリットとしては、何が考えられるのでしょうか?メリットとされていることも、人によってはデメリットになるケースもあるかもしれません。職能給の特徴からデメリットを2つ見ていきましょう。
仕事の成果が反映されにくい
職能給では仕事の成果そのものは評価の対象にならないため、どれほど難しい仕事をしても金額に反映されません。
専門性の高い業務でも一般的な業務でも、同時期に入社した社員なら給与にほぼ変わりがないということです。
また、給与の金額が年功序列になりやすく、若い社員にとっては仕事量が給与に見合わないという不満につながるケースもあるでしょう。
いくらがんばって成果を出しても給与が上がるわけではないため、人によっては仕事へのモチベーションが下がってしまう可能性があります。
転職がしにくくなる可能性も
職能給を採用している企業の中には、自社に特化した人材を育成しようとするところも多いようです。他の企業で評価されるスキルが付かないと、転職市場での価値を高められない可能性もあります。
企業が求める人物像と自身が目指す将来像との間に隔たりがないか、入社する前によく確認しておくことが大切です。
そのためにも、自分のキャリアプランを明確にした上で、企業がどのような人材を求めているかを面接でしっかり聞いておきましょう。
職務給のメリットとデメリット

職能給と職務給は、手当の額を決める軸が真逆ともいえる制度です。自分に合った給与体系を知るためにも、職務給によくあるメリット・デメリットについても把握しておきましょう。
職務に応じて賃金額が決まる
職務給では、年齢や勤続年数を問わず公平に評価されます。仕事の成果をしっかり出せば、勤続年数の浅い若手社員でも先輩社員の給与を追い越すことも夢ではありません。
担当職務に見合った給与をもらえる環境は、働きがいにもつながります。専門的な知識やスキルが身に付きやすいことから、転職市場での価値も上がるでしょう。
勤務時間を基準としない成果主義型の職務給を取り入れている企業なら、育児や介護で時短勤務をしたい人にとってもメリットがあります。
企業に対して愛着を持ちにくい
職務給は、職務に対して支払われる給料なので、職務が変わらない限り、給与額は変わりません。長期勤続したとしても担当職務が同じであれば賃金額も変わらないので、企業に対する愛着を持ちにくくなるかもしれません。
給与体系の知識を転職に生かそう
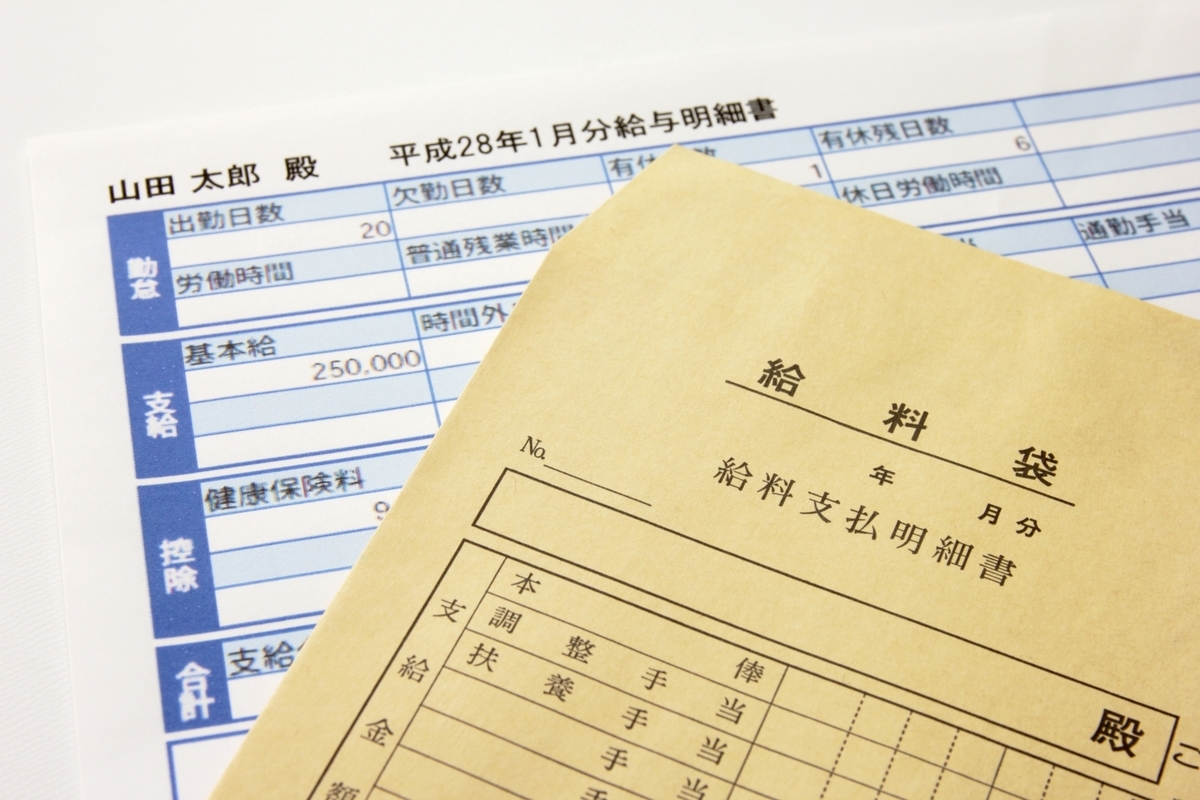
職能給は、安定した給与アップを望む人にとっては魅力的な給与体系です。仕事の成果が直接給与に反映されないとはいえ、人事考課の結果によっては昇給額がアップする可能性もあります。
勤続年数が長くなるほど高くなり、業務内容が変わっても給与はほとんど変わりません。じっくり腰を落ち着けて働きたい人や、さまざまな部署で幅広いスキルを身に付けたい人にもおすすめです。
転職先を探すときは給与体系の違いもしっかり理解して、自分に合った働き方ができる企業を見つけましょう。

あした葉経営労務研究所代表。特定社会保険労務士。法政大学大学院経営学研究科修了(MBA)、同政策創造研究科博士課程満期修了。人事・労務・採用に関するコンサルティングに一貫して従事。マネジメント向けの研修やeラーニングの監修も行う。
All Aboutプロフィールページ
