登録販売者の仕事が気になっている場合は、メリットやなり方を理解するのがおすすめです。資格取得後の働き方をイメージしやすくなるため、転職へのモチベーションが高まるでしょう。登録販売者とはどのような仕事なのか詳しく解説します。
登録販売者とは

登録販売者は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)という法律で定められている資格です。まずは、登録販売者の役割や誕生した背景について解説します。
一般用医薬品を販売できる専門資格
登録販売者は一般用医薬品を販売できる専門資格です。具体的には、一般用医薬品のうち、第2類・第3類医薬品を販売できます。
一般用医薬品とは、市販されている医薬品のことです。リスクに応じて第1類・第2類・第3類に分かれており、第2類と第3類が全体の9割以上を占めています。
登録販売者の代表的な勤務先は、医薬品を取り扱うドラッグストア・スーパー・コンビニです。薬を探しに来た人に対して正しい使い方を説明することが、登録販売者の役割です。
参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索
登録販売者が誕生した背景
登録販売者は比較的新しい資格です。登録販売者の資格ができるまでは、薬種商や薬剤師しか一般用医薬品を販売できませんでした。
しかし、セルフメディケーションの推進にあたり薬剤師不足が問題となり、2009年の薬事法改正によって登録販売者資格が誕生したのです。
セルフメディケーションとは、自分の健康に責任を持ち、軽い症状は自分で治すことです。セルフメディケーションを推進するために、一定の条件を満たせば所得控除を受けられるセルフメディケーション税制も創設されています。
登録販売者と似た職業

登録販売者と間違いやすい職業としては、薬剤師と調剤薬局事務が挙げられます。それぞれの特徴や登録販売者との違いを見ていきましょう。
薬剤師
薬剤師は薬剤師法で規定されている国家資格です。登録販売者が第2類・第3類医薬品しか販売できないのに対し、薬剤師は全ての一般用医薬品を販売できます。
医師が発行した処方箋に基づいて調剤を行える点も、薬剤師の大きな特徴です。登録販売者が行えるのは医薬品の販売のみであり、調剤はできません。
登録販売者の資格を取得するための受験資格は特にありませんが、薬剤師になるためには6年制の薬学部を卒業して国家試験に合格する必要があります。登録販売者より薬剤師の方が、資格取得のハードルは高めです。
調剤薬局事務
調剤薬局事務とは、調剤薬局で事務作業に従事する職種です。調剤報酬の算出やレセプトの作成、保険者への請求が、調剤薬局事務の主な仕事内容といえます。
調剤薬局事務に関する資格には、調剤事務管理士や調剤報酬請求事務専門士などがありますが、全て民間資格です。無資格でも調剤薬局事務として働けます。
調剤薬局事務は登録販売者と同じく、医薬品に関する仕事を担う職種ですが、医薬品に直接関わることはありません。あくまでも事務作業がメインの職業です。
登録販売者資格を生かせる職場

登録販売者が働ける代表的な場所と仕事内容を紹介します。転職後の働き方をイメージしやすくなるでしょう。
ドラッグストア・スーパー・コンビニ
登録販売者の勤務先として最も多いのがドラッグストアです。ほとんどのドラッグストアでは、医薬品販売以外にもレジ打ち・品出し・陳列・在庫管理などを行う必要があるでしょう。
近年はスーパーやコンビニでも、一般用医薬品を取り扱うケースが増えています。スーパーやコンビニで働く登録販売者も、一般のスタッフと同じ業務を行わなければなりません。
このように、薬を買いに来た人への接客がメインにはなるものの、登録販売者は医薬品以外の商品に関する仕事も担当することになります。
調剤薬局
登録販売者は調剤薬局で働くことも可能です。調剤薬局では薬剤師が調剤を行い、登録販売者は受付や窓口業務を行います。調剤薬局事務の業務を任されるケースもあるでしょう。
調剤薬局はドラッグストアやスーパーより営業時間が短く、残業も少なめです。また、大半の調剤薬局は日祝日が休日となっています。
仕事とプライベートの両立を図りたい人や、子育て中で不規則な生活ができない人は、調剤薬局で働くのがおすすめです。
登録販売者のメリット

一生モノの資格が身に付くことや、資格取得後にキャリアアップを目指せることが、登録販売者の主なメリットです。それぞれの具体的な内容を解説します。
一生モノの資格が身に付く
登録販売者は一度取得すれば生涯有効な資格です。出産や子育てにより離職しなければならなくなっても、生活が落ち着いたら再就職しやすいでしょう。
働ける場所が全国各地にあるのもメリットです。家庭の事情で引っ越しを余儀なくされた場合も、引っ越し先で比較的たやすく再就職先を見つけられます。
薬剤師に比べると資格取得のハードルも低いため、一生モノの資格を身に付けたい人には登録販売者がおすすめです。
キャリアアップを目指せる
登録販売者が働ける職場によっては、資格手当が付く場合もあります。時給が高くなるケースもあるため、収入アップを図りたい場合に登録販売者資格が役立つでしょう。
また、ドラッグストアなどの店長として働くためには、一般的に登録販売者の資格が必須です。登録販売者の資格を持っていれば、店長候補として就職できます。
一般のスタッフとして働いている場合も、登録販売者の資格を取得すれば昇進の道が開けるため、キャリアアップにもつながります。
登録販売者になるには
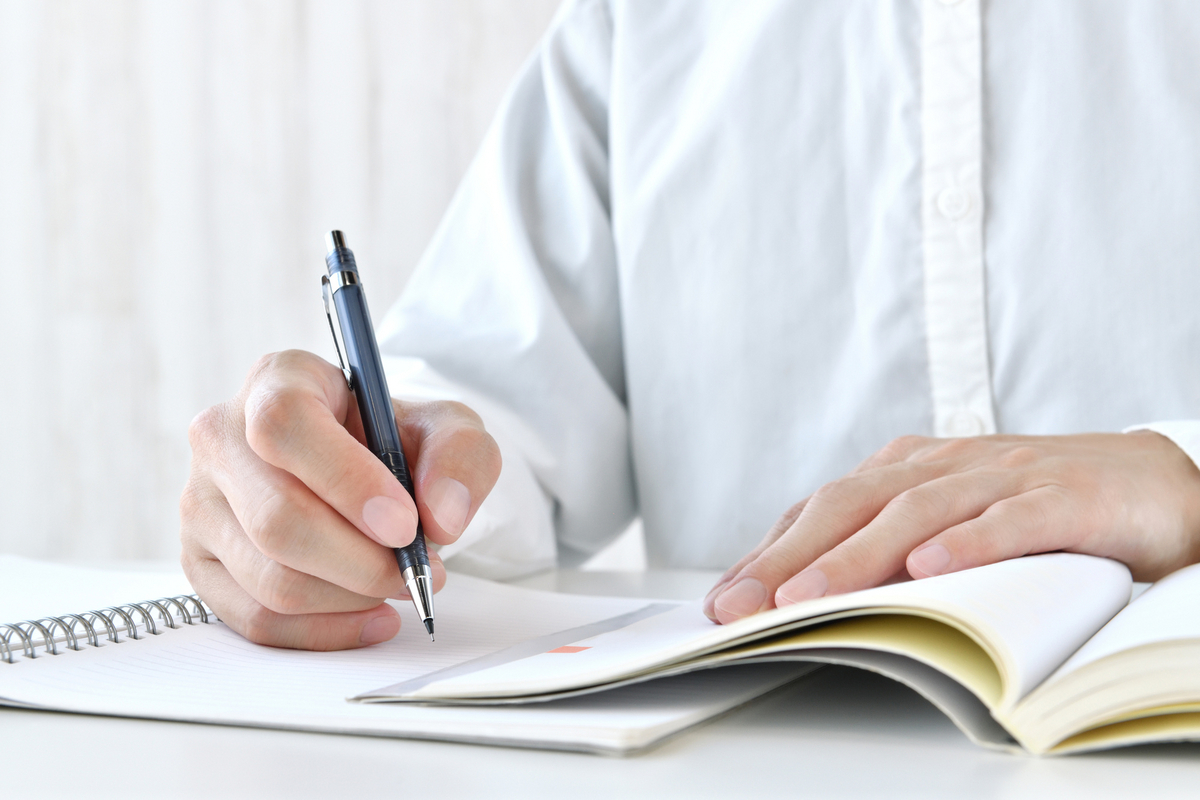
登録販売者になるまでの大まかな流れを紹介します。転職後の働き方をイメージするための参考にしましょう。
登録販売者試験に合格する必要がある
登録販売者として働くためには、登録販売者試験に合格しなければなりません。試験は都道府県が年1回実施しています。
登録販売者試験の合格率は40~50%です。難易度がそれほど高い試験ではありませんが、受験者の半数以上は不合格になっているため、しっかり勉強しておく必要があります。
登録販売者試験には受験資格が設けられておらず、誰でも試験を受けることが可能です。試験は年1回しか実施されないため、計画を立てて学習を進めましょう。
都道府県で販売従事登録を行う
登録販売者試験に合格したら、勤務先がある都道府県で販売従事登録を行う必要があります。試験合格後に転職する場合、転職先が決まらなければ登録申請を行えません。
販売従事登録を申請する場所は、都道府県の保健福祉課や業務課です。都道府県により申請先や名称が異なるため、事前に確認しておきましょう。
販売従事登録の申請には、登録申請書や合格通知書、戸籍謄本などの書類が必要です。医師による診断書の提出も求められるため、早めに準備しておきましょう。
実務経験を経て正規の登録販売者になれる
販売従事登録を行った後も、すぐに店舗で独り立ちできるわけではありません。1人で医薬品を販売できるようになるまでには、過去5年の間に1年以上の実務経験が必要です。以前は2年以上の実務経験が必要でしたが2023年4月に緩和されました。
未経験から登録販売者になる場合、登録販売者の管理下で研修を受けなければなりません。1年以上の実務経験を積めば、実務従事証明書が発行されて1人で売り場に立てるようになります。
登録販売者の実務経験年数にカウントできるのは、80時間以上働いた月です。勤務先が変わるとカウントがリセットされる点にも注意しましょう。
登録販売者はニーズの高い注目の資格

登録販売者とは、第2類・第3類医薬品を販売できる専門資格です。主にドラッグストア・スーパー・コンビニで働くことになります。
登録販売者になるためには、試験に合格した後に販売従事登録を行い、実務経験を積まなければなりません。仕事内容やなり方を理解し、転職を成功させましょう。
登録販売者として働ける場所を探す場合は、スタンバイで求人を探すのがおすすめです。全国の求人が数多く掲載されているため、自分に合った職場を見つけやすいでしょう。
