転職を考えている人にとって難しいのが、会社に退職を伝えるタイミングです。退職を伝えるのが早いと辞めづらくなると考える人もいますが、実際にはどうなのでしょうか?退職を伝える最適なタイミングや、スムーズに退職するためのポイントを解説します。
退職を伝えるタイミングが早すぎると?

会社に退職の意志を伝えるタイミングは、スムーズに退職をするための重要なポイントです。退職を伝えるのが早すぎると、以下の問題が発生する可能性があるので注意しましょう。
長期的な引き留めの可能性
退職の旨を会社に早く伝えてしまうと、実際に退職をするまでに、長く引き留めの説得を受ける可能性が増えるでしょう。
退職は仕事の引き継ぎを伴うため、上司だけではなく、仕事を引き継ぐ同僚などからも引き留められる可能性があります。多くの人から引き留められると、人によっては退職の意志がくじけてしまうケースも考えられます。
転職を決意したならば、意志が揺らがないように、伝えるタイミングに注意が必要です。
職場に居づらくなることも
会社に早いタイミングで退職の意志を伝えると、職場に居づらくなることもあります。上司に「どうせ辞める人だから」と思われ、責任のある仕事を回してもらえないなど、冷遇されてしまう恐れもあるでしょう。
さらに、周りの社員にも知られた場合、同じように「辞める人」として見られるため、人間関係に問題が生じる可能性もあります。
雑務ばかりを任されたり、周りから協力してもらえなかったりすることが考えられるため、タイミングを見計らうことが大事です。
退職を早めに伝えるメリット

退職の意志を伝えるのが早すぎると、長く引き留められたり冷遇されたりする可能性があります。
しかし、伝えるのが遅すぎると会社に迷惑をかけてしまうため、適切なタイミングを考えることが重要です。早めに退職を伝えるメリットについてもチェックしておきましょう。
余裕のある引き継ぎが行える
早めに退職の意志を伝えることで、余裕を持った引き継ぎが可能になります。多くの時間を使えるので、業務の引き継ぎ相手を誰にすべきかを含めて、慎重に決められるのがメリットです。
引き継ぎ用の資料なども、きちんと作り込めるようになるでしょう。特に、多くの業務を兼任している人の場合、複数の相手に引き継ぎが必要になるため、資料の作成と説明に時間がかかります。
相手に迷惑をかけないためにも、計画的に引き継ぎをすることが大切です。丁寧に引き継ぎをすることで、良い印象の中で退職できるでしょう。
有給休暇の消化を計画的に行える
計画的に有給休暇を消化できるのも、退職の意志を早めに伝えるメリットの1つです。自分の仕事をこなしながら、余裕を持って引き継ぎを済ませることで、計画的に有給休暇を消化できます。
事前に引き継ぎを済ませておけば、退職で周りに不要な負担をかける可能性が低く、罪悪感を持たずに休暇を満喫できるでしょう。
ただし、急にまとめて有給休暇を取得すると、会社に迷惑をかける可能性があるので、こちらも早めに伝える必要があります。
円満退職がしやすい傾向も
早めに退職の旨を伝えることで、円満退職がしやすくなる傾向もあります。
あまりに伝えるのが早すぎると、過度な引き留めにあったり、業務で冷遇されたりするリスクがあります。しかし、適切なタイミングで伝えれば、きちんとした引き継ぎが可能になり、会社側も新たに人員を補充する時間が持てるようになるでしょう。
自分が辞めた後の会社の負担を最小限にできるため、円満に退職できる可能性が高まります。いわゆる、「立つ鳥跡を濁さず」を実践できるでしょう。
一般的な退職を伝えるタイミングは?

退職を伝えるべきタイミングは、いつがよいのでしょうか?多くのビジネスパーソンは退職の際、1カ月前にはその旨を伝えています。ただし、企業によっては就業規則に明記されている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
多くは1カ月前が一般的とされる
会社に退職の旨を伝えるタイミングは、一般的に退職希望日の1カ月前とされています。例えば、8月末で退職を希望するならば、7月の後半には退職の意志を伝えるということです。
ただし、立場によっては引き継ぎに時間がかかるケースもあり、2~3カ月前に伝えている人も少なくありません。
就業規則に、1カ月前には退職の意志を伝える必要がある旨が記載されている会社も多いので、できるだけ余裕を持って申し出るようにしましょう。
就業規則もチェック
退職に当たり、就業規則を事前にチェックすることが必要です。
一般的に、1カ月前には退職の意志を伝える必要があるものの、就業規則で届け出の期間が定められているケースもあります。不要なトラブルを起こさないためにも、きちんと就業規則を確認するようにしましょう。
就業規則に明記された期限までに届け出が難しい場合は、早めに上司に相談することが大事です。法的には退職の意志を伝えるのは2週間前で問題ありませんが、会社に迷惑をかけないためにも、できる限り就業規則に準拠するようにしましょう。
法的には2週間前
一般的には1カ月前、就業規則によっては2カ月前など、退職を伝えるべきタイミングはさまざまです。
しかし、民法においては、期間の定めがない雇用の場合、退職する日から2週間前までに、退職の申告をする必要がある旨が記載されています。
たとえ企業側が退職を拒んだとしても、2週間前にきちんと意思表示をしているならば、法的に退職が可能ということです。
会社側もその事実は認識しているので、引き留められたとしても法令に準拠している限り、退職を拒否され続けることはないでしょう。ただし、会社側にできるだけ迷惑をかけないためにも、早めに退職の意志を伝えることが大事です。
働き方別で見る退職を伝えるタイミング

働き方別に、退職を伝えるタイミングを解説します。法律上は2週間前に退職の意志を伝えればよいとされていますが、それは期間の定めのない雇用の場合です。
働き方によっては、退職を申し入れるべき時期が変わってくるので、よく確認しておきましょう。
6カ月以上の報酬制の場合
民法第627条第3項では、以下のように定められています。
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
上記は、会社側からの契約解除の申し出に関する法令です。そのため、年俸制をはじめ6カ月以上の報酬制で雇用契約を結んでいる場合も、期間の定めのない雇用と同様、従業員側からの退職の申し出は2週間前までで問題ありません。
なお、期間によって報酬が決められる月給制では、月の途中で会社側から雇用契約の解除の申し入れがあることも考えられます。この場合、月の前半の宣告なら当月末、後半の宣告なら翌月末の契約解除となります(民法第627条第2項)。
こちらも会社に対する法令であるため、従業員が退職を申し出るタイミングは2週間前まででOKです。
期間の定めがある雇用の場合
契約社員や派遣社員など、期間の定めがある雇用契約の場合、原則として契約期間中の退職はできません。
しかし、病気やけが、出産・介護など、やむを得ない理由がある場合は、契約期間中での退職も可能です。期間の定めがない雇用契約のケースと同様に、2週間前までに退職の申し出をしましょう。
また、期間の定めはあるものの、契約期間が5年を超えているケースや、契約の終期が不確定なこともあります。
この場合は5年を経過した時点で、会社側・社員側のどちらからも契約の解除が可能です。退職希望日の2週間前までに、退職の旨を伝えれば問題ありません。
スムーズな退職に必要なポイント
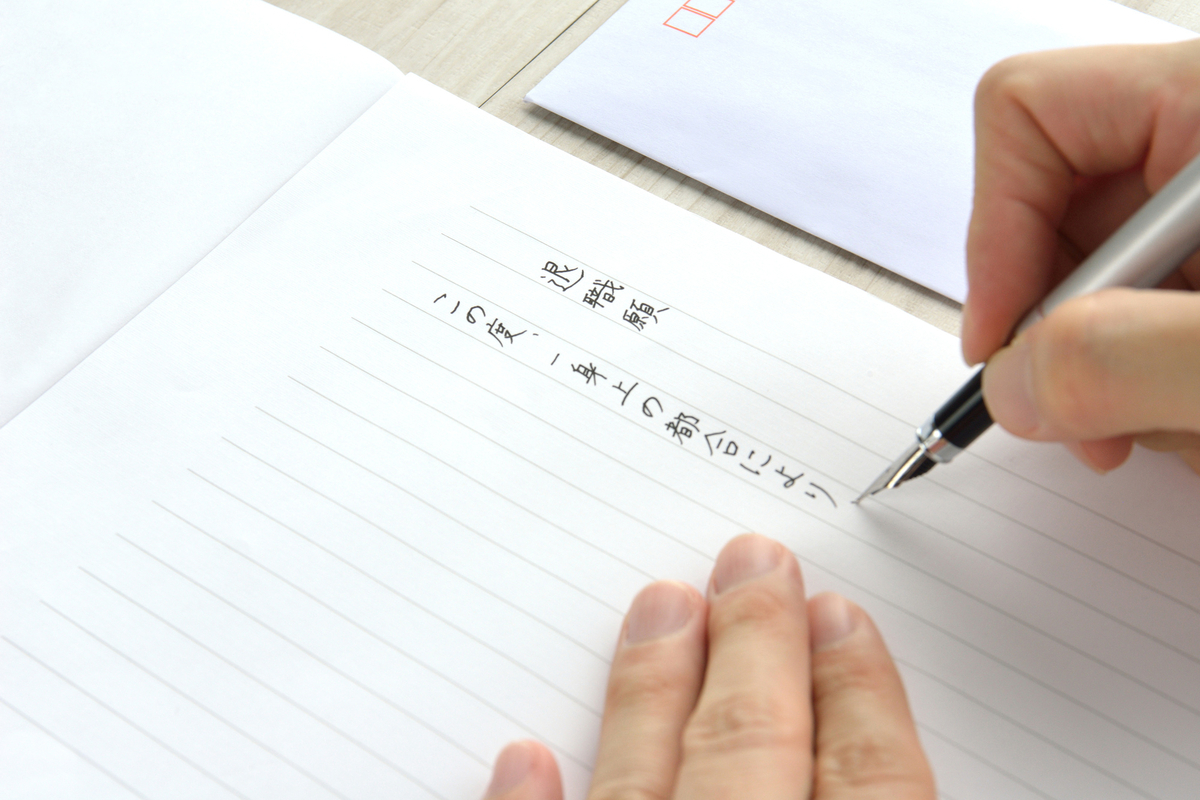
できるだけ会社に迷惑をかけず、スムーズに退職するためのポイントも押さえておきましょう。事前に伝えるべき退職理由を考えておき、できる限り繁忙期を避けて伝えることが大事です。
退職理由はポジティブに伝える
たとえ会社に不満があって退職を決意した場合でも、ネガティブな理由にしない方が無難です。とはいえ、うその理由を伝えるべきではありませんが、ポジティブに言い換えるようにしましょう。
例えば、職場の人間関係の悪さが原因で退職したい場合、ダイレクトに伝えるのは避ける必要があります。
新しい環境で、自分のスキル・経験を生かして活躍したいといったように、うまく言い換えると角が立たずに済みます。業務内容が合わない場合でも、同じような理由に変えるとよいでしょう。
退職の意志を強く持つ
タイミングを見計らって退職する旨を伝えた場合でも、上司や同僚から引き留められる可能性はあります。引き留められた場合にも、退職の意志が固まっているならば、きちんとその旨を伝えるようにしましょう。
引き留める際に「条件を良くする」などと言われても、ぐらつかないことが大事です。たとえ良い条件を提示されたとしても、実現してもらえるとは限りません。
きちんと考えた上で退職・転職の道を決めたならば、他者の意見に揺らがない意志を強く持ちましょう。
できるだけ繁忙期は避ける
早めに退職の意志を伝える場合でも、できるだけ繁忙期は避けた方がよいでしょう。繁忙期に伝えた場合、忙しさから上司が拒否することも考えられます。周囲との関係も険悪になり、仕事がしづらい環境に置かれる可能性も否めません。
また、自分が担当するプロジェクトがある場合も、避けた方が無難です。プロジェクトを投げ出して退職するイメージを、持たれてしまう恐れがあります。できる限りプロジェクトを完遂させてから、退職の意志を伝えるようにしましょう。
退職に関するQ&A

退職に関して、多くのビジネスパーソンが抱える疑問・不明点に回答します。上司以外に退職を伝えるべきタイミングや、転職先の情報に関する扱いなど、きちんと押さえておきましょう。
上司以外にはいつ伝えるべき?
上司以外の社員に退職の事実を伝える場合、業務に差し支えがないならば、基本的にはいつでも問題ありません。上司と相談した上で、伝えるべきタイミングを考えるとよいでしょう。
ただし、あまり早く伝えすぎると、職場の士気を下げてしまったり、人間関係に問題が生じたりする恐れがあります。
また、上司より先に周りの人間に伝えてしまうと、社内でうわさが広がり、トラブルに発展することも考えられます。同僚に退職の意向を伝える際には、必ず前もって上司に伝えておくことが大事です。
転職する場合は転職先を伝えるべき?
転職を理由に現在の会社を退職する場合、転職先の情報を伝えるべきか悩む人は少なくありません。上司・同僚などから、聞かれる場合もあるでしょう。しかし、基本的には、転職先の情報を明かす必要はありません。
むやみに情報を開示することで、不要なトラブルに発展したり、転職先についてネガティブなことを言われたりする可能性もあります。転職先の企業の情報を守る意味でも、余計なことは伝えない方が無難です。
退職をメールで伝えるのはあり?
退職の申し出は、原則メールではなく、上司に直接伝えるようにしましょう。
メールでも退職の意志が伝われば問題ありませんが、相手がメールを確認していない可能性があるのに加えて、一般的なマナーとしても直接伝えた方がよいとされています。ただし、退職の意志を伝えるためのアポイントを取るのは、メールでも構いません。
また、近年はオンラインでのビデオ通話で、社員同士がコミュニケーションを取る機会も増えています。画面越しではあるものの、相手と面と向かって話せる環境であるため、ビデオ通話で上司に退職の意志を伝えるのは問題ないでしょう。
タイミングを見極めてスムーズな退職手続きを

退職を伝えるタイミングは、法的には退職希望日の2週間前で構いませんが、一般的には退職日の1カ月前といわれています。ただし、立場によっては、2~3カ月前に余裕を持って伝えておいた方がよいケースもあります。
伝えるのが早すぎると、過度に引き留められたり、職場に居づらくなったりするリスクもあるので、タイミングを見計らうことが大事です。
社内での立場や仕事内容に応じて、最適なタイミングを考えましょう。有給休暇が残っている場合は、消化する時期も考える必要があります。
実際に退職の旨を伝える際には、ポジティブな内容にするとともに、できるだけ繁忙期を避けるのもポイントです。上司や同僚から引き留められても、退職の意志を強く持ちましょう。
