休職中は仕事ができない焦りや、生活費への不安が付きまといます。休職中の不安を少しでも減らすために、給与の有無や利用できる制度について確認しましょう。また、休職までの流れや、注意点などについても詳しく紹介します。
休職中に給与はもらえるの?
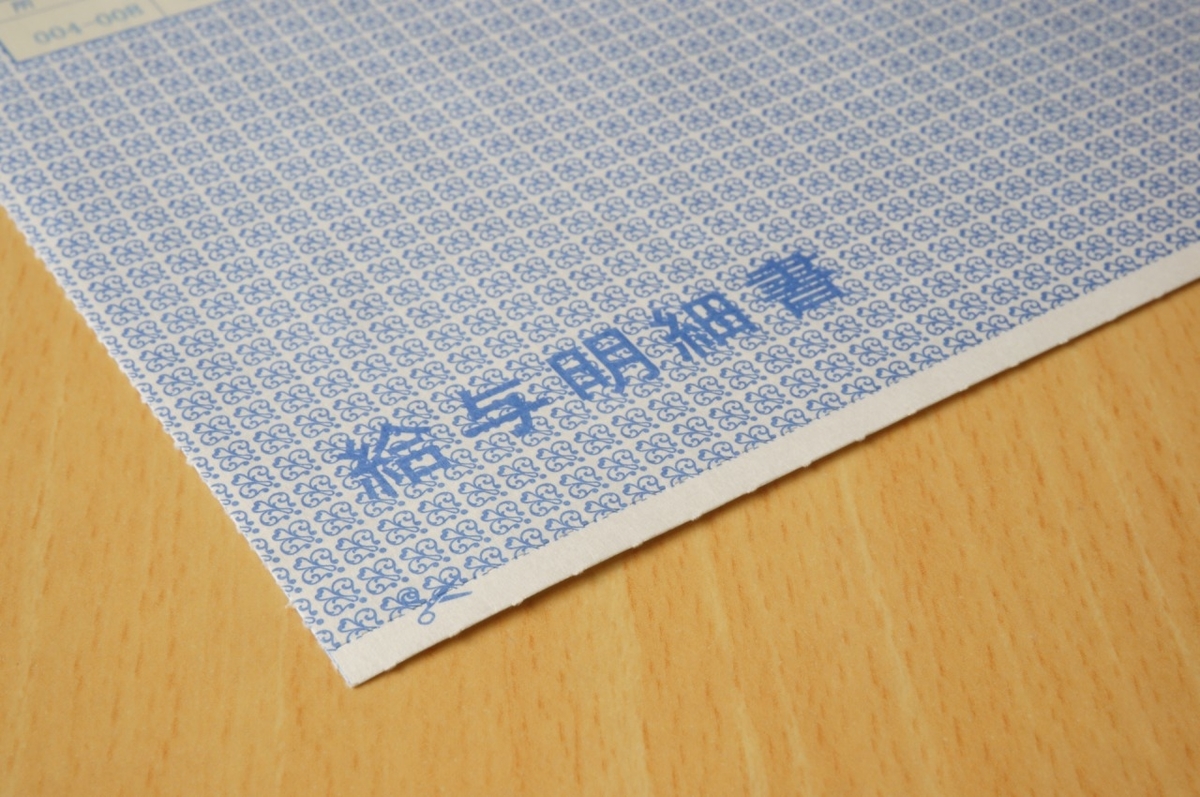
働けない期間は、生活費や療養費のことが不安になります。休職中に収入があると、安心だと感じる人は多いはずです。休職中の給与はどうなるのか、見ていきましょう。
給与はもらえないケースが一般的
自己都合や私傷病で休職している場合、給与はもらえないケースが一般的です。 労働契約は、雇用主と労働者の双方が同意することで成立し、給与は労働の対価として支払われます。
会社に在籍していても働いていない状態では、従業員に賃金を支払う義務はないので、ほとんどの場合は無給になるのです。
休職制度自体が会社の独自の制度であり、労働基準法や労働契約法といった法律上、休職中の人に会社が賃金を支払わなければならない定めはありません。就業規則に休職中の給与を一部負担するといった記載がない限りは、もらえないと考えましょう。
給与補償制度を設けている会社もある
休職中の従業員を支え、スムーズに復職してもらえるように給与補償制度を設けている会社もあります。就業規則に、休職中の給与に関する記載がないかチェックしてみましょう。
もらえる場合でも、給与の全額ではなく一部であることがほとんどです。少額であっても、もらえる場合は待遇が手厚いといえるでしょう。
なお、国家公務員は民間の企業に比べて待遇が手厚く、私傷病による休職期間中(病気休暇)も一定の期間(連続90日まで)は、100%の給与が保証されています。
会社都合による休業は6割を支給
自己都合で働けない場合と違い、会社都合で働けない場合は法律上のルールが設けられています。労働者側には働けない理由がないにもかかわらず、会社側の事情で休業する場合、雇用主は労働者に「休業手当」を支給する決まりです。
会社は、休業中でも平均賃金の「6割以上」を労働者に支払わなければなりません 。このような決まりがないと、労働者が会社の都合に振り回されて賃金を得られない可能性があるため、法律でしっかりと定められています。
休職の基本知識
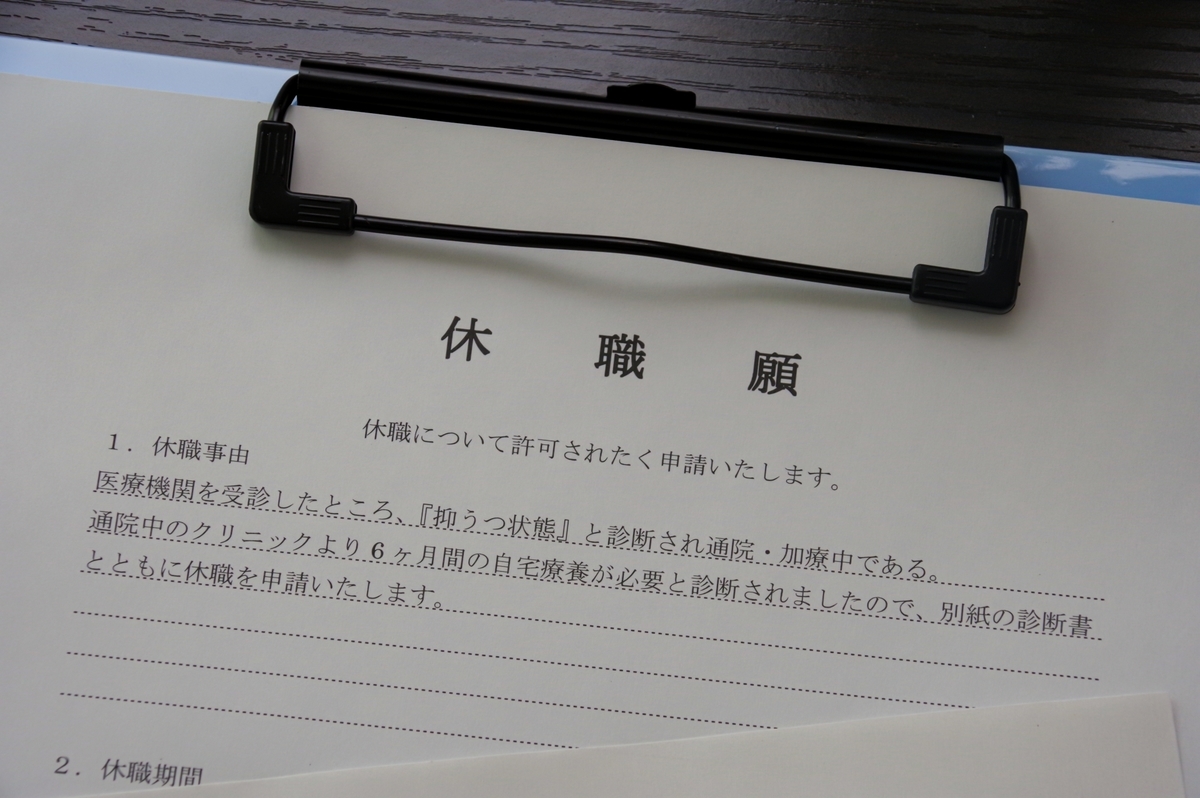
働けない事情が生じたとき、誰もが休職できるわけではありません。休職に対して間違った認識を持っていると、当てが外れて大変な思いをしてしまう可能性があります。休職に関する基本知識をチェックしましょう。
労働契約を維持しつつ就労を免除されること
休職とは、病気・けがなどで働けない事情ができてしまったとき、退職せず会社に在籍したまま就労を免除されることです。
会社を辞めれば収入がゼロになってしまいますし、再度同じ条件の職に就けるとは限らないので、休職制度を利用できれば心強いといえます。
休職制度に法律上の決まりはなく、義務ではありません。正社員であっても、休職制度がない企業も存在します。利用できるか分からない場合は、就業規則をチェックしましょう。
雇用形態によって条件や詳細が異なることも珍しくないので、内容をしっかりと確認することが大事です。
休職の種類
病気・けがを治す目的で、一定期間業務を休まなければならなくなったときに休職することを「傷病休職」と呼びます。
個人的なケガや病気で休職する場合(私傷病休職)と、業務が原因で発症した病気・ケガによる休業(業務災害による休業)、通勤中の事故が原因で負傷し休業する場合(通勤災害による休業)は、区別しておく必要があります。
休職の期間や復職する際の判断基準などは、会社によって違います。詳細は就業規則を確認しましょう。
休職中にお金を受け取れる制度
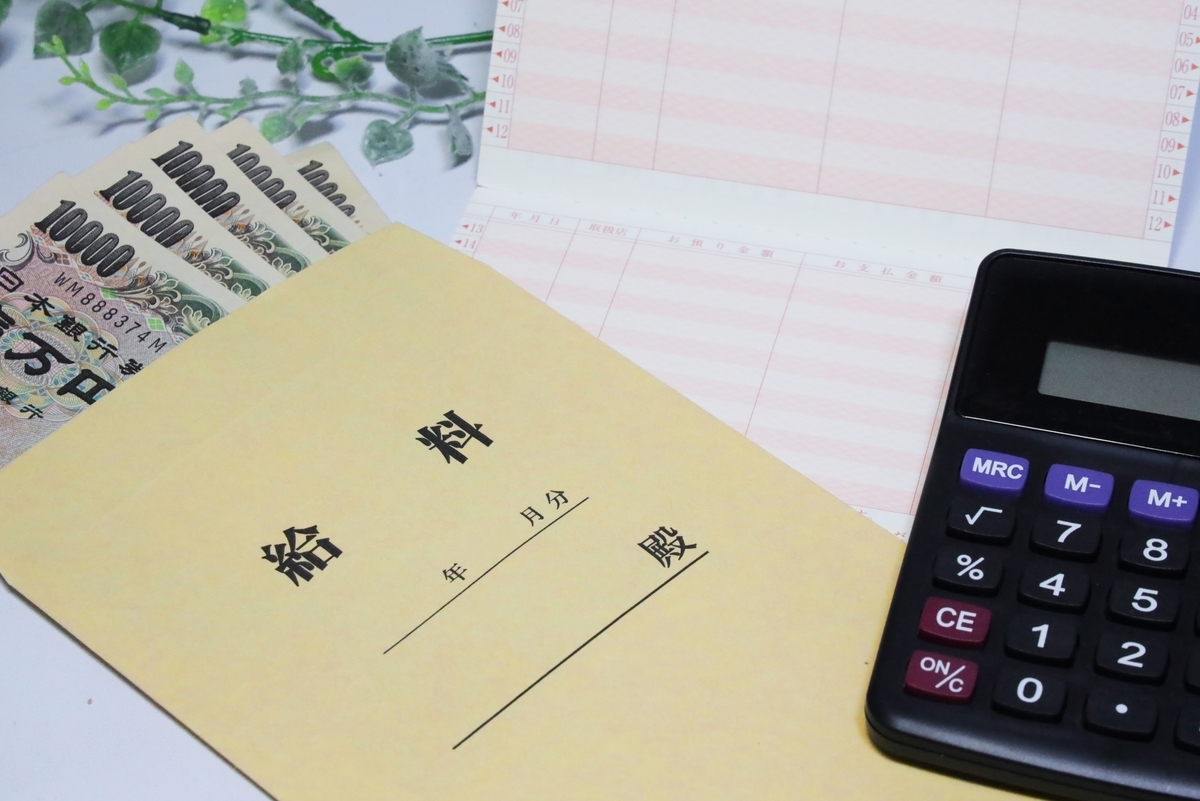
休職中に会社から給与をもらえなくても、お金を受け取れる制度を利用すれば、生活費を確保できる可能性があります。どんな制度を利用できるのか見ていきましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険制度から支給されるもので、健康保険制度(協会けんぽ、健保組合)の被保険者が対象です。
業務外の病気・けがが原因で4日以上仕事を休み、労務不能だと判定されているなど、一定の条件を全て満たしている場合に受け取れます。1日当たりの支給額を出す計算式は、以下の通りです。
- 【傷病手当金の支給開始日以前12カ月間の、標準報酬月額の平均額】 ÷30日×2/3
つまり、月給のおよそ「2/3」が支給される計算になります。支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
- ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- イ 標準報酬月額の平均額
会社が加入している健康保険組合によっては、組合が定める標準報酬月額を元に算出するパターンになっている場合もあり、微妙に額が異なります。受け取れる期間は、支給開始日から通算して「1年6カ月」までです。
労災保険
業務中・通勤中の事故や、労働が原因の病気などが発生したときは、労災保険の休業補償を受けられます。労働者を1人でも雇用している会社は、労働者を労働保険へ加入させることが義務付けられています。
仕事が原因で病気・けがをした人に、治療費などを自己負担させないよう、治療にかかるお金や労働基準法の規定に基づいて、賃金の補償をする決まりです。
労災保険は、派遣社員や請負契約の労働者を除く「全ての従業員」が対象となり、パートやアルバイトでも休業補償を受けられます。
障害年金
状況によっては、休職後の生活が不安な人もいます。病気・けがなどで思うように働けなくなってしまった場合は、障害年金を受け取れる可能性があります。
障害が残り、元通りに働けなくなってしまった人の生活を支えるのが障害年金です。対象者は、厚生年金・国民年金のいずれかに加入し、年金を納めている人となっています。
障害基礎年金の受給には一定の要件が必要であり、障害の程度に応じた等級区分が適用されて、障害基礎年金が支給される仕組みです。年金は高齢者がもらうものだと思っている人は多いですが、障害年金の場合は現役世代でも受け取れます。
障害年金(受給要件・請求時期・年金額)|日本年金機構
休職までの流れ

休職制度がある場合でも自己判断して休めるわけではなく、一定の手続きが必要です。どのような流れで進めていけばよいのか見ていきましょう。
医師から診断書を受け取る
会社の休職制度を利用するには、医師の診断書を提示する決まりになっている場合がほとんどです。就業規則で提出が義務付けられているか、確認しましょう。
診断書を提出すれば、病気・けがで働けない状態を客観的に理解してもらえます。受診している医療機関で、診断書を発行してもらいましょう。診断書の手数料は、診断内容によって1部につき2,000~10,000円程度です。
会社によって規定が異なり、事業者が選任する産業医の診断が必要なケースもありますし、診断書がなくても所定の手続きが済めば休職が認められるケースもあります。
直属の上司に相談
休職の必要がある場合は、直属の上司に病気・けがで通院中である旨を伝え、現状を理解してもらいましょう。直属の上司とは、普段仕事の指示をしてくれている人を指します。
長期間仕事ができない状態になっている場合、何も報告しないと無断欠勤扱いされてしまう心配があるので、必ず報告が必要です。やりかけの仕事があるときは、どのように引き継ぎしたらよいかなども相談しましょう。
また、療養期間が事前に分かっていれば、伝えた方がスムーズに復職できます。上司に相談すると同時に、休職に必要な手続き方法などの確認もしましょう。
「休職届」を出す
休職を決意したら、必要書類を提出しなければなりません。診断書だけでなく、休職届を出して受理してもらう必要があり、書式が決まっている場合がほとんどです。
手続きがうまくいかないとトラブルの原因になるので、必要な手続きについて確認しておきましょう。
休職届には、申請年月日・所属部署・氏名などの基本情報や、休職希望期間・休職理由・診断書の有無・休職中の連絡先などを記載するのが一般的です。
療養中は、自由に体を動かせない状況になってしまうこともあります。電話や郵送などでも手続きは可能なので、自分の状況を伝えて手続き方法について相談しましょう。
「傷病手当金」の申請
休職届を提出したら、傷病手当金を申請します。必要な手続きをしない限り、自動的にお金がもらえることはありません。
申請書を入手するには、健康保険組合のホームページからダウンロードしたり、窓口で受け取ったりするなどの方法があります。医師に書き込んでもらう欄が設けられているタイプの場合、通院時に持参するのを忘れないようにしましょう。
加入している健康保険組合によって必要な書類が異なるので、事前に人事部の担当者に確認することをおすすめします。
休職中の注意点

休職をした経験がないと、心配事が多くなりがちです。無事に休職期間を過ごすために、事前に押さえておくべき注意点を見ていきましょう。
社会保険料の支払いが発生する
休職中に給与をもらえなくなったとしても、会社に在籍している状態に変わりはありません。休職中であっても、厚生年金保険料や健康保険料など、社会保険料の支払いが発生する点には注意しましょう。
休職が考慮されて減額になるわけではなく、原則として休職前と同額が必要です。多くの治療費が必要になる場合、負担が大きいと感じる人は多いでしょう。
勤務中は給与から天引きして支払われますが、休職中は給与がないので同じようにはいきません。どのような方法で社会保険料を納めるかは、会社によって異なります。休職前に、支払方法について確認しておきましょう。
休職中の経過報告や連絡先を把握しておく
休職中は、会社と連絡を取れる状態にしておきましょう。休職前に上司や人事部から、定期連絡をするように指示されることもあれば、会社から連絡をくれる場合もあります。
事前に、連絡方法や窓口について確認しておいた方がスムーズです。会社に療養中の経過報告をすることが目的なので、連絡の頻度は月に1回程度である場合が多くなっています。
療養中に連絡が取れなくなれば心配をかけてしまいますし、休職期間を終えた後スムーズに復職を目指すためにも、連絡を取れる環境を整えておきましょう。
休職制度がない場合は転職も視野に入れよう

休職制度や休職中の給与の有無は、会社によって異なります。給与がもらえなくても、病気・けがで労働できない期間中は傷病手当金を受け取れる可能性があり、療養中の生活を支えてくれます。
休職制度のない会社に勤めている場合、やむを得ずに退職することになる場合も少なくありません。復職したくても、療養後に転職せざるを得ない場合も多いはずです。
まずは療養に専念し、調子が戻ったら転職活動をしましょう。スタンバイでは、1,000万件以上の多種多様な職種の求人情報が見つかります。

あした葉経営労務研究所代表。特定社会保険労務士。法政大学大学院経営学研究科修了(MBA)、同政策創造研究科博士課程満期修了。人事・労務・採用に関するコンサルティングに一貫して従事。マネジメント向けの研修やeラーニングの監修も行う。
All Aboutプロフィールページ
