ボーナスを期待して返済計画などを立てている人は、ボーナスカットされると困ってしまいます。「ボーナスの減額は違法行為では?」と思う人もいるでしょう。ボーナスカットが問題になる場合や、退職予定がある場合の考え方などを紹介します。
ボーナスカットは違法?

これまでもらえていたボーナスがもらえなくなると、不満を感じる人が大半です。まずはボーナスカットは違法なのか、見ていきましょう。
ボーナスの不支給や減額は違法ではない
ボーナスの支給は法律で義務付けられているわけではありません。労働基準法上の扱いは、賞与として下記の要件を満たすものがボーナスに該当します。
- 労働者の勤務成績により、定期または臨時に支給される
- あらかじめ、支給額が決定しているわけではない
企業の業績や労働者の成績が悪かったり、就業規則や雇用契約書に記載されている条件が満たされたりしている場合、前年比で減額や不支給になったとしても違法ではないのです。
賃金や各種手当のカットは違法
基本賃金はボーナスと性質が異なり、企業側の都合で、労働者の合意なく一方的に減額することは労働基準法上、認められていません。
また就業規則で定められている、各種手当の未払いも違法となります。ただし、事前に就業規則の変更を周知し、労働者との合意を得た上での賃金や手当の減額は認められる場合もあります。
基本的には、企業の業績がよく労働者の勤務態度など大きな問題がない場合は、一方的に賃金や各種手当をカットすることはできません。
ボーナスカットが問題になる場合

労働者の成績や就業規則により企業側がボーナスカットできるといっても、問題になるケースもあります。どんな場合に問題になるのか見ていきましょう。
就業規則などに記載されている場合
あらかじめ就業規則や労働契約で「夏季に◯カ月分、冬季に◯カ月分支給する」など、支給条件が決められている場合は、企業側にボーナス支給の義務が発生します。
しかし、併せて「業績不振や労働者の勤務成績の悪化により、ボーナスの一部をカットすることがある」などの不支給条件が設けられており、条件に当てはまる場合は支給されなくても問題にはなりません。
ボーナスカットの明確な根拠がない場合
労働者がボーナスカットに相当するような明らかなミスをしていないのに、ボーナスカットされたり、減額理由の説明を求めたにもかかわらず十分な回答が得られなかったりしたときは違法と見なされる可能性があります。
企業側が労働者のミスによって、どのような損害を受けたのか説明が全くない状況では、労働者側の不満が高まりやすいでしょう。
また企業側から説明を受けても、労働者の責任範囲を超えた理由だったり、ほかの労働者との支給条件の公平性が乏しかったりする場合は違法と見なされる可能性があります。
懲罰やパワハラが理由の場合
従業員に不当な罰を与える目的や、パワハラによるボーナスカットは違法になります。また産休や有休を多く取っているなどの理由で、ボーナスの全額をカットする行為も認められません。産休や有休は労働者の権利として認められています。
なお、妊娠、出産、育児休業の取得等を理由とした不利益な取扱いは禁止されています。産休や有休の給与の扱いを確認しておきましょう。
退職予定のためボーナスが支払われない場合
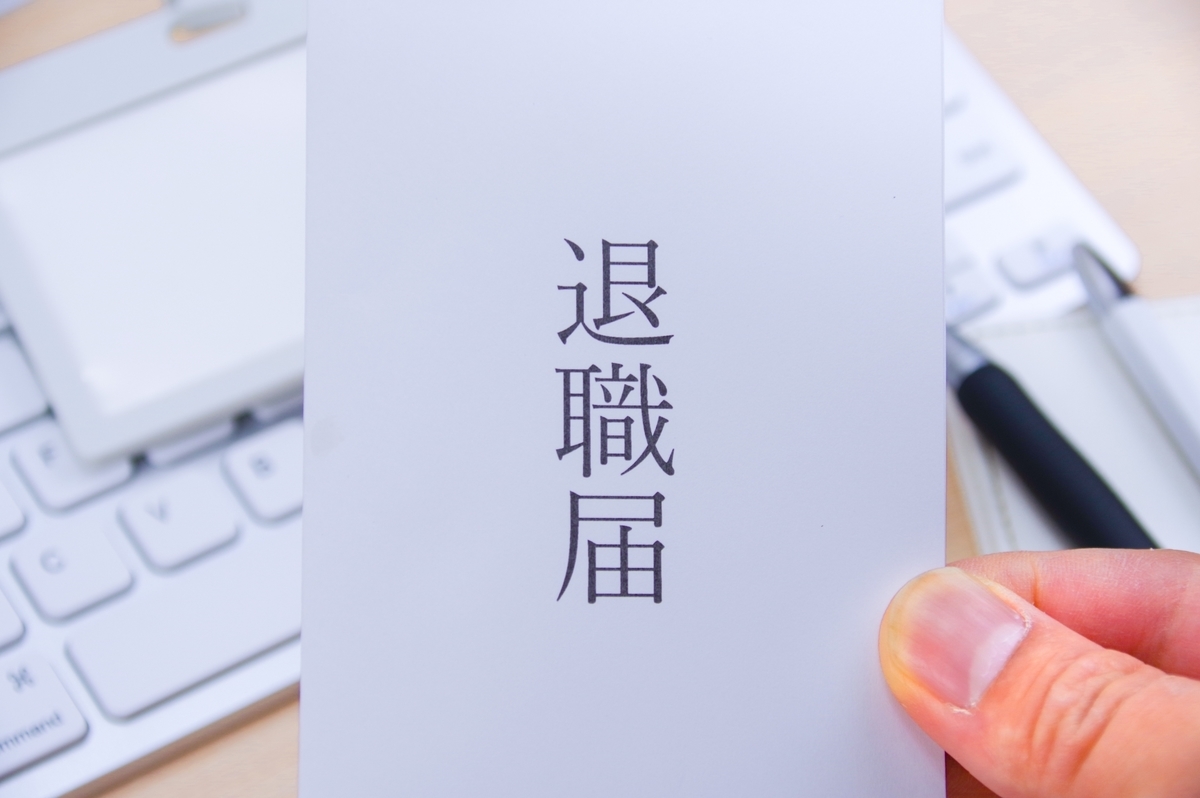
退職の予定がある場合、例年通りボーナスをもらえるのか不安になる人もいるでしょう。退職時のボーナスの考え方や注意点を紹介します。
減額が認められるケースは多い
ボーナスの支給日と退職予定日が近い場合、減額が認められるケースは少なくありません。
ボーナスは今後の労働に期待する意味合い、労働への対価として与えられるものなので、今後も継続的に働いてくれている人と退職者の支給額に差が出るのは不自然ではないでしょう。
退職予定の従業員に対し、ある程度の減額をすると就業規則で定められている場合、減額が認められることが一般的です。
在籍条項など支給の要件を確認
就業規則に支給日在籍条項があれば、内容を確認しておきましょう。支給日在籍条項は、ボーナスの支給日に在籍している従業員が支給の対象になるなど、詳しい条件が記載されています。
「退職するといっても、これまで会社に在籍していたのだからボーナスをもらえないのはおかしい」と感じる人もいるかもしれませんが、支給日在籍条項が定められているのであれば、退職後にボーナス減額やカットされる可能性があります。
ただし、会社都合や定年退職などで従業員が退職日を自由に決められなかった場合は、当てはまらない点を押さえておきましょう。
ボーナスカットされたらどうする?

ボーナスカットされたとき、根拠が妥当かどうか自分では判断できない場合があります。納得できない場合はどのような行動をすればよいのか見ていきましょう。
ボーナスカットの根拠を確認
ボーナスカットされたときは、まず就業規則や雇用契約書などに記載されているボーナスに関する項目をチェックします。ボーナスカットの根拠になる部分を重点的に確認し、該当する理由が適正なものか判断しましょう。
雇用契約書にボーナスに関する項目が明記されていなくても、慣例として支給されている場合は請求できる可能性がゼロではありません。
「記載内容通りにボーナスが支給されていない」「就業規則で定められていても、従業員に周知されない状況となっている」などの問題があれば、ボーナスカットが不適切だとして争う余地があります。
ボーナスありきの支出を見直す
ボーナスを必ずもらえるという労働契約になっていない限り、もらえないケースがあるのも自然なことです。ボーナスを当てにした支出が多ければ、もらえなかったときに苦しむことになってしまいます。
多くの収入があると思うと財布のひもが緩んでしまう人は、「計画的に家計を組み立てているか」を見直してみましょう。できれば、家計簿をつけて収入に対する支出額を可視化することがおすすめです。
家計簿をつけていると、税金・赤字の補填分・家具の買い替え・交際費費・飲食費などの項目ごとにボーナス支出後のお金の動きと共に、削れる支出も見えてきます。
転職を視野に動くこともおすすめ
道理に反する理由でボーナスがカットがされたり、業績アップが全く期待できない状態になったりしているなら、転職を視野に入れることもおすすめです。
会社への不信感や、将来性がないなどの不安を抱えたまま働くのは苦しく、自分の理想のキャリアプランからかけ離れてしまうかもしれません。
スタンバイでは、さまざまな職種の求人情報を扱っています。希望に合った転職先を探すために、ぜひチェックしてみましょう。
ボーナスカットされたら就業規則を確認

ボーナスの支給条件は、企業ごとに就業規則や雇用契約書で定められています。不明点がある際は確認しましょう。支給条件だけでなく、不支給となる条件も記載されていることが多いので、そちらも併せて確認します。
例えば業績不振に陥っているときは、減額されると明記されている場合があります。ボーナスの支給条件は変更になるケースもありますが、一方的な変更は認められず、きちんと従業員に周知しなければなりません。
ボーナスの減額やカットが認められる場合であっても、年俸制などで毎月の賃金として支払われる場合は、違法になる場合があります。

あした葉経営労務研究所代表。特定社会保険労務士。法政大学大学院経営学研究科修了(MBA)、同政策創造研究科博士課程満期修了。人事・労務・採用に関するコンサルティングに一貫して従事。マネジメント向けの研修やeラーニングの監修も行う。
All Aboutプロフィールページ
