勤務体系について詳しく知りたい人は、多いのではないでしょうか?勤務体系とは働き方を示す言葉で、さまざまな種類があります。勤務体系の正しい意味やメリット・デメリットと併せて、働きやすい職場の見つけ方も転職先参考にしましょう。
勤務体系(形態)とはどういう意味?
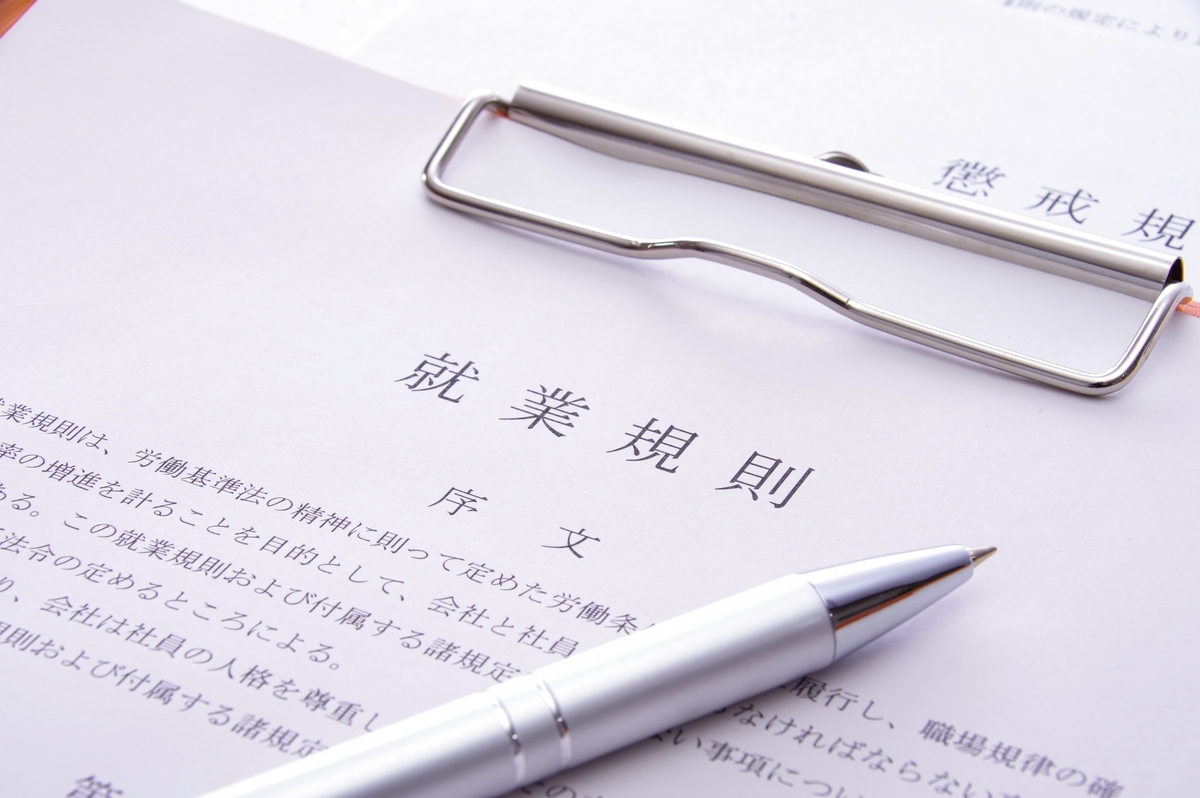
勤務体系の内容について詳しく知る前に、正しい意味を把握しておきましょう。似ている言葉として意味を取り違えられやすい「雇用形態」との違いも説明します。
従業員の働き方のこと
勤務体系とは、従業員の「働き方」を表す言葉です。勤務日や勤務時間帯・勤務頻度などのことで、細かく見ると固定時間制・シフト制、日勤・夜勤、常勤・非常勤などの区別があります。
近年は会社選びの際の条件として、働き方を重視する転職者が多くなってきました。在宅勤務・リモートワークのように、勤務する場所の違いも勤務体系として考えられるようになっています。
現代においては、柔軟な勤務体系を取り入れることが、企業にとっても優れた人材を確保するために有効な施策の1つです。
「雇用形態」とは全く別の言葉
雇用形態は、会社と労働者の間で交わされる「雇用契約」の種別です。勤務体系と雇用形態は紛らわしいため混同する人もいますが、全く異なる意味を持っています。
主な雇用形態の種類は、以下のようなものです。
- 正社員
- 派遣労働者
- 契約社員(有期労働契約者)
- パートタイム労働者
- 時短正社員
業務委託(請負)契約や家内労働者なども、企業に雇用されるわけではありませんが、同じく仕事における契約の形態を表す言葉として使われます。
雇用形態は同じ正社員であっても、日勤・夜勤など勤務体系が異なる場合もあると考えると、2つの言葉の違いを理解しやすいでしょう。
勤務体系(形態)の種類と特徴

勤務体系には、さまざまな種類があります。それぞれの働き方にはどのような特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。
固定時間制
固定時間制とは、始業・終業の時間が決まっている働き方です。労働時間は原則として、「1日8時間、週40時間を超えてはならない」と労働基準法の第32条に定められています。
会社側から見ると、固定時間制は労務管理しやすい点がメリットです。従業員側からすれば、勤務日と時間が決まっているため先の予定を立てやすいでしょう。
しかし、1日8時間は必ず拘束される上、土日が休みであれば平日にしか営業していない行政機関や銀行に行きにくいというデメリットもあります。また、急な予定が入ったときに対応しにくいことも難点です。
変形労働時間制
変形労働時間制は、労働時間を月単位・年単位で調整する働き方です。シフト制も変形労働時間制の一種です。
変形労働時間制を導入している企業では、1カ月単位で就労時間を設定していることが多く、「1日8時間、週40時間以内」の法定労働時間内に収まるように月間の就業時間を定めます。
変形労働時間制には、自分の都合に合わせて勤務日・勤務時間を決められるというメリットがあります。
一方で、希望する勤務日に必ず就業できるか分からなかったり、先の予定が立てにくかったりという点がデメリットです。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、一定期間内の労働時間が法定労働時間内に収まる範囲で、従業員が自由に始業・終業の時間を決められるシステムです。
1日の労働時間のうち、出勤・退勤の時間を自由に決められる「フレキシブルタイム」と、必ず勤務していなければならない「コアタイム」を設定して運用されます。
従業員にとっては、出勤時間をずらすことで子どもの送り迎えや親の介護などをしやすくなったり、ワーク・ライフ・バランスを取りやすくなったりするのがメリットといえるでしょう。
しかし、社内や取引先との間で就業時間がずれるため、社員同士のコミュニケーションを取りにくい、定時がなく労働時間の管理が難しいといったデメリットもあります。
みなし労働時間制(裁量労働制)
みなし労働時間制(裁量労働制)は、事前に決めた時間を働いたと「みなす」制度で、労働者が労働時間の配分を任されることが多い働き方です。みなし労働時間制には、以下の3種類があります。
- 事業場外みなし労働時間制:営業職のように事業場以外で業務に当たる場合に適用される
- 専門業務型裁量労働制:デザイナーやSEのように専門性の高い業務を遂行する場合に適用される
- 企画業務型裁量労働制:事業運営の企画や立案・調査・分析を行う業務について適用される
時間に縛られずに就業のスケジュールを決められる点が、従業員側から見たみなし労働時間制のメリットです。
一方、労働時間が長くなったとしても残業代は支払われません。ただし、みなし労働時間が法定労働時間を超えれば、その時間分の割増賃金は上乗せされます。
テレワークとは?

近年よく聞かれるようになったのが、テレワークという働き方です。新型コロナウイルス感染症拡大がきっかけで導入を始めた企業が増えたため、テレワークで働ける仕事への転職を希望している人もいるはずです。
テレワークの定義について、正しく理解しておきましょう。
時間や場所にとらわれない働き方のこと
テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用して、時間・場所を選ばずに仕事をする働き方のことです。日本でも働き方改革の一環として、また2020年からは感染症対策として広く浸透し始めました。
総務省が行った「通信利用動向調査」によると、日本でテレワークを導入している企業の割合は2021年で51.9%と半分を超えています。
今後導入予定がある企業を加えると57.4%と6割近くに達していることから、これからもますます増えていく働き方の1つといえるでしょう。
リモートワークとテレワークは同じ意味
テレワークと似た言葉に、「リモートワーク」があります。リモートワークもテレワークと同様、オフィス以外の場所で仕事をする働き方のことです。リモートワークには明確な定義がなく、遠隔で行われる業務全般を指します。
リモートワークという言葉も、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけとして一気に浸透しました。テレワークとリモートワークは同じ意味の言葉と考えて問題はありません。
ただ、リモートワークという言葉はIT企業やベンチャー企業・フリーランスなどの間で使われることが多く、官公庁をはじめ公的な機関ではテレワークと表現されています。
テレワークの主な種類
テレワークを細かく見ていくと、主に「在宅勤務」と「モバイルワーク」「サテライト勤務」の3種類の働き方に分かれます。それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
在宅勤務
在宅勤務は職場から離れ、自宅で就業するスタイルです。全く出社しないわけではなく、週に数日ずつ在宅・出社を組み合わせた勤務方法を取り入れている企業がほとんどです。
午前・午後のみ在宅で勤務するなど、1日のうち一部だけ在宅勤務を実施する「部分在宅勤務」を導入している企業も珍しくありません。
また、在宅勤務というと、正社員・契約社員のような雇用形態での働き方という印象を持つ人が多いでしょう。しかし、業務委託・請負など雇用されていない場合も、「自営型テレワーク」として在宅勤務に該当します。
モバイルワーク
モバイルワークも、オフィス以外で仕事をする働き方です。在宅勤務と似ていますが、働く場所に違いがあります。
在宅勤務が会社の就業時間内に自宅で勤務することを指すのに対し、モバイルワークは電車やバスなどでの移動中や、カフェ・ホテルなどで仕事をすることもあり、場所も時間も選ばないのが特徴です。
モバイルワークは常に外で仕事をするわけではなく、営業職が外出中の隙間時間に業務を行うケースが多いでしょう。
サテライトオフィス勤務
本拠地のオフィスから離れたところに設置したワークスペースで就業する施設利用型の働き方です。自宅に近い場所に設置されたサテライトオフィスなどを活用する働き方が一般的です。
働きやすい職場に転職するには?

勤務体系にはさまざまな種類があり、どの働き方がいいと一概には言えません。自分に合った「働きやすい職場」へ転職するためのポイントを押さえて、仕事探しに役立てましょう。
自分に合った働き方(勤務体系)を考える
働きやすい転職先を探すためには、まず勤務体系ごとのメリット・デメリットを比較して、どの働き方が自分に合っているのかを見極めるところから始めましょう。
マッチする勤務体系が分からないときは、生活スタイルや譲れない条件などを書き出してみるのもよい方法です。
例えば、土日は必ず休みたい人には、平日勤務の固定時間制が向いています。日中に子どもの送り迎えや家事で仕事を離れる必要があるなら、フレックス制や在宅勤務制が両立しやすいでしょう。
転職サイトを活用する
数ある企業の中から希望に合う転職先を見つけるには、転職サイトを活用するのがおすすめです。転職サイトなら、いつでも好きな時間に自分のペースで転職活動できます。
スタンバイでは、勤務体系の他にもこだわりの条件での検索が可能です。さまざまな企業の求人情報を手軽に閲覧できます。
掲載されている求人数が豊富で、希望の働き方を実現できる仕事に出会いやすいのもうれしいポイントです。
働き方以外も大切に
福利厚生が充実しているか、教育制度がしっかりしていてキャリアアップしやすいかなども、やりがいを持って仕事をするためには大切な要素です。求人情報や会社概要をしっかりチェックしておきしょう。
また、会社の方針に従えるかどうかも、働きやすさに影響します。入社後のミスマッチを防ぐためにも、企業のWebサイトで経営理念やポリシーを自身のキャリアと照らし合わせましょう。
社員インタビューや口コミサイトなどで、会社が目指す方向性や雰囲気をつかんでおくのも1つの方法です。
自分に合う勤務体系の仕事を見つけよう

働き方の多様化に伴い、勤務体系にもさまざまなパターンが増えています。近年は在宅勤務・リモートワークを導入する企業が増えてきており、これまで以上に働き方を選べるようになりました。
現在の職場の勤務体系が合わないと感じたら、別の働き方を考えてみるのもおすすめです。
それぞれの働き方のメリット・デメリットを比較するだけでなく、ライフスタイル・考え方に合った勤務体系を選ぶことが、働きやすさにつながるでしょう。

あした葉経営労務研究所代表。特定社会保険労務士。法政大学大学院経営学研究科修了(MBA)、同政策創造研究科博士課程満期修了。人事・労務・採用に関するコンサルティングに一貫して従事。マネジメント向けの研修やeラーニングの監修も行う。
All Aboutプロフィールページ
