休職には、収入減や復職の不安などのデメリットがあります。休職中の給与の扱いや社会保険料についても、理解しておかなければなりません。休職したとしても状況が変わらないようならば、転職も視野に入れ、自分にとって最善の道を選びましょう。
この記事のポイント
- 休職とは
- 仕事に復帰するための前向きな休みであり、休業や欠勤などとは意味合いが異なります。
- 休職する際の注意点
- 会社の就業規則をあらかじめ確認し、休職中の給与やルールについて把握しておきましょう。
- 休職ではなく転職した方がよいケースも
- 休職期間中に状況が改善しない場合、復職を目指すよりも転職の方が適切な選択となることもあります。
休職とは?休業・欠勤・退職の違い

休職と混同されやすい言葉に、「休業」「欠勤」「退職」がありますが、それぞれ意味が異なります。混同しやすいこれらの言葉について、具体的な違いを見ていきましょう。
休職とは?期間・条件もチェック
休職とは、個人的な理由によって契約を結んだまま業務から離れ、一時的に休みを取ることを指します。例えば、病気・けが・メンタル面の不調・家庭の事情などで、一時的に仕事に従事するのが難しいケースが当てはまります。
就業規則などにもよりますが、休職できる期間は、一般的に3カ月〜3年程度とされています。
休職中に心身を回復させたり、家庭の事情に対応したりする時間を確保し、しっかり働けるようになった状態で戻ってくることが前提です。
休職中は雇用契約が維持され、給与や福利厚生が一部支給されることもありますが、会社の就業規則や契約内容によって休職できる条件や期間は異なります。
休業・欠勤・退職との違い
休職と似ている言葉に、休業・欠勤・退職がありますが、以下の通りそれぞれ意味が異なります。
- 休業:従業員が働く意欲を持っているにもかかわらず、会社が一時的に業務を停止している、もしくは従業員が何らかの理由で業務ができない状態です。休業中は通常、雇用契約が続いており、会社から手当が支給されることもあります。
- 欠勤:会社の稼働日に出勤をしないことです。無断で休む場合も欠勤に該当します。病気や私用で欠勤すると、休職とは違い、欠勤控除によって給与が支払われないケースが多いでしょう。
- 退職:会社を辞めることを意味します。退職すると雇用契約が終了するので、休職中に受けられる支援や福利厚生はなくなります。
休職するとどんなデメリットがある?

しっかり休んで心身ともに元気になった方がよいと分かっていても、やはり休職することのデメリットが気になる人も多いでしょう。特に、経済面や保険料の負担については、事前にしっかり理解しておく必要があります。
収入がなくなる
休職の大きなデメリットとしてまず挙げられるのが、収入がなくなることです。健康上の理由や家庭の事情で休職する場合、収入がなくなることで生活費の確保が難しくなるかもしれません。特に長期間の休職となると、経済的な不安も増すでしょう。
ただし、会社によっては、給与の一部を支給することが一般的です。場合によっては、賞与も支給対象になります。休職を考えているならば、休職前に就業規則や休職に関する会社の方針を確認することが大切です。
社会保険料は支払い続けなければならない
休職中でも、社会保険料の支払いは続けなければなりません。社会保険料とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険を指します。
休職している間は、給与が全く支給されない場合でも会社との雇用契約が維持されるため、社会保険に加入した状態が続きます。
つまり、給与の有無にかかわらず、社会保険料を支払う必要があるということです。具体的には、以下3つの社会保険料が対象です。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料(40歳以上の加入者)
会社によっては、休職中の社会保険料を一部負担してくれる場合もあります。また、雇用保険料は給与に連動しているため、給与が支給されない場合は支払う必要はありません。
社内評価や今後のキャリアへの影響
休職中でも会社との契約は続いているため、基本的には昇進・昇格に影響が出ることは少ないと考えられます。しかし、休職が長期化した場合は、影響が出ないとは言い切れません。
例えば、評価基準に業績や貢献度が含まれている場合、休職期間中はその部分でのアピールができないため、昇進・昇格が難しくなる可能性もあります。
ただし、休職の理由が正当なものであれば、会社側はその状況を理解し、評価を公正に行う場合がほとんどです。
休職の影響を過度に心配し無理をして働き続けることは、健康やメンタル面に悪影響を与える可能性があり、長期的に見ると逆効果になることもあります。休職後の評価を気にして無理を重ねるよりも、自分の健康を最優先に考えましょう。
復帰できない可能性がある
休職後、復帰が難しくなる可能性も考えられます。特に精神的な不調が原因で休職していた場合、復職に対して不安やプレッシャーを感じるかもしれません。周囲に迷惑をかけたのではないかという罪悪感が、復職へのハードルを高くすることもあるでしょう。
また、休職が長引くと、就業規則に定められた休業期間を超えてしまう恐れもあります。会社側から復職を認めてもらえないこともあるため、復帰への不安が増すかもしれません。
会社によっては、休職期間終了後に復職できないケースや、退職を選ばざるを得ないケースもあります。休職前に就業規則を見直しつつ、担当者とコミュニケーションを取り十分確認しておきましょう。
休職のメリット
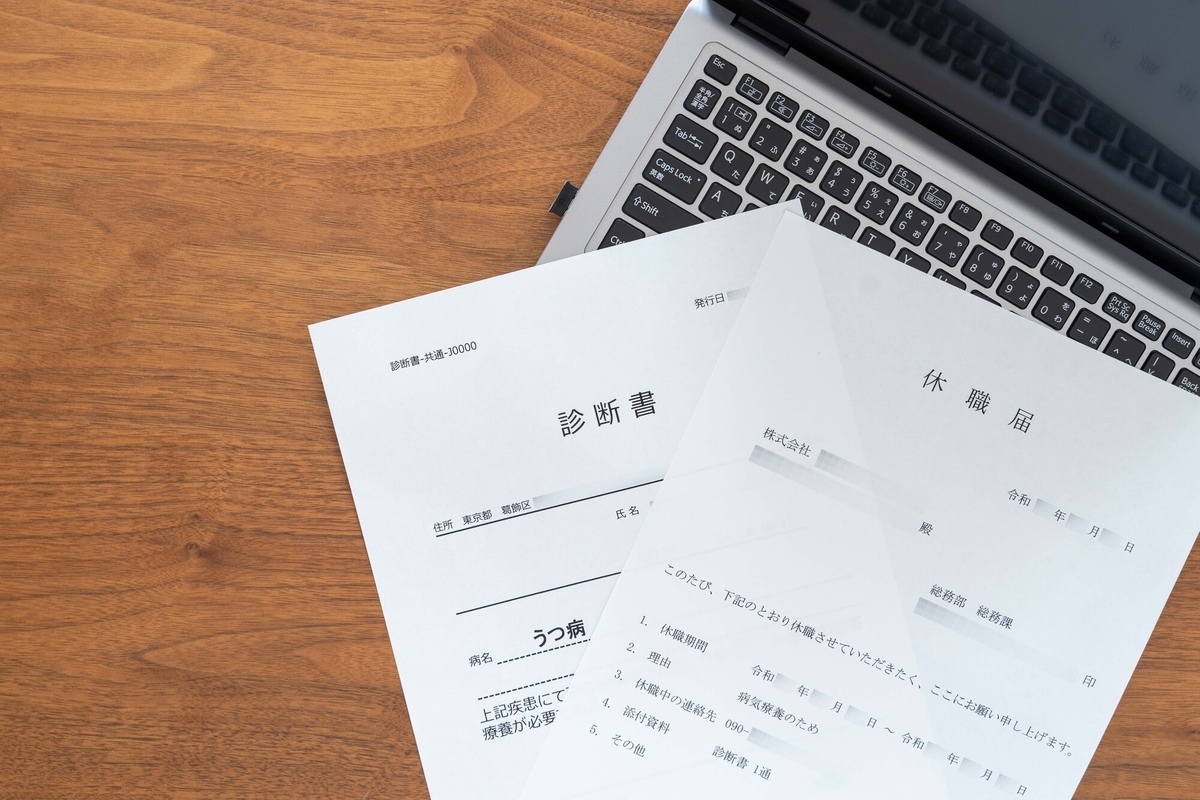
治療・療養にじっくり専念できることや、雇用契約が維持されている安心感など、休職にはメリットもあります。休職をすることで得られるメリットについて見ていきましょう。
自分のキャリアを見直す時間を確保できる
休職中は、自分自身に向き合うために時間を使えます。自分が本当にやりたいことや、目指すべき方向性について、深く考えてみましょう。
別の部署に異動して新しい経験を積んだり、転職を考えたりするきっかけにもなります。例えば、子育てをしながら復職後に時短勤務を取り入れたいなど、自分のライフスタイルに合った働き方をイメージします。
自分の人生やキャリアについてじっくり考えることで、復職後のより自分らしい働き方が見つかるかもしれません。
治療・療養に専念できる
病気やけがで休職する場合、治療や療養に専念できる貴重な時間を得ることができます。仕事を離れることで、体調や精神面の回復が早くなるかもしれません。
無理に働き続けると症状が悪化し、後々さらに長期の休養が必要になるリスクがあります。
休職中は十分な休養を取って心身ともに回復し、より元気な状態で自信を持って仕事に戻ることを目指しましょう。
元の職場に戻れる安心感がある
休職中でも雇用契約は続くため、自分が依然として社員であるという安心感があります。休職の理由が何であれ、再び元の職場に戻れる場所があることは、精神的に大きな支えとなるでしょう。
例えば、業務量や職場環境が原因で休職していた場合、休職期間中に改善策が講じられていることが期待できます。
実際に改善されるかどうかは会社によりますが、休職中に職場環境が整備されれば、以前よりも働きやすくなった状態で復帰できるでしょう。
休職を決めたらどうすればよい?流れと休職中の過ごし方

休職を決意したら、まずは身近な上司に相談することが大切です。休職の具体的な手続きや、休職中の過ごし方について解説します。
休職の手続き4ステップ
休職を決めたら、スムーズに進めるために以下の4つのステップを踏みましょう。
- 休職制度を確認
まずは、自分の会社の休職制度についてしっかり確認します。休職の期間・給与や手当はどうなるのか・復職の条件・手続きなどを把握しておくことが必要です。会社の就業規則や福利厚生規定に記載されていることが多いので、それを参考にしましょう。 - 上司・産業医・人事部などの担当者に相談
休職を決めたら、上司や産業医、そして人事部門に相談します。休職理由や状況について率直に話すことで、必要なサポートが得られます。 - 必要書類の準備
休職の手続きに必要な書類を準備します。一般的に、休職願や医師の診断書が必要となります。 - 申請書類がそろったら、正式に会社に休職申請を出します。
申請後は会社の規定に従って休職期間が認められ、休職に入ります。休職中の過ごし方についても、会社からの指示やアドバイスを受けましょう。
休職中の補償や給付金・ローン返済支援
休職中でも、会社の就業規則によっては給与や賞与の一部を受け取れる場合があります。その割合や支給条件は会社ごとに異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
また休職中は、以下のような補償や保険も利用できる可能性があります。
- 傷病手当金:病気やけがが原因で休職する場合は、健康保険から傷病手当金が受け取れます。給与の6割程度を支給されるのが基本です。
- 労災の休業給付金:休職の原因が労災の場合は会社都合の休業となるため、給与の約8割の金額が受け取れます。
- 住宅ローン返済支援保険:加入している人はローン返済がカバーされます。条件は各保険で異なるため確認が必要です。
- 就業不能保険や所得補償保険:加入している場合は補償が受けられます。
休職中の過ごし方
病気やけがによる休職の場合、まず心身をしっかりと休めることが最も重要です。無理をせず、身体的・精神的な回復を最優先にして過ごすようにしましょう。
また、休職中の状況や社員の健康状態を把握するために、会社によっては定期的に状況を報告しなければならない場合があります。今後の復職に向けての計画を尋ねられることもあるでしょう。
医師の診断を受けることも大切です。休職が病気や精神的な理由による場合は、定期的に通院を続け、医師のアドバイスを受けることが早期回復につながります。復職の際も、医師に復職可能かどうか判断を仰ぐ必要があるため、治療・通院は継続しましょう。
休職ではなく転職を選ぶなら

転職した方が今後のキャリアや生活にとってプラスになると感じた場合、休職ではなく転職を選ぶ人もいるでしょう。どのようなケースで転職を検討するとよいのか解説します。
休職より退職の方が望ましいケース
復帰後に職場の状況が変わらないと感じる場合、転職の方が前向きな選択となるかもしれません。
休職後に職場の体制が改善される見込みがない場合や、業務の負担が解消されないと感じる場合、退職して新しい環境でキャリアを再スタートする方が、自分の成長や心身の回復につながるでしょう。
休職期間中に経済的な不安を感じる場合、思い切って転職をし、新しい職場で収入を得る方が安心感を持って生活できます。自分の状況を好転させる前向きな転職として捉えましょう。
退職時に利用できる制度
退職時には公的支援や制度を活用できます。例えば、失業保険は、退職後に収入がなくなる期間をサポートしてくれる制度です。一定の条件を満たすことで、失業手当が支給され、転職活動をしながら生活費の一部を補えます。
休職後に退職を決意することもあるでしょう。病気やけがで休職しているならば、転職活動を始める前に医師と相談しながら進めます。
特にメンタル面で不調がある場合は、焦らず無理なく転職活動を行いましょう。心身の回復を最優先にし、無理をしないように、計画的に新しい職を探すことが大切です。転職は大きな決断ですが、適切な制度を活用しつつ自分のペースで進めていきましょう。
自分にとって最善の道を選択しよう

会社や国の制度を活用すれば経済的不安が軽減され、心身の回復に専念する時間を持つことができます。休職する前に、いま一度就業規則を確認してみましょう。
また休職は、自分の状況やキャリアを見つめ直す期間でもあります。休職を続けることが負担になる、職場環境が改善される見込みがない、などと感じた場合は、転職を前向きに検討するのも1つの選択肢です。
気持ちを切り替え、新しい仕事にチャレンジしたくなったら、仕事・求人情報一括検索サイト「スタンバイ」を活用してみてください。前向きな選択で、より良い未来をつかみましょう。
スタンバイ|国内最大級の仕事・求人情報一括検索サイトなら
