ものづくりや建物が好きで、建築士になってみたいと思っている人は多いかもしれません。建築士に向いてる人の特徴や仕事のやりがい、苦労について解説します。資格の取得方法についても紹介するので、建築士を目指す人は参考にしましょう。
建築士に向いてる人の特徴

建築士はビルや住宅など、さまざまな建物の設計や工事を監理する職業です。建築士に向いてる人には、どのような特徴があるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
自分で何かを作ることが好き
純粋にものづくりが好きな人は、建築士に向いているでしょう。建物を設計し、施工から完成までを見届けるには、長い期間がかかります。完成するまでの間に、予想外のトラブルに見舞われる場合もあるかもしれません。
何かを作り上げることにやりがいを感じるタイプなら、行き詰まりを感じたときやつらくなったときにも、くじけることなく乗り越えていけるでしょう。
子どもの頃からプラモデルの作成やデザインなど、手を動かして何かを作るのが好きだった人は、建築士になってからもやりがいを持って仕事ができるはずです。
美的センスに自信がある
設計や建築法規などのスキルや知識に加えて、創造力や美的センスがある人も建築士に向いているでしょう。
建築士はクライアントの要望に基づき、建物の外装から内装まで、あらゆる部分の設計やデザインを決定します。建物全体の見た目はもちろん、室内の空間デザインや素材の色・材質といった細かい部分まで、トータルに考えられる創造性が必要です。
センスや創造力は後から磨くことも可能なので、自信がないからといってあきらめる必要はありません。優れた建築物を見たり美術館に通ったりして、勉強する意思があることが大切です。
継続力や責任感がある
建築士には、継続力や責任感も求められます。建築士になるためには、勉強して資格を取得しなければならず、何年もかかるのが普通です。継続力がなく、何事も途中であきらめてしまう性格の人は、建築士には不向きでしょう。
建築士になってからも、1つの建物を完成させるまでには長い時間がかかります。建築物の規模によっては、数年を要するケースも珍しくありません。
さまざまな人に指示を出して仕事を進めていく立場なので、途中で投げ出さない責任感がある人も建築士に向いてるでしょう。
理系の科目が得意
学生時代に理数系の科目が好きだった人も、建築士に向いてるでしょう。建築家は建物のデザインに目がいきがちですが、実は構造計算や、立地と建築限界などの割合計算といった過程が非常に重要です。耐震構造や地盤などに関する知識も不可欠です。
さらに近年は、建築業界でもプログラミングスキルが求められるようになってきています。物事をロジカルに処理できる理系の素養があると、建築士としての価値を高めやすいでしょう。
建築士のやりがい

建築士の仕事には、やりがいを感じられる場面が多々あります。これから目指したいと思っている人は、イメージしやすくするためにも、どんなやりがいがあるのかを知っておきましょう。
ものづくりの面白さを感じられる
ゼロから建物を作り上げていくこと自体がやりがいだと感じている建築士は多いでしょう。クライアントの要望に添って、自分なりのセンスやアイデアを形にしていく楽しさは、ものづくりを職業とする建築士だけが味わえる醍醐味です。
設計から施工、完成まで数年かかる場合も珍しくないため、実際に竣工したときの達成感は大きなものでしょう。ものづくりの面白さは、建築士にとって大きなやりがいといえます。
仕事で人を喜ばせられる
クライアントの理想をかなえる建物を作って感謝の言葉を伝えられることは、建築士にとってのやりがいといえるでしょう。
建築士が作るのは単なる建造物ではなく、誰かが生活する場や人々が集まる空間です。建築士は建物を作ると同時に、人々の生活や地域に豊かさを与えるといっても過言ではありません。
完成した建物に満足してもらえることは、建築士にとって大きな喜びです。自分の手がけた建物がクライアントを笑顔にし、人々から愛されているところを見れば、大きなやりがいと達成感を味わえるはずです。
建築士の大変さ

建築士は、ものづくりの楽しさや建物が完成したときの達成感を味わえる仕事です。しかし同時に、大変なことも多々あります。建築士の仕事によくある苦労を紹介します。
時間に追われがち
建築士の仕事は、基本的にクライアントが指定する納期までに建物を完成させなければなりません。案件によっては非常にタイトなスケジュールの場合もあり、納期を守るため時間に追われがちです。
設計段階ではクライアントとの打ち合わせも多く、定時に仕事が終わることは少ないと思った方がよいでしょう。
納期に終われて残業が多い上、新しいアイデアや知識をインプットするための勉強も欠かせません。建築士には長時間労働に耐えられる肉体的なタフさに加えて、常に付いて回る納期のプレッシャーに負けない精神力も必要です。
クライアントの要望と安全性の両立が難しい
建築士をしていると、クライアントの要望と安全性の両立に悩む場合もあります。建築士は基本的に、クライアントの理想や要望を建築という形で実現するのが仕事です。しかし同時に、その建物が安全で法律をクリアしている必要もあります。
クライアントの要望をかなえようとすると、安全基準に問題が生じるケースは少なくありません。そのような場合、クライアントに分かりやすく説明して妥協してもらうのも建築士の仕事です。
とはいえ、中には何度説明しても納得してくれないクライアントもいるため、コミュニケーションの難しさに苦労することもあるでしょう。
「資格別」建築士の目指し方もチェック
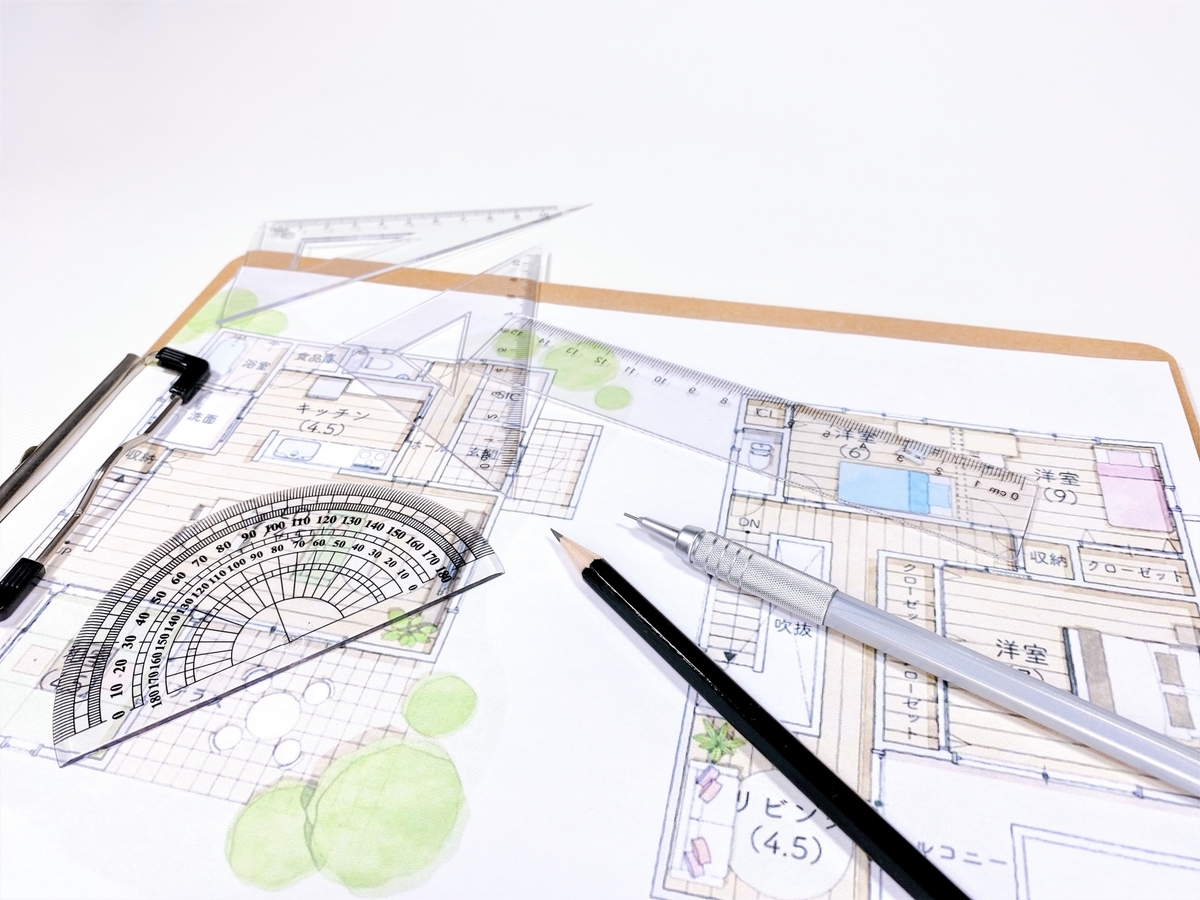
建築士には、設計・監理できる建物の違いによって「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類があります。それぞれの資格取得の方法と、設計や工事監理できる建物について解説します。
設計できる建物が多い「一級建築士」
一級建築士は、建築士の中で最も難易度が高い資格です。一級建築士になると、一般的な住宅からスタジアムのように大きな建物まで、幅広い種類の設計・工事監理ができます。
一級建築士の資格試験を受験するには、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 大学・短期大学・高等専門学校で指定科目を修了して卒業している
- 二級建築士として免許登録している
- 国土交通大臣が上記と同等以上の知識および技能を有すると認めている(建築設備士を含む)
一級建築士として免許登録するには、一定期間の実務経験が必要です。
- 大学卒業:2年以上
- 短期大学(3年):3年以上
- 短期大学(2年)・高等専門学校:4年以上
- 二級建築士:二級建築士として4年以上
- 国土交通大臣が同等と認める者:所定の年数以上
- 建築設備士:建築設備士として4年以上
実務経験の期間は学歴によって異なることに注意して、キャリアプランを描きましょう。働いていた時期は合格の前後を問いません。
住宅メインなら「二級建築士」
二級建築士は、主に木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造などの住宅の設計や工事監理が可能になる資格です。二級建築士の資格を取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 大学・短期大学・高等専門学校・高等学校で指定科目を修了して卒業している
- 建築の実務経験を7年以上積んでいる
- 都道府県知事が例外として認めている
二級建築士として免許登録するには、学歴別に以下の実務経験が必要です。
- 大学・短期大学・高等専門学校:不要
- 高等学校・中等教育学校:2年以上
- 都道府県知事が同等と認める者:所定の年数以上
一級建築士と違って実務経験のみでも受験できるのが、二級建築士の特徴です。実務経験だけで受験する場合は、登録の実務要件も7年となります。
歴史ある建物に携わる機会も「木造建築士」
木造建築士は都道府県知事が与える免許で、主に木造住宅の設計・工事監理が可能な資格です。一級建築士や二級建築士と違って鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物は設計できないものの、神社仏閣のような歴史的建築物に携われる可能性があります。
木造の建築物に特化しているため、木材についての専門知識や木造建築物の構造について深く理解できるのもメリットです。木造建築士試験の受験要件は以下の通りです。
- 大学・短期大学・高等専門学校・高等学校で指定科目を修了して卒業している
- 建築の実務経験を7年以上積んでいる
- 都道府県知事が例外として認めている
木造建築士として免許登録するには、学歴別に以下の実務経験が必要です。
- 大学・短期大学・高等専門学校:不要
- 高等学校・中等教育学校:2年以上
- 建築の実務経歴のみ:7年以上
- 都道府県知事が同等と認める者:所定の年数以上
二級建築士と同じく、実務要件のみで受験・免許登録ができます。木造建築に特化した建築士を目指したい人は、目指してみるとよいでしょう。
適性を知って目指す道を自分で決めよう

建築士は、ものづくりが好きな人や理系科目が得意な人に向いてます。建物をゼロから作り上げていくため、大きなやりがいを実感できる仕事です。
建築士の資格を取得して免許登録するには、建築の実務経験が必須になります。他業種から建築士を目指すなら、まず建築業界で実務経験を積みながら資格取得を目指しましょう。
建築業界への転職には、求人数が豊富な求人サイトを活用するのがおすすめです。豊富な求人数を誇るスタンバイで、自分に合った建築の仕事を探してみましょう。
