年休消化(年次有給休暇の消化)は、転職や退職の際、残っている有給休暇を取ることを指すケースが多いが、特に必要ないと考える人もいます。しかし一定の条件に該当すれば、年休消化は義務となるので注意しましょう。有給休暇の基本知識や取得条件などを解説します。
年休消化(年次有給休暇の消化)とは?

年休消化(年次有給休暇の消化)とは、転職や定年退職をする際に、その時点で残っている有給休暇を消化することを指すことが多いです。まずは、年休の基本的な知識や取得条件を知っておきましょう。
年休の基礎知識
年休(年次有給休暇)は、所定の休日とは別に、賃金が支払われることを前提として労働者が取得できる休日です。
労働基準法第39条で定められている労働者の権利であり、正社員や契約社員はもちろん、アルバイトやパートの立場でも、一定の条件を満たす場合には有給休暇を取得できます。
転職や定年を機に退職する場合、仕事の引き継ぎをはじめ、退職に支障がないタイミングで有給休暇を取得することが大事です。
年休の取得条件
年休を取得できる条件は、入社から6カ月間、継続的に勤務していることと、期間内の全労働日のうち、8割以上出勤していることです。
この条件を満たす限り、どういった労働形態であっても年休が取得できます。裏返せば、入社から半年以上経過するまでは、原則として有給休暇を取ることはできません。
従来、労働者が年休を取得しない場合でも、特に問題にはなりませんでした。しかし後述するように、現在は年休の取得が義務化されているため、企業は条件に該当する従業員に対して、年休を必ず取得させる必要があります。
年休消化は義務?
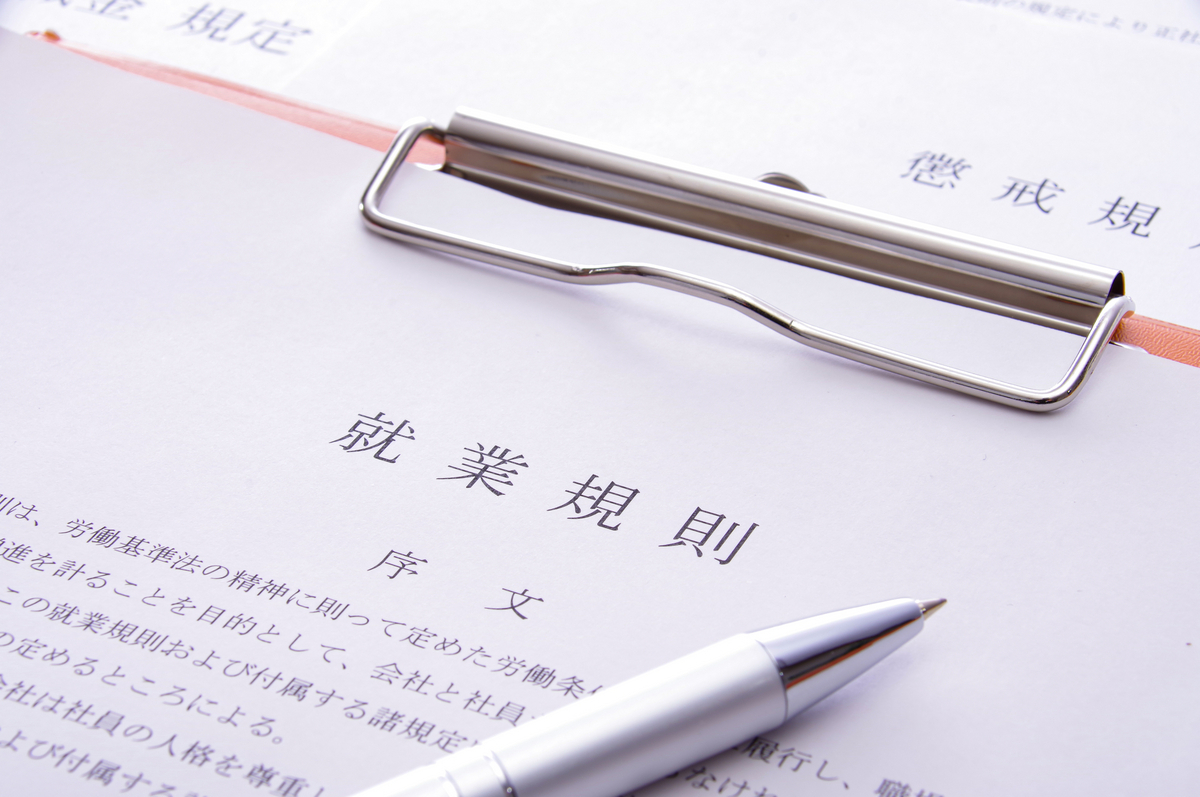
年休の取得条件を満たしている場合でも、特に休みを取りたいと思わない人も少なくありません。しかし2019年の法改正により、年休の取得が義務化されました。
年5日の年休消化が義務化
2019年4月の労働基準法改正によって、年間10日以上の有給休暇を取得できる従業員に対して、年5日間の年休を取得させることが企業の義務になりました。
期限は付与日(基準日)から1年以内で、当該従業員の意見を聴取した上で、取得時季を指定する必要があります。
ただし、すでに5日以上の年休を請求・取得している従業員に対しては、企業側がさらに年休の取得時季を指定することはできません。従業員の5日以上の年休の消化は、全ての企業の義務とされています。
参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省
年休消化が義務化された背景
年休消化が法律により義務化された背景としては、本来は労働者の権利である年休を、周囲への配慮から取得しない労働者が多い点があります。
また、政府が主導している働き方改革推進の一環として、国民に対して積極的に年休を取るよう促すようになりました。
日本の場合、特に上司や同僚への気兼ねから、積極的に休みを取らない人が少なくありません。適度にリフレッシュする期間を持たせるために、年休の権利はしっかりと行使することが大事です。
利用できる年休の日数は?
年休の取得日数は、次のように勤続年数が長くなるにつれて増えていきます。
- 半年:10日
- 1年半:11日
- 2年半:12日
- 3年半:14日
- 4年半:16日
- 5年半:18日
- 6年半以上:20日
ただし、週の所定労働日数が4日以下、かつ所定労働時間が30時間未満の場合、勤続勤務年数が増えるにしたがって取得できる年休の日数は増えるものの、通常の労働者の付与日数とは異なります。
詳しくは、労働基準法第39条あるいは厚生労働省の資料を確認しましょう。
参考:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
年休消化のパターン
転職や定年などで退職する場合、最終出勤日以降に年休をまとめて取る方法と、年休を消化してから退職するパターンがあります。
最終出勤日を終えてから有給休暇に入る場合、そのまま退職することになるので、事前に仕事の引き継ぎや関係者へのあいさつなどを済ませておきましょう。
一方、年休を消化してから退職する場合、退職日を迎えるまでは引き継ぎの確認や、後任へのフォローが可能です。
どちらのパターンを選ぶにせよ、退職後に残された社員が業務を進めやすいように配慮しましょう。
年休消化で守るべきルール

年休の消化は従業員側にとっては権利ですが、取得に際しては守るべきルールがあります。特に退職時に年休を取る場合は、できるだけ早く、上司や職場の管理者への相談・報告が大事です。
なるべく早く管理者に相談・報告する
退職を決意したら、なるべく早く上司や部門・部署の管理者に報告し、年休の取得について相談しましょう。
会社側は社員に年休を消化させなければならないので、拒否はできません。しかし、急に休暇取得を申請すると、周囲が対応できない可能性があります。特に部下がいる立場の人は、休暇中に問題が起こらないように、しっかりと指示を出しておきましょう。
引き継ぎを確実に終わらせる
基本的なマナーとして、退職するならば年休の取得にかかわらず、確実に業務の引き継ぎをしなければいけません。年休を取るタイミングによっては引き継ぎが難しくなるので、後任の事情も考えた上で、休暇を取得する日程を調整する必要があるでしょう。
引き継ぎが終わらないまま年休に入ってしまい、後任が仕事の内容を把握していない事態が発生する職場は、決して少なくありません。引き継ぎが十分にされないと、年休中や退職後に、業務に関する相談や質問を受ける可能性もあります。
退職するまでには、確実に引き継ぎを終わらせるようにしましょう。
年休消化が許されない場合は?

上述の通り、2019年から年休の消化は義務化されており、条件に該当する従業員に対して、企業は年休を取得させなければいけません。しかし、年休の権利を有しているにもかかわらず、会社側が休暇取得を認めてくれない場合はどうすればよいのでしょうか?
年休消化を認めないと企業に罰則が
社員に年休消化を認めない企業は、罰則の対象となります。従業員側は気にせず、年休を申請して問題はありません。
会社側が認めない場合でも、労働者の権利として取得を求めることが可能です。年休を取得できる従業員が5日以上の有給休暇を取得できない場合、会社に対して30万円以下の罰金が科されるケースがあるため、最終的には認められるでしょう。
ただし、急な申請によって業務が混乱することが原因で、取得を拒否される可能性はあります。早めに休暇を申請したり、引き継ぎを終わらせたりして、周囲に迷惑をかけないようにしておくことが大事です。
年休消化を拒否された場合は労基署に相談
上司や部門管理者から年休消化を拒否された場合、まずは社内のコンプライアンス部門や人事部門などに相談しましょう。急な年休消化で現場が対応できない場合など以外は、会社側は労働基準法違反となるため、休暇の取得自体は認めなければいけません。
それでも年休取得が認められないならば、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署は無料で相談が可能で、労働基準法違反が認められた場合、会社側に是正勧告をしてもらえます。
ほかにも、労働に関するさまざまな相談ができるので、困ったことがあれば利用してみるとよいでしょう。
年休消化は計画的に実行しよう

年休消化は労働者の権利であるため、条件に該当しているならば、問題なく休暇の取得が可能です。
ただし、年休が残った状況で転職や定年退職する場合、早めに休暇の取得について上司や管理者に相談しましょう。休暇を取得しようとする時期によっては、仕事の引き継ぎが難しくなる可能性があります。
事前にしっかりと計画を立てた上で、確実に仕事の引き継ぎを終わらせるようにしましょう。引き継ぎに差し支えないように、年休のタイミングを調整することも大事です。
