「仕事を辞めたいのに辞めさせてもらえない」そんな悩みを抱えてはいませんか?スムーズな退職をかなえるヒントとして、退職を認めないことの違法性や法律上の退職の条件について確認していきましょう。状況別の具体的な対処法も紹介します。
この記事のポイント
- 労働者には辞める権利がある
- 職業選択の自由が憲法で保障された日本では、誰もが自分で選んだ職業に就く権利と同時に退職の自由も保障されており、会社側に退職を制限する権利はありません。
- 雇用期間の有無で退職の条件が変わる
- 雇用期間に定めのない場合は、2週間前までに申し出れば退職は可能です。雇用期間に定めがある場合は、やむを得ない事情を除き、契約期間満了まで退職できません。ただし、契約期間が1年を超える契約の場合は、契約から1年を経過した時点でいつでも退職が可能です。
- 退職できないときの対処法
- 辞めると決意したら意思を固く持ち、本気度を伝えるためにも退職届を用意するのがおすすめです。受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便で会社に送ることも検討しましょう。
仕事を辞めさせてくれないのは違法?
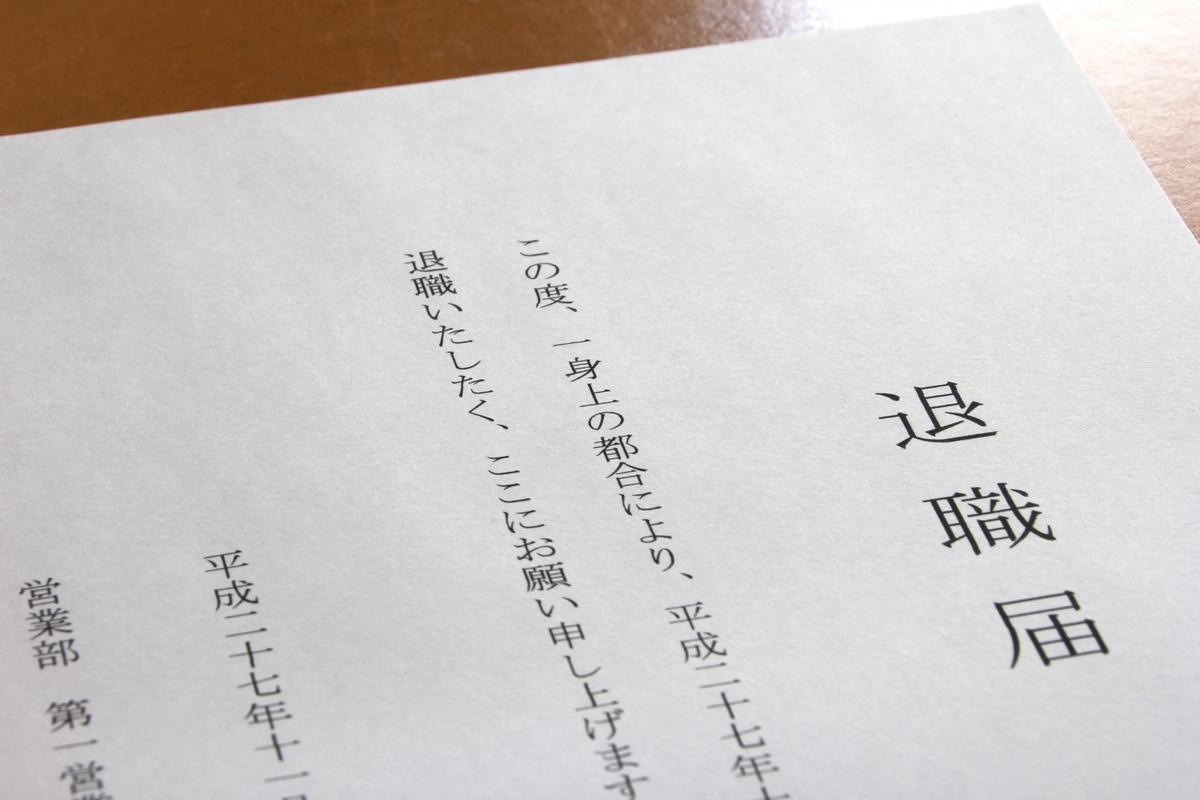
仕事を辞めたいと伝えているにもかかわらず辞めさせてもらえないとき、「これは違法なのでは?」と考える人は少なくありません。法律上の違法性について詳しく見ていきましょう。
労働者には辞める権利がある
職業選択の自由が憲法で保障された日本では、誰もが自分で選んだ職業に就く権利を持っています。これは同時に退職の自由も保障するもので、会社側に退職を制限する権利はありません。
正社員など、雇用期間の定めがない労働者の場合、退職を申し出てから2週間が経過した時点で雇用関係は終了します。この際、会社側の承諾は不要です(民法627条1項)。
つまり、労働者には辞める権利があり、会社側がそれを受け入れないのは違法行為にあたります。正式に退職の意思を伝えているにもかかわらず退職できずにいるのであれば、すでに権利が侵害された違法状態にあると考えられるでしょう。
違法となる例
実際に違法と判断されるのはどのようなケースなのでしょうか。いくつかの具体例を見てみましょう。
- 「今退職するのなら損害賠償を請求する」と言われた
- 過去のミスなどを持ち出して「辞めるのならば懲戒解雇にする」と言われた
- 「今月の給料(退職金)は払わない」と言われた
- 「離職票を出さない」と言われた
- 有給休暇の消化を認めてもらえない
このような脅しや嫌がらせとも取れる行為は違法です。上記のようなケースにあてはまる場合は、会社側が違法行為を行っていることを前提に堂々と対応していきましょう。
お願いの段階は違法とは言い切れない
快く退職を受け入れてもらえなかったからといって、会社側の対応のすべてが違法とは限りません。
例えば、退職の申し出が繁忙期にあたる時期の場合、「繁忙期が終わるまで辞めるのは待ってほしい」と引き留められるのはよくあるパターンです。特に人手が足りない職場の場合、「代わりの人が見つかるまで待ってほしい」とお願いされることも考えられるでしょう。
このように、退職を渋られたり条件を提示されたりしたとしても、それがあくまでもお願いの段階である場合には違法とは言い切れません。もちろん、お願いであれ強要であれ、従う義務はないこともあわせて心に留めておきましょう。
法律における退職の条件
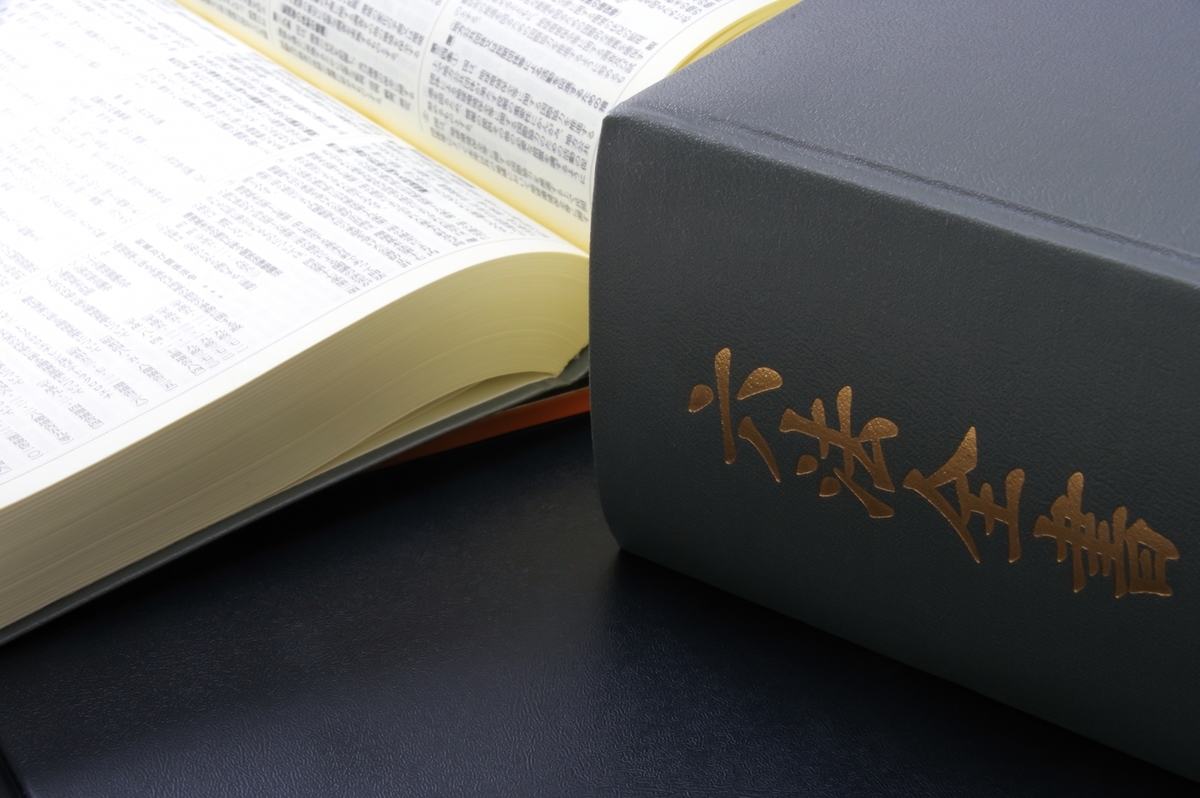
法律上、2週間前までに退職の申し出をすれば退職は可能です(民法627条1項)。
ただしこの条件は、雇用期間の定めがない労働者が対象であり、雇用期間の定めがある労働者の場合はこの限りではありません。雇用期間が定められている場合・定められていない場合、それぞれの詳しい退職の条件を確認していきましょう。
雇用期間に定めがない場合
雇用期間に定めのない労働者(一般的には正社員)が退職をする場合、2週間前までにその旨を申し出れば退職は可能です。
たとえ会社側が退職を認めなかったとしても、2週間後に雇用関係は終了とみなされるため、無理に勤務を続ける必要はありません。
ただし、会社の就業規則に「退職は1カ月前までに申告する」など退職の申し出に関わる規定がある場合には注意が必要です。定められた期間があまりにも長すぎるケースを除き、基本的には就業規則が適用されるでしょう。
なお雇用期間に定めがない場合でも、6カ月以上の期間で報酬が定められている場合には、3カ月以上前までの申告が必要です(民法627条3項)。
雇用期間に定めがある場合
契約社員のように雇用期間に定めがある労働者の場合、原則として契約期間が満了するまでは退職できません。契約が有効である以上、定められた期間は勤務を続ける必要があるでしょう。
ただし、病気で勤務ができなくなったり、雇用条件が契約内容と異なったりとやむを得ない事情がある場合には直ちに契約を解除できます(民法第628条)。この事情が会社側・労働者どちらかの一方的な過失の場合には、損害賠償義務が発生する可能性があることも頭に入れておきましょう。
また、契約期間が1年を超える契約の場合には、契約から1年を経過した時点でいつでも退職が可能です(労働基準法第137条)。
仮に、雇用形態が正社員ではなくアルバイトやパートだとしても、これらの条件に違いはありません。必要に応じて退職の手続きを進めましょう。
会社側が退職を認めない理由

「仕事を辞めたいのに会社側が認めてくれない」というケースが起こる理由とは、どのようなものがあるのでしょうか。考えられる主な理由を紹介します。
繁忙期で人手が足りない状態である
会社側が退職を認めない理由としてまず挙げられるのが、繁忙期など人手が足りない状態にあるというものです。
会社によっては、繁忙期とそれ以外の時期との忙しさに大きな差があります。猫の手も借りたいような時期に退職の申し出をされても、快く受け入れられないのも無理はありません。
これは慢性的な人手不足の会社の場合も同様です。1人抜ければたちまち業務が立ちゆかなくなるような状況では、退職をすんなりとは受け入れられないでしょう。
中には、新たな人材を採用するコストを惜しんで退職を認めないケースもあります。いずれにせよ、基本的には会社側が対応・改善するべき問題といえるでしょう。
会社の離職率を上げたくない
会社によっては、離職率が上がることを恐れて退職を渋るケースもあります。
離職率は、会社のイメージを大きく左右するものです。退職者が多い会社は、それだけで「環境が悪いのだろう」「ブラック企業なのかもしれない」といったネガティブなイメージを持たれる可能性があるでしょう。
イメージを重視する会社や、人手不足の会社にとっては大きな痛手となりかねないため、役職のある社員に対し部下の離職率を引き下げるよう通達が出されているケースも少なくありません。
離職率を上げたくないというのが会社全体の意向である場合、退職の申し出は一層渋られることになるでしょう。
上司が自身の評価を気にしているケースも
上司個人の思惑によって退職を認めてもらえないケースも存在します。
社風にもよりますが、部下の退職=上司の力不足、もしくは上司個人に何らかの問題があると評価されてしまうことは案外多いものです。同じ上司の部下が立て続けに退職した場合、管理能力不足を問われ、上司自身の昇進やボーナス査定に影響が及ぶこともあるでしょう。
直属の上司が保身に走りやすいタイプである場合、こうした個人的な事情で退職を認めてもらえない可能性も考えられます。心当たりがあるなら、上司以外の人の協力を仰ぐ必要があるでしょう。
辞められないときはどうすればいい?

「仕事を辞めたいのに辞められない」そんなときは、いったいどうすればよいのでしょうか?段階に沿って、取るべき行動を紹介します。
退職の意思を直属の上司にはっきりと伝える
退職を認めてもらえない場合、その原因としてしばしば見られるのが、本気度が伝わっていないというものです。
このケースでは、退職の意思はあくまでも愚痴や相談として受け取られていると考えられます。「辞めようと思っています」「もう続けていくのは難しいです」といった曖昧な伝え方をした場合に多く見られるパターンといえるでしょう。
この場合、本気度を伝えるためにも退職届を用意するのがおすすめです。退職の意思が固いことを明確にすれば、意外とあっさり退職を認められるかもしれません。
直属の上司がダメならさらに上の上司・人事部へ
場合によっては、直属の上司に退職届を提出したにもかかわらず、受け取ってもらえないこともあるでしょう。
そんなときは、直属の上司のさらに上の上司へと退職届を提出するのがおすすめです。通常、上の役職であればあるほどに退職にまつわる法律も熟知しています。退職届を提出すれば、法律に従って手続きを進めてくれるでしょう。
万が一、上の上司も退職を認めない可能性があるなら、直接人事部に提出するのも1つの方法です。いずれのケースでも、退職の許可を求める「退職願」ではなく退職を通告する「退職届」にすることで、固い意志をより強力にアピールできるでしょう。
労働基準監督署に相談するのも手
社内であらゆる手を尽くしたけれど、退職を認めてもらえないときは、労働基準監督署への相談も選択肢の1つです。
労働基準監督署は、通称「労基」と呼ばれる厚生労働省管轄の機関です。労働条件や安全衛生の改善や指導・労災保険の給付などを担う、いわば労働者のための機関といえるでしょう。
退職が認められない場合、労働基準監督署に相談することでアドバイスを受けることができます。残念ながら、直接会社への訪問や指導・勧告を行ってくれるケースはまれですが、状況を打開する大きなヒントを得られるかもしれません。
【状況別】退職できないときの対処法

ひと口に「退職できない」といっても、置かれた状況は人によってさまざまです。考えられる状況ごとに、それぞれ適した対処法を確認していきましょう。
退職届を受け取ってもらえない
退職の意思を会社に伝えさえすれば、基本的には2週間後に退職が可能です。しかし、肝心の退職届を受け取ってもらえなければ、そもそも「退職の意思を伝えた」と公に認めてもらうことができません。
そんな事態を防ぐためにも、退職届は内容証明郵便で会社に送りましょう。内容証明郵便は「どんな内容の文書をいつ誰が誰に送ったのか」を郵便局が証明してくれるサービスです。
細かいルールがありますが、特定の文書を確実に届けたと証明する上で、非常に便利なサービスといえます。
内容証明郵便で退職届を送れば、会社側も「受け取っていない」との言い逃れはできません。退職の意思は公に証明され、スムーズに退職できるでしょう。
会社が指定した退職日までが長い
会社の就業規則に「退職日の○日前までに申し出なければならない」といった規定がある場合、基本的にはその規定に従う必要があります。ただし、定められた期間が常識的に考えてあまりにも長い場合には、必ずしも従う必要はありません。
この民法と就業規則のどちらが優先されるかについては、過去に「民法第六二七条の予告期間は、使用者※のためにはこれを延長できないものと解するのが相当である。」との判例も出ています。
就業規則が民法に優先するかどうかは、その期間の合理性について客観的に認められるかどうかによるといえるでしょう。
※雇用主・会社
参考:労働基準判例検索-全情報
損害賠償・懲戒解雇などの脅しを受けている
中には、もっともな理由をつけられた上で「今辞めるなら損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」との脅しを受け、退職できずにいる人もいるかもしれません。
しかし、そもそも損害賠償は、会社に与えた損害に対する賠償です。例えば「長く勤務することを前提に会社の費用で高額なセミナーに参加した」というような特別な事情がない限り、請求されるものではありません。
懲戒解雇についても同様で、犯罪行為や明らかな就業規則違反があって初めて申し渡される類いのものです。
実際に損害賠償請求をされたり懲戒解雇処分を受けたりすることはまずないため、取り合わずに退職の準備を進めましょう。万が一、実際に不当な処分を受けるようなことがあった場合には、労働基準監督署や弁護士への相談がおすすめです。
有給休暇・残りの給与を認めない
退職までの期間に有給休暇を認めないというケースも、比較的多く見られるでしょう。
しかし労働基準法は「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と定めています(労働基準法第39条5項)。そのタイミングで有給休暇を与えることにより、業務が極端に滞るなど特別な事情がある場合を除き、拒否することはできません。
また、「辞めるなら給与は払わない」と脅されたという事例もありますが、このケースも真に受ける必要はありません。同じく労働基準法において「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められているためです(労働基準法24条1項)。
残りの有給休暇・給与ともに、認めないと言われても取り合わず退職準備を進めていきましょう。
仕事を辞めさせてくれないことに関するQ&A

仕事を辞めさせてもらえない状況に陥ると「こうしたらどうだろう?」「この方法なら辞められそうだけれど、許されるだろうか…」と、さまざまな疑問が脳裏に浮かぶものです。中でも特に多く見られる疑問点とその答えを紹介します。
無理やり辞めてしまうのはアリ?
退職の希望を伝えても受け入れてもらえない場合、「いっそのこと無理やり辞めてしまおうか」と考える人もいるのではないでしょうか。
しかし、この方法はあまりおすすめできません。というのも、無理やり辞める=無断欠勤扱いとなる可能性が高いからです。
無断欠勤となれば、当然ながら心配した同僚や上司から絶えず連絡がきます。場合によっては自宅を訪問されたり、家族に連絡がいったりということにもなりかねません。
また、就業規則に「○○日以上の無断欠勤は懲戒解雇とする」といった規定がある場合、懲戒解雇扱いとなり今後の就職に悪影響を及ぼす可能性も十分に考えられます。
会社を辞めるにあたっては、どんなに面倒だとしても正攻法で手続きを進める必要があるのです。
退職をメールで伝えても大丈夫?
退職の意思の伝え方に決まったルールはありません。メールを使った退職の申し出も法的に有効と考えられます。
「直接退職の意思を伝えても慰留されてしまう」「恫喝されて怖い」といった場合でも、メールであれば安心して自分の意思を伝えられます。また、できるだけ早いタイミングで退職する必要があるときにも有効な手段となるでしょう。
なおこの場合でも、直属の上司が退職の意思を認めてくれない場合には、さらにその上の上司や人事部宛にメールを送付するのがおすすめです。確実に退職の意思を会社に伝えることを第一に考えて行動を起こしましょう。
辞めると決意したら意思を固く持とう
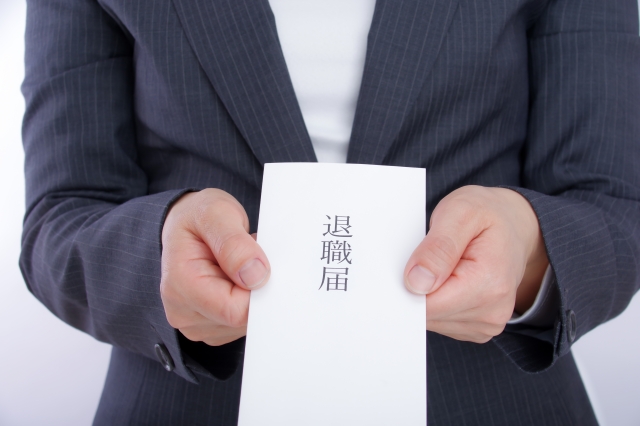
会社を辞めたいにもかかわらず辞めさせてもらえないときは、退職の意思をはっきりと伝える・直属の上司に聞き入れてもらえないときはさらに上の上司や人事部に伝えるといった方法が有効です。
それでもなおうまくいかないときは、労働基準監督署への相談も検討する必要があるでしょう。
なお大前提として、退職の自由は法律で保障されています。特別な理由がないにもかかわらず退職を認めない行為はそもそも違法であることを念頭に、怯むことなく必要な手段を講じていきましょう。

大学卒業後、銀行勤務を経て社会保険労務士資格を取得し独立開業。上場企業をはじめ数多くの企業の人事労務管理の相談指導、給与計算業務等に携わる。また年金問題についての執筆、講演も多数。
All Aboutプロフィールページ
