退職するときに、消化しきれていない有休が残っていることはよくあります。上司や同僚に迷惑をかけず、円満に退社するためには、計画的に有休を消化する必要があります。有休の基本的な仕組みや、有休消化の注意点について解説します。
有休消化の義務と権利

従業員と会社にとっての、有給消化の義務と権利について解説します。有給は、ただ与えられるだけではありません。きちんと消化できるよう、労働基準法でも定められていることを、理解しておきましょう。
有休消化とはどういうこと?
一般的に、有休消化とは、有給休暇を利用することを指します。有給休暇は、有休・年次休暇・年休と呼称される場合もありますが、どれも内容は同じです。
有休を保持している労働者なら、自分の好きなタイミングで有休を消化できます。
退職するときに、残っている有休をまとめて消化するケースも多くみられ、これを有休消化と表すこともあります。
この場合、最終出勤日に合わせて消化するか、退職日に合わせて消化するかを自分で選べます。
会社には有休消化させる義務がある
労働基準法により、年間10日以上の有休が付与される従業員には、年5日有休を消化させることが、会社に義務付けられています。
従業員が指定された有休を消化できなかった場合、会社に罰金が科される、罰則付きの規定です。
従業員の有休消化を促進するために、会社は従業員に対して、有休消化の時季を指定できます。これを「時季指定」といいます。
しかし、本来有休は、従業員が好きなタイミングで取るべきものです。会社が時季指定をする場合、従業員の希望にできるだけ添う必要があります。
参考:労働基準法 第四章 第三十九条 (年次有給休暇)|e-Gov法令検索
有休消化は労働者の義務
有休は労働者に与えられた義務なので、従業員が取得したいと申請すれば、基本的に会社は断れません。従業員が有休の日にちを指定して、申請する権利を「時季指定権」といいます。
しかし、従業員が有休を消化することで、会社の業務が回らなくなったり、正常な運営ができなくなったりするケースもあるでしょう。そのため、会社は有休消化の時季を変更する権利があり、これを「時季変更権」といいます。
通常の有休消化の場合は、時季指定同様、時季変更も従業員の意思に添う必要があります。しかし、退職時の有休消化は、原則として時季変更できません。
時季変更権は、有休消化の時季をずらす権利です。しかし、退職する従業員は、時季をずらせないので、会社は繁忙期でも時季変更権を行使できず、従業員の希望通りに、有休消化を承認することになります。
退職時の有休消化は主に2パターン
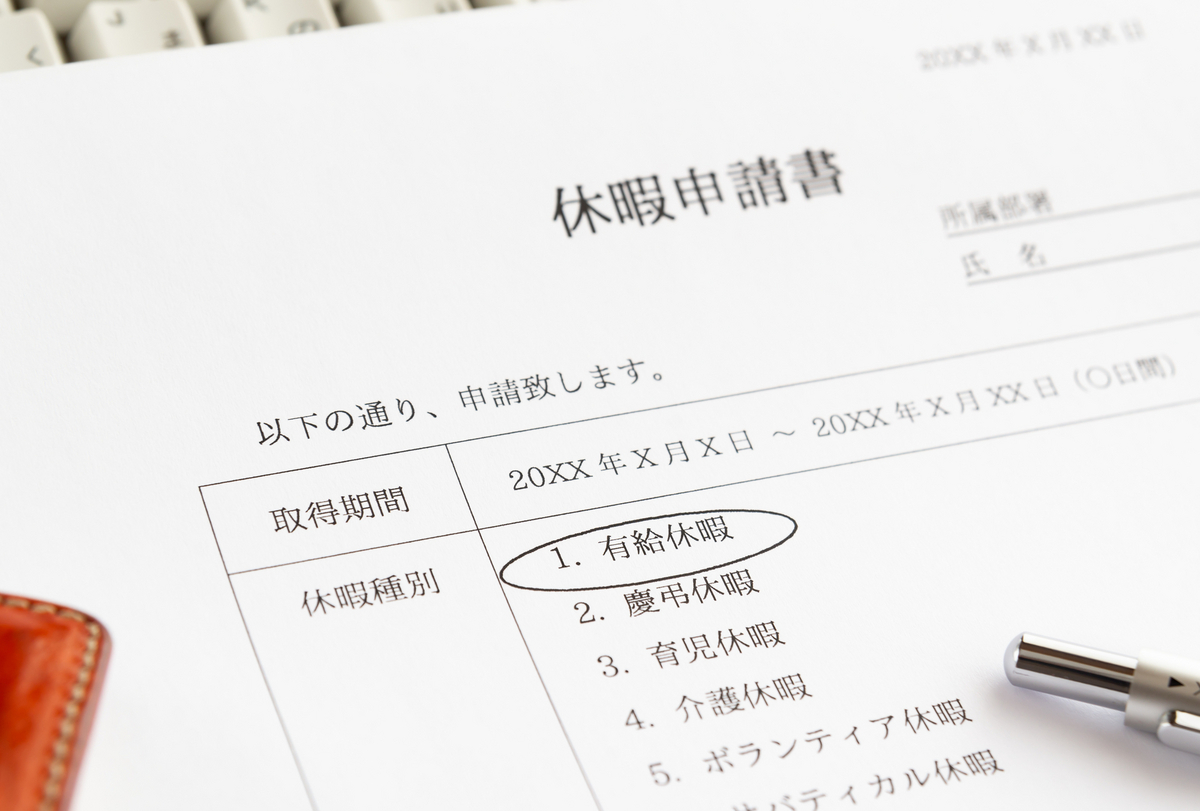
退職時にたまった有休をまとめて消化する場合の方法は、2パターンあります。どちらも一長一短なので、自分の希望や会社の引き継ぎなどと併せて考え、有休を取得しましょう。
有休を最終出勤前に消化する
最終出勤日の前に有休を消化するパターンは、有休を消化した後も退職日まで出勤することになります。
このケースの注意点は、有給消化前に業務の引き継ぎを済ませておくことです。有休消化後に出勤するからと、引き継ぎを残しておくと、最終出勤日に慌ただしくなってしまう可能性があります。
最終出勤日は、デスク周りの片付けや、あいさつ回りだけで済ませるよう、有給消化に入る前に、引き継ぎは全て済ませておきましょう。
また、最終出勤日に健康保険証や社員証などを返却できるので、後日郵送する手間もかかりません。
有休を最終出勤後に消化する
退職時のケースとして、最終出勤日後に有休消化し、有休終了日を退職日にする方法が一般的です。
最終出勤日と退職日が異なりますが、有休消化後に出社する必要がないので、気持ちを新たに、リフレッシュできる点がメリットといえます。
次の仕事が決まっている場合は、入社に向けた準備ができます。決まっていない場合は、腰を据えて就職活動に専念できるでしょう。
有休消化中も、退職日までは会社に籍があるので、健康保険証が使えます。しかし、退職日を過ぎたら、速やかに返却するのを忘れないようにしましょう。
有休日数の確認はしっかりと

退職時に有休消化をするにあたり、正確な残日数を把握しておく必要があります。日数を間違えると、有休が余ってしまったり、不足分を給料から差し引かれたりする場合もあります。
有休の計算方法
自分が取得できる有休の日数は、給与明細に記載してあったり、会社の人事部や経理課に問い合わせたりすれば確認できます。会社は従業員が有休を消化したときに「年次有給休暇管理簿」を作成・保存する義務があるので、日数を把握しているはずです。
有休の日数は自分でも確認できます。まず、有休が付与される条件として「雇用されてから6カ月経過」「決められた労働日数の8割以上を出勤している」の2つを満たす必要があります。
フルタイムで就労する正規労働者の有休は、6カ月経過すると10日与えられます。その後、「1年6カ月・11日」「2年6カ月・12日」「3年6カ月・14日」「4年6カ月・16日」「5年6カ月・18日」「6年6カ月以降は20日」と増えていきます。
有休は消化しないと、2年で消滅してしまう点に注意が必要です。繰り越せる日数は、就労年数によっても異なりますが、6年6カ月以上就労している人は、最大20日まで可能です。今年に付与された20日を合わせると、最大40日以上、保有できます。
参考:
年5日の確実な取得 年次有給休暇管理簿の作成|厚生労働省
労働基準法 第十二章 雑則 第百十五条 (時効)|e-Gov法令検索
退職時スムーズに有休消化する方法

退職するにあたって重要なのが、自分の業務を引き継ぐことです。会社や、上司・同僚などに迷惑をかけないように引き継いでおけば、スムーズに有休消化できます。
退職の意思は早めに伝える
退職の意思を伝えるタイミングは、民法によると2週間前に申し出ればいいことになっています。もちろん、就業規則に退職についての記載がある場合は、就業規則が優先されます。
例えば、1カ月前に申し出るようにと就業規則に記載があれば、1カ月前に申し出なければいけません。
しかし、退職時に有休残日数をまとめて消化したい場合は、業務の引き継ぎを確実に行うためにも、退職の意思は早めに上司に伝えておきましょう。
会社の業務や他の従業員との兼ね合いで、業務に支障が出ないような、退職日・最終出勤日を設定するのが賢明です。
参考:民法 第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | e-Gov法令検索
引き継ぎは計画的に行う
退職および、退職前の有休消化のために、自分の業務を引き継ぐ必要があります。
退職日までに引き継ぎが終わらないと、有休消化中や退職後に、業務について連絡がくる可能性があります。会社から退職日を延ばすように、相談されるケースもあるでしょう。
こういったトラブルを防ぐために、引き継ぎは計画的に、確実に行う必要があります。
そのため、退職日ではなく、最終出勤日から逆算して、引き継ぎなどのスケジュールを組みましょう。「誰にどの業務を任せるのか」「引き継ぎ方法」「資料やマニュアルの作成」「取引先や顧客のリストアップ」など、やるべきことは多くあります。
上司と退職日について相談し、後任を決めたら、後任者と引き継ぎスケジュールを決めましょう。
有休消化に関するトラブルと対処法
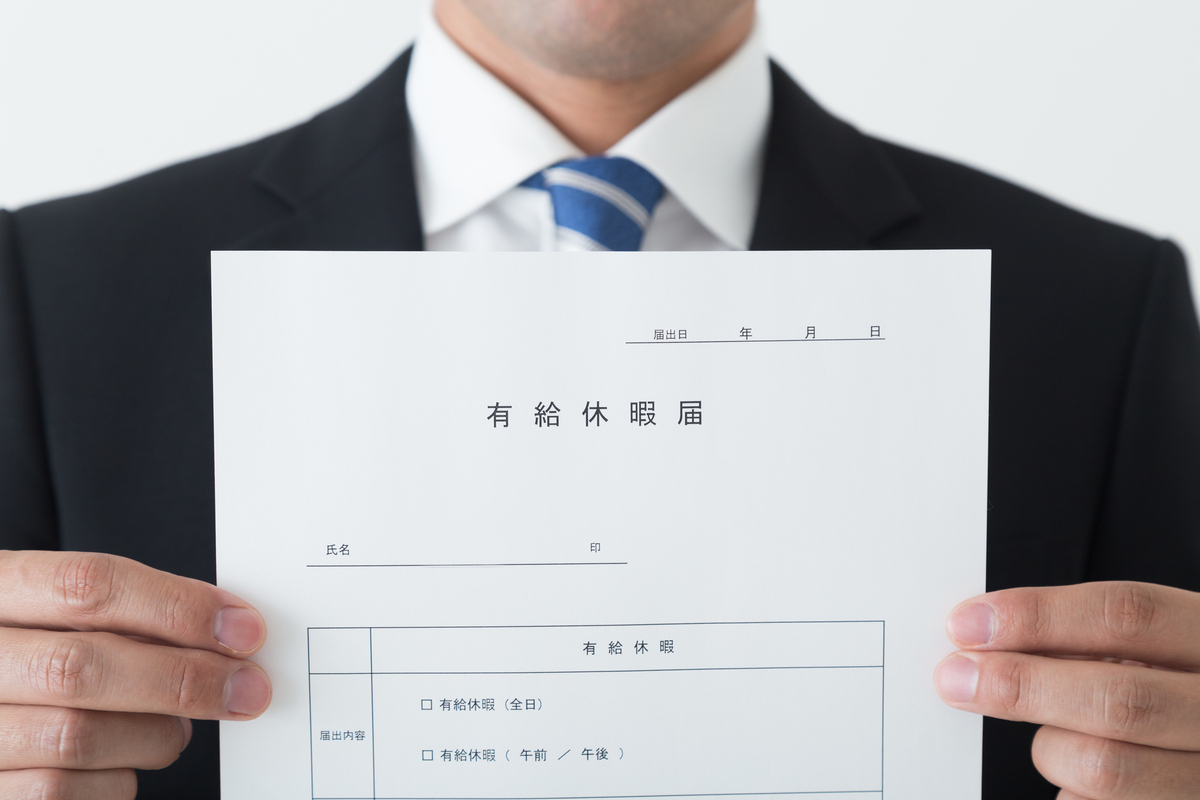
退職時の有休消化は、業務の状況や、上司の理解・会社の方針により、トラブルが発生するケースもあります。有休消化で起こりうるトラブルと、対処法について解説します。
有休が消化しきれない場合
就業年数にもよりますが、有休は最大40日保有できるので、退職の意思を1カ月前に伝えると、消化しきれない恐れがあります。また、引き継ぎに予定よりも時間がかかってしまい、出勤せざるを得ない状況になると、有休を消化しきれなくなる可能性も出てきます。
有休は従業員の権利ですが、退職日をもって雇用関係がなくなる点に注意しましょう。
有休を消化しきれない場合は、退職日を遅らせるように会社に相談する方法もあります。また、互いに合意に至れば、会社が指定する日に有休を消化し、全て使い切ってから退職することも可能です。
しかし、次の職場と入社日が決まっている場合は注意が必要です。
有休の買取りについて
さまざまな事情で退職日をずらせない場合、会社に有休を買取りしてもらうことは、できるのでしょうか?
原則的に有休の買取りは違法行為にあたるとされています。従業員の権利である有休を、お金を払って与えない会社が出てくることを防ぐためでもあります。そもそも、使い切れなかった有休を、会社が買取る義務はありません。
しかし、会社によっては、労働基準法を上回る日数の有休を付与しているケースもあります。その場合は、例外的に有休の買取りが認められているようです。
有休の買取りについては、会社によって対応が異なるので、就業規則を確認し、上司や会社に相談しましょう。
有休を消化させてもらえない場合
上司や会社に有休消化について相談しても、取り合ってもらえないケースもあります。
繁忙期や業務に支障が出るなどの理由で、有休消化を拒否されたら、いつなら取得できるのか尋ねてみましょう。それでも取得させてもらえない上に、有休の買取りもしてもらえず、退職日までに有休が消化できない場合は、しかるべきところに相談する必要があります。
コンプライアンス部門や、労務管理部門がある会社なら、上司に有休消化を拒否された場合は担当部署に相談しましょう。該当する部門がない会社の場合は、労働組合に報告するのも一案です。
会社に拒否された場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することになります。労働基準監督署への相談は無料です。会社が労働基準法に違反していると認められた場合、会社に指導・是正勧告が入る可能性があります。
弁護士に相談する場合は有料ですが、代理人としてトラブルを解決してくれるため、心理的な負担が軽減される点はメリットといえます。
有休消化中に転職先で就業したい場合
有休消化中の時間を利用して、転職先で就業するためには注意点がいくつかあります。
現在の職場と転職先の、双方の就業規則で二重就労を許可している場合のみ可能だということは覚えておきましょう。
禁止されているにもかかわらず就業してしまった場合、就業規則違反になります。現職場では退職金の減額または、支給されなくなる可能性があります。転職先では注意止まりでも、気まずい思いをするでしょう。入社取り消しや、使用期間内での解雇につながる恐れもあります。
転職先から就業の依頼があった場合は、現職場と転職先のどちらも二重就労を許可しているなら就業できます。その場合、雇用保険は二重では入れないので、現職場に「雇用保険資格喪失手続き」を依頼し、転職先で加入しましょう。
有休消化中の転職活動は可能
有休消化中の就業は、双方の会社の就業規則によりますが、転職活動は就業規則にかかわらず行えます。
また、有休消化中に転職活動を行うことを、上司や会社に報告する義務もありません。そもそも有休は、どのような理由でも取得できる従業員の義務であり、有休の理由を会社に申し出る必要がないものです。
現職場に出勤しているうちは、時間に余裕がないため、落ち着いて就職活動ができないので、有給消化中に転職活動を行うのが一般的です。
有休消化するときは念入りな準備が大切

退職時にまとめて有休を消化する場合、会社に迷惑をかけないように準備し、トラブルを防ぐことが大切です。
自分の有休が何日残っているのかを正確に把握して、業務の引き継ぎをしっかり行ってから、退職日を迎えられるようにしましょう。
引き継ぎが中途半端だと、有休消化中に連絡がきたり、退職日を遅らせなければならない事態に陥ったりしてしまいます。
世話になった上司や同僚に、負担をかけないように退職するためにも、念入りな準備を行ってから有休を消化しましょう。
