年間休日の最低ラインは、労働基準法により105日と決まっています。最低ラインを下回るとどうなるのか、休日がどのくらいあればよいのか、気になる人もいるでしょう。最低ラインの決め方や全国平均、業界別の日数など、年間休日の基礎知識を解説します。
この記事のポイント
- 年間休日の最低ライン
- 労働基準法による年間休日の最低ラインは105日です。下回ると罰則がありますが、違法ではないケースもあります。
- 年間休日の平均
- 年間休日の全国平均は110日以上です。業種や企業規模によっては、120日を超えます。
- 年間休日数と働き方の関係
- 年間休日が多いほど、ワークライフバランスが向上するといわれています。休日数に不満がある場合は会社と交渉したり、転職したりなどの方法があります。
年間休日に関する規定

年間休日の最低ラインは、労働基準法をもとに算出されます。違反した企業への罰則や休日出勤時の賃金など、年間休日に関する規定を見ていきましょう。
労働基準法では105日が最低ラインとなる
労働基準法第32条では、労働時間は週に40時間を超えてはならないとされています。週に5日かつ1日8時間働くと、ちょうど40時間です。
1年は約52週あるため、年間の労働時間の上限は「52×40=2,080時間」となります。これを1日の労働時間で割ると「2,080÷8=260」ですから、年間の労働日数は260日が上限と分かります。
つまり、1年の日数365日から260日を引いた105日が、年間休日の最低ラインとなるわけです。
なお、労働基準法第35条には、会社は従業員に「毎週少なくとも1日、または4週を通じて4日以上」の休日を与えなければならないとあります。これを法定休日といい、年間では52日となります。
しかし、労働時間の規定を守るためには、法定休日だけでは足りません。そのため、企業は独自に法定外休日を設定し、年間休日を105日以上としています。
最低ラインを下回る場合は罰則がある
労働基準法第35条にある法定休日(年間52日)を下回る企業には、罰則があります。罰則の内容は、労働基準法第119条で規定されており、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
なお、休日とは「労働契約において労働義務がないとされている日」のことで、原則として同じ日付の0〜24時までの、連続した24時間を指します。
例えば、法定休日が日曜日の会社で、土曜日の18時から翌日の午前1時まで残業した場合、その日曜日を休日として与えたことにはなりません。
出典: 労働条件 : 休憩・休日(休憩・休日) | 徳島労働局
休日に働く場合の規定
法定休日の労働についても、労働基準法第36条に規定があります。企業が従業員を法定休日に労働させるには、「36(さぶろく)協定」と呼ばれる労使間の協定を結び、就業規則や労働契約に明記しなければなりません。
また、振り替え休日を設定せず法定休日に労働させた場合、通常賃金の1.35倍以上の割増賃金を支払うこととされています。
振り替え休日とは、法定休日に労働する代わりに、別の労働日を休日にすることです。労働日に振り替えとなるため、休日労働の割増賃金は発生しませんが、事前に従業員へ通知する必要があります。
一方、法定外も含めた休日労働の後に付与する休日を、代休といいます。法定休日に労働させ、後日代休を与える場合は休日労働の割増賃金の対象です。
出典:法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省
年間休日が最低ライン以下でも違法にならないケース
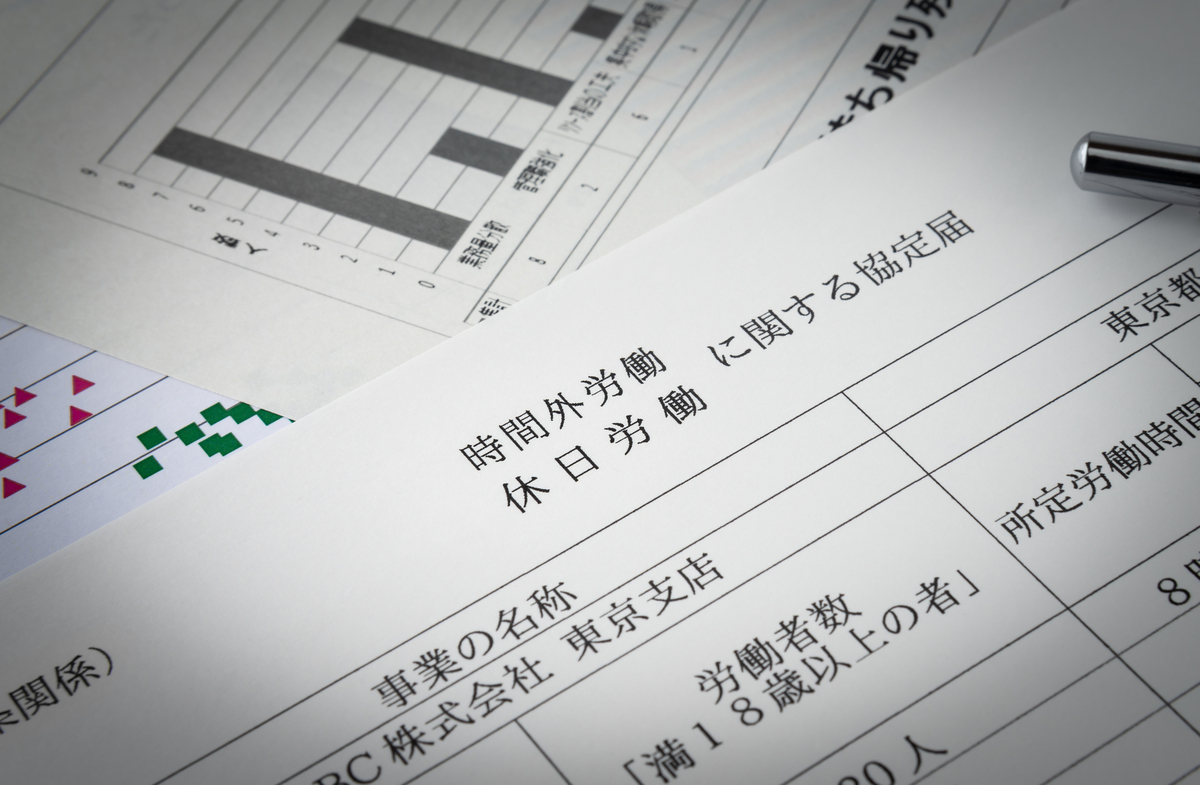
年間休日が105日未満だからといって、必ずしも労働基準法に抵触するとは限りません。ここでは、最低ライン以下でも違法ではないケースを紹介します。
労働時間が短い
105日は、労働基準法の労働時間の規定(1日8時間かつ週40時間)をクリアするための、最低ラインです。このため労働時間が短い場合は、年間休日が105日未満でも違法とはなりません。
例えば、1日の労働時間が6時間とすると、週に6日働いても1週間の労働時間は36時間ですから、労働基準法の規定内です。週に1日は休みがあるので、「毎週少なくとも1日、または4週を通じて4日以上」の規定もクリアできます。
労働時間が7時間の人は、年間の労働日数が「2,080÷7=298日」となり、年間休日は「365-298=67日」あればよいことになります。
36協定を締結している
36協定を締結している場合、年間休日が105日未満でも問題ないケースがあります。36協定は、時間外労働や休日労働に関する労使間の取り決めです。
協定を結び、労働基準監督署に届け出れば、企業は従業員に時間外労働・休日労働をさせられます。
ただし、36協定で認められる時間外及び休日労働の時間には、上限が設けられています。時間外労働と休日労働の合計が「月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内」であれば、年間休日数が105日より少なくても違法とはなりません。
労働形態が変則的
フレックスタイム制や裁量労働制、変則労働制を採用している場合も、違法にならないケースが多いでしょう。
変則労働制は、ホテルやタクシーなど、繁忙期と閑散期の差が激しい業界でよく採用されます。忙しさに応じて、労働時間の配分を認める制度です。
忙しい時期には連続出勤となりますが、暇な時期にまとまった休みを取れます。ただし、1カ月以上1年以内の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことが条件です。
有給休暇を含めている
基本的に、年間休日に有給休暇は含まれません。しかし、有給休暇を含めて105日とすることは可能です。
フルタイム勤務の場合、入社後半年経過すれば、10日の有給休暇が与えられます。有給休暇は1年に5日は必ず取得しなくてはならないため、その分を含めて年間休日を105日とすれば、問題ありません。
ただし、労働時間の規定や、36協定の範囲を超えないように注意する必要はあります。
年間休日が少ない場合の対応策

十分に休めない状態では、仕事のパフォーマンスが低下するばかりか、心身の健康を害する恐れもあります。以下、年間休日が少ないときの対応策を見ていきましょう。
最低ラインを下回っているとき
法定休日の最低ライン52日や、1日8時間・週40時間労働での最低ライン105日を下回る場合は、労働基準法に抵触している可能性があります。
会社が設定する休日が明らかに少ないときは、労働基準監督署に相談すると効果的です。調査の上、違反が認められれば、労働基準監督署は企業に是正を勧告します。
従わないと刑事手続きに発展する恐れがあるため、勧告された時点で休日日数の改善が期待できます。
平均よりも少ないとき
違法ではないものの、年間休日が平均よりも少ない場合、増やしてほしいと思う人も多いはずです。休日労働が多いのに振替休日・代休を取りにくく、年間休日が少なくなるケースもあります。
このように、労働条件を改善してほしいときは、会社と交渉してみましょう。個人よりも複数人で交渉する方が、成功する可能性が高くなります。
労働組合があるなら、団体交渉の場で提案してもらうのがおすすめです。ない場合は、同じ考えを持つ従業員と一緒に交渉を持ちかけるとよいでしょう。
それでも改善されない場合は、思い切って転職するのも一案です。ただし、年間休日の多さだけで、転職先を選ぶのはよくありません。これまでの経験・スキルを発揮できるかどうかも、しっかりと検討した上で応募しましょう。
年間休日の平均日数

年間休日の日数は、企業規模や業種によって異なります。全国平均と、休日が多い業種・少ない業種を紹介します。
全国平均は約110日以上
厚生労働省の調査によると、2023年の労働者1人あたりの年間休日数の平均は116.4日で、1企業あたりの平均は112.1日です。前年では、それぞれ115.6日・110.7日でしたので、いずれも増えていることが分かります。
また、企業規模が大きいほど、休日日数も多い傾向です。
- 1,000人以上:117.1日
- 300~999人:115.9日
- 100~299人:113.6 日
- 30~99人:110.0日
年間休日が多い業種・少ない業種
「令和6年就労条件総合調査」によると、2023年の年間休日数が最も多かった業種は「情報通信業」で、121.3日です。次いで「金融業・保険業」が120.7日、3位は「学術研究、専門・技術サービス業」で120.5日でした。
情報通信業のように企業との取引が中心の業種は、休日が多い傾向にあります。特に金融業は、銀行法に祝日・年末年始の休みが定められていることもあり、カレンダー通りに休みやすい業種といえるでしょう。
「学術研究、専門・技術サービス業」には、労働者が自分で仕事量を調整できる特徴があります。一方、年間休日が少ない業種は、以下の通りです。
- 宿泊業、飲食サービス業:100.3日
- 運輸業、郵便業:103.5日
- 小売業:104.4日
いずれも土日祝日が労働日となるケースが多いため、年間休日も少なくなりがちです。
年間休日の日数別の働き方のイメージ

年間休日の日数が違うと、生活にどのような影響があるのでしょうか?日数別に、考えられる働き方を見ていきましょう。
最低ラインの105日の場合
年間休日が最低ラインの105日だったとしても、週に2日は確実に休めます。1年は約52週のため、毎週土曜日と日曜日に休めば年間休日は104日となるからです。
ただし、この場合祝日はほぼ休めないでしょう。残りは1日しかないため、4連休以上の長期休暇の取得も難しくなります。
夏季や年末年始などに続けて休むには、週2日の休みのうちどちらかを出勤日にしたり、有給休暇を使ったりする必要があります。
110日の場合
年間休日が110日あれば、毎週土曜日・日曜日に加えて、計6日間の休みを取れます。ただし、祝日は出勤となり、連続休暇も最大6日までしか取れません。旅行や帰省の機会も、限られるでしょう。
このため月に1~2回、土曜日を出勤日として祝日を休みにしたり、夏季や年末年始の休暇に充てたりする会社も多いようです。
月に1回土曜日に出勤すれば、年間で12日分の休みを他の日に回せるので、夏季や年末年始をゆっくり過ごせます。
120日以上の場合
1年間の土日祝日は、約120日あります。年間休日が120日以上に設定されていれば、完全週休2日に加えて祝日もほぼ休みとなり、カレンダー通りの生活が実現するでしょう。
さらに、夏季・年末年始休暇を付与し、120日を超える年間休日を設けている会社もあります。これに加えて有給休暇を使えば、より多く休むことも可能です。
1年のうち約1/3が休みとなり、ワークライフバランスを保ちやすいでしょう。
年間休日の最低ラインを意識しよう

年間休日は、52日の法定休日と、労働時間の規定を考慮して企業が設ける法定外休日の合計です。1日8時間・週40時間労働の場合は、105日が最低ラインです。
平均日数は約112日で、企業規模が大きいほど日数も多い傾向にあります。また宿泊業・小売業など、土日祝日に働くことが多い業種では、年間休日が少なくなっています。
土曜日と日曜日、さらに祝日も完全に休むなら、年間休日は120日必要です。休日の日数だけで働きやすさは判断できませんが、働き方の参考として意識することは重要といえます。
これから転職先を探すなら、国内最大級の求人情報一括検索サイト「スタンバイ」を利用してみましょう。さまざまな条件の求人を多数扱うスタンバイなら、理想の仕事に出会える可能性が高まります。
