会社に退職の意思を伝えたとき、引き止めにあう人は少なくありません。しかし、引き止めにあう理由と対処法を知っていれば、冷静に対応できます。そこで本記事では、退職の引き止めにあいやすいパターンと、それぞれの対処法について解説します。
この記事のポイント
- 退職の引き止めを回避する方法
- 退職の意思を伝えると、会社側から引き止めにあうケースは少なくありません。退職の意思が固い場合は、今後のキャリアビジョンや転職先を明確に伝えることが重要です。
- 会社が退職を引き止める理由
- 会社が退職を引き止める理由としては、人材不足や上司の評価が下がることへの懸念や優秀な人材を手放したくない思惑などが考えられます。
- 退職の引き止めは違法になる可能性がある
- 過度な退職の引き止めは、法律違反やパワーハラスメントにあたる可能性があります。退職を受理しない行為や、脅迫的な言動は違法です。
「パターン別」退職の引き止めを回避する方法
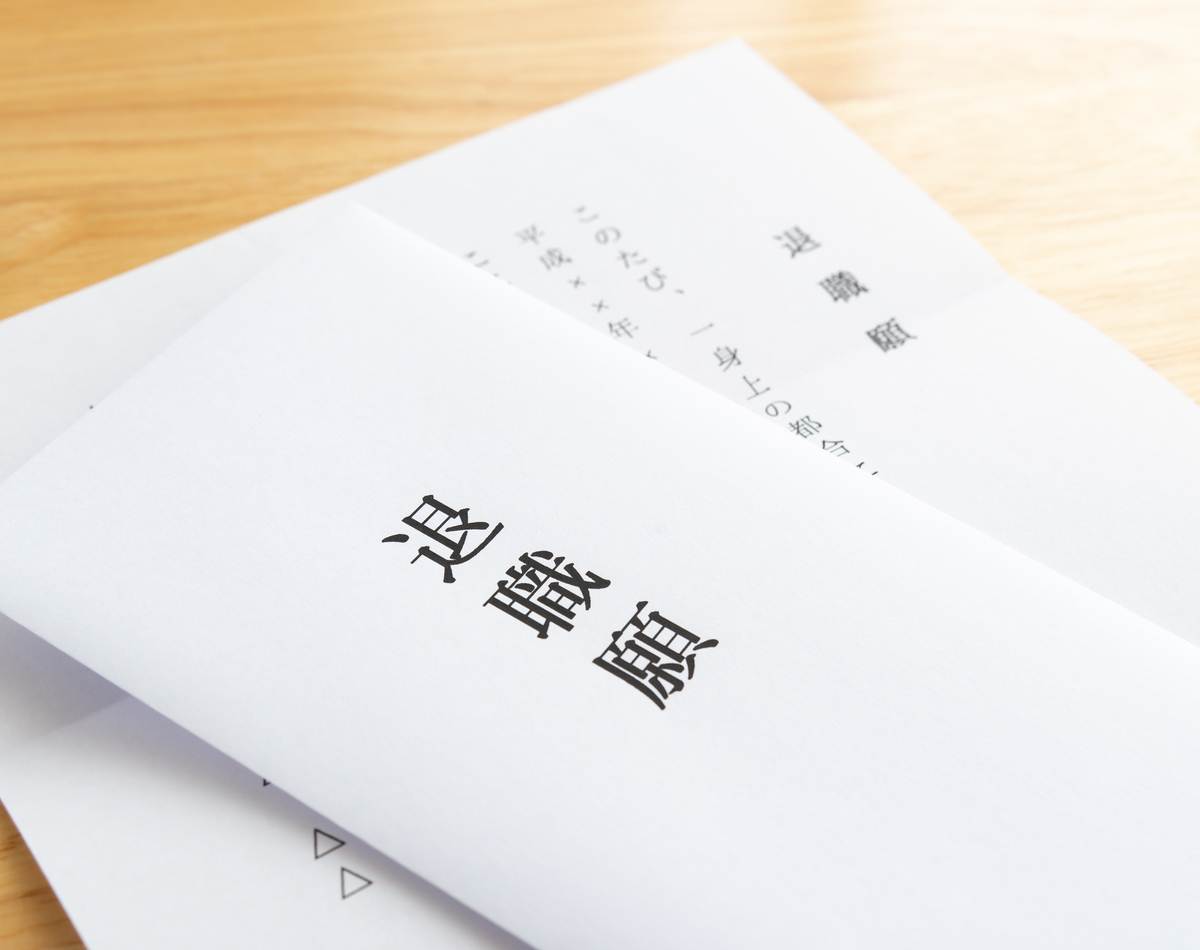
「自分のしたい仕事ができない」「職場環境が合わない」「将来に期待が持てない」など、退職理由は人によってさまざまです。
しかし、会社に退職の意思を伝えると引き止めにあうケースも少なくありません。以下で退職の引き止めを回避するためのパターン別の対処法を紹介します。
感情に訴えてくる場合
退職の引き止めでよくあるのが、感情に訴えかけてくるパターンです。たとえば「この仕事はあなたにしかできない」「あなたが辞めたら会社は大損害を受ける」「あなたの将来に期待している」など、承認欲求をくすぐるような言葉で引き止めようとします。
誰しも他者から認められたい・尊重されたい・評価されたいという気持ちは持っているものです。そのため、このような言葉をかけられると、退職の決意が揺らぐ人も。
しかし自分の将来に関わる決断をするためには、感情に流されてはいけません。冷静に判断するために、考える時間をもらうことも有効な手段です。
待遇の改善を提案してくる場合
退職理由が待遇面にある場合、上司から待遇改善を持ちかけられるケースもあります。具体的には、給料アップ・昇進・残業時間の削減・部署異動の提案などです。
待遇が原因での退職であれば、改善してもらうことで退職を踏みとどまる人もいるでしょう。しかし社長・役員ではない限り、上司が独断で待遇を改善できるとは限りません。
待遇改善が実現すれば、会社に残る選択肢も出てきます。待遇が改善すれば現職を続けていけるか、また本当に待遇は改善されるのかを冷静に見極めた上で決断しましょう。
不安をあおってくる場合
「退職するなら懲戒解雇にする」「損害賠償を請求する」「契約違反として違約金を払ってもらう」など、さまざまな手段で不安をあおってくる可能性もあります。
しかし、懲戒解雇は会社の資金横領などの重大な理由がない限り、認められるものではありません。損害賠償請求・違約金についても同様です。
強い言葉で脅されると不安になるかもしれませんが、圧力をかけて退職を思いとどまらせる行為は違法です。もしもの場合は、労働局などの行政機関に相談するようにしましょう。
上司が退職を引き止めるのはなぜ?

退職を申し出た際、上司に引き止められるケースは少なくありません。なぜ上司は退職を引き止めるのでしょうか。よくある理由を3つ紹介します。
人材不足の回避
社員が1人退職すると、職場の人材が不足し、組織全体の戦力ダウンにつながる可能性があります。すぐに人材を補充できれば問題ありませんが、人員に余裕のある企業は多くありません。
また新たな人材を採用するためには、コストと時間がかかります。そのため、退職を引き止めるほうが企業にとって都合が良いともいえます。
退職によって職場がひっ迫することに、申し訳なさを感じる人もいるかもしれません。しかし大切なのは自分の今後の働き方です。一時的に会社に迷惑をかけることになっても、心配し過ぎる必要はありません。
上司の管理能力に対する評価の懸念
社員が退職を申し出る相手は、通常、直属の上司です。上司は部下を管理する責任を負っているため、部下の退職は管理能力不足とみなされ、評価が下がる可能性があります。
また人員が減ることで、残ったメンバーで業務を進めなければならず、上司の負担が増える場合もあるでしょう。このような状況を避けるため、上司は退職を引き止めることがあります。
上司の立場を考慮して退職を躊躇する人もいるかもしれませんが、まずは自分の長期的なキャリアを優先しましょう。もちろん、お世話になった上司には、感謝の気持ちを伝えることを忘れてはいけません。
優秀な人材を手放すことへの不安
優秀な人材の退職は、企業にとって大きな損失です。特に、専門性・実務能力・リーダーシップなどを持つ人材の退職は、企業の競争力低下につながる可能性があります。
また、優秀な人材は周囲の人材にも刺激を与え、組織の活性化に貢献していることも少なくありません。
そのため、企業は優秀な人材の流出を、短期的な業務への影響だけでなく、長期的な成長戦略への影響も懸念します。従って優秀な人材ほど、強く引き止められる傾向にあります。
ポジティブな理由で引き止められると嬉しく感じるかもしれませんが、自分の市場価値・ビジョンを冷静に見極めて判断することが大切です。
過度な退職引き止めは違法になる?

会社側からの過度な退職の引き止めは、法律違反・パワーハラスメントに該当する可能性があります。どのような行為が違法になるのか、具体的に説明します。
退職を受理しない行為は法律違反になる
退職の意思を伝えたにもかかわらず、上司や会社が退職を受理してくれない場合・何らかの理由をつけて強引に引き止める行為は、法律違反にあたります。
民法627条1項では労働者への退職の自由が認められており、正社員の場合、退職の意思表示から2週間が経過すれば雇用契約は解除されます。つまり、退職希望日の2週間以上前に伝えれば、法律的には問題はありません。
ただし例外として、年俸制で6カ月以上の雇用契約を結んでいる場合は、3カ月前までに申し出る必要があります。また契約社員の場合は、原則として契約期間満了まで退職できません。
退職拒否はパワハラに該当する
厚生労働省は、役職上の優位な関係を利用し、業務上必要な範囲を超えて従業員の就業環境を悪化させる行為を「パワーハラスメント」と定義しています。
「懲戒解雇にする」「損害賠償を請求する」「違約金を支払わせる」などの脅し文句が、退職に関するパワーハラスメントの例です。
また直接的な脅しだけでなく、有給休暇を取得させない・給料や退職金を減額するといった行為なども、パワーハラスメントにあたる可能性があります。
出典:「労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止対策義務化)について」|厚生労働省
退職の引き止めに合わないためには?

退職の引き止めに合わないためには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、主なポイントを3つ紹介します。
今後のキャリアビジョンをしっかり伝える
退職理由は、建設的で前向きなものであることが理想的です。そのため、今後の自分のキャリアビジョンを明確に伝え、それが今の会社では実現できないことを理解してもらう必要があります。
不満を理由にしてしまうと、「不満が解消されれば会社に残るのか」と引き止めにあう可能性があります。
たとえ不満が退職のきっかけであったとしても、「このような分野に挑戦したい」「経験を積んで、その分野の専門家を目指したい」など、前向きな退職理由を述べましょう。
「そのようなことを目指すのであれば、今の会社では難しいかもしれない」と上司に納得してもらえれば、気持ちよく送り出してもらえるかもしれません。
転職先を決めておく
退職の決意を固めるためには、次の転職先を事前に決めておくことが重要です。転職先が決まっていることを伝えることで、退職への強い意志を示すことができ、会社側も引き止めにくくなります。
転職先の入社日に合わせて退職日を決めれば、引き止めに合って退職が先延ばしになる心配もありません。優柔不断な態度や伝え方は引き止めにつながりやすいため、注意が必要です。
一度退職を決めた理由を忘れずに、感情に流されないようにしましょう。有給休暇の消化も含め、最終出勤日を早めに伝えることも大切です。
感情的にならず一貫した姿勢で伝える
退職の引き止めに合わないためには、感情的にならず、冷静かつ具体的な退職理由を伝え、一貫した態度を保つことが重要です。
上下関係が厳しい会社では、退職に上司の許可が必要だと考える人もいるかもしれません。しかし退職は労働者に認められた権利であり、「許可をもらう」のではなく、「退職は決定事項である」という態度で交渉することも大切です。
円満に退職するためには、丁寧な対応と入念な準備が欠かせません。退職後も会社の人たちと関係が続く可能性があるため、礼儀を守って対応しましょう。また、退職後の業務が滞らないように、引き継ぎをしっかりと行うことも重要です。
円満に退職して次の道へ進もう

感情に訴えかけられたり、懲罰的な処分を示唆されたりすると、退職の気持ちが揺らぎ、躊躇してしまうかもしれません。しかし退職・転職は人生における重要な決断でもあり、一時的な感情で簡単に考えを曲げないようにしましょう。
引き止められたときは、退職を決意した理由を忘れず、一貫した態度を保つことが大切です。そのためには、転職先を事前に決め、退職は決定事項であることを明確に伝えることが重要といえます。
退職後の転職を検討している場合は、国内最大級の求人情報一括検索サイトである「スタンバイ」をご覧ください。
