専門知識を持つ人や定年を迎えた人が、企業から嘱託社員になることを打診されるケースがあります。嘱託の意味を知らないと、どのような働き方なのかイメージできないでしょう。
不利な立場にならないようにするには、労働契約を結ぶ前に他の就業形態との違いや労働条件などを理解しておくことが大切です。
この記事では、嘱託社員の働き方やメリット、待遇、注意点などを解説します。労働契約を結んだ後で後悔しないように、嘱託社員に対する理解を深めましょう。
この記事のポイント
- 嘱託社員の意味
- あらかじめ期間を定めた雇用契約で働く社員を指し、定年後に再雇用される際などによく採用されています。
- 一般的な労働条件
- フルタイムで働く場合もあれば労働時間を減らせる場合もあり、どのような労働契約を結ぶかは企業によって異なります。
- 注意点
- 有期雇用契約で働く際は、あらかじめ定められた期間が終わると、契約が更新されない可能性があります。
嘱託とは何か?

明確な定義はないものの、多くは有期雇用としての働き方を指します。契約内容は企業によりさまざまです。よくある2つの働き方を見ていきましょう。
定年後の再雇用として働くケース
一般的な働き方として、定年後の再雇用時に嘱託社員として雇用されるケースが多いでしょう。再雇用とは、定年を迎えた従業員を企業が再び雇い入れることです。
再雇用した従業員を、嘱託社員と呼ぶ場合があります。再雇用を希望する従業員を、嘱託社員として雇い入れる企業は少なくありません。
引き続き同じ部署で働ける場合もありますが、別の仕事を任せられる場合もあります。どのような条件で働くのか、しっかりと確認することが大切です。
高度な専門性を求められるケース
嘱託社員と呼ばれるのは、再雇用された人だけではありません。高度な専門性が求められるスペシャリストとして、雇用されるケースもあります。
例えば、嘱託医や嘱託弁護士などが該当します。社内では対応できない問題を解決するために、専門的な知識を持つ人に業務を任せる場合があるでしょう。
こちらは業務委託として働く場合があり、通常の業務を担う従業員に比べ、高待遇で迎えられる例も珍しくありません。
嘱託社員が求められる背景

多くの企業で嘱託社員が採用されています。なぜ、定年を迎えた社員を再雇用するのでしょうか。嘱託社員が求められるようになった社会背景について、理解を深めましょう。
少子高齢化による労働人口の減少
嘱託社員が求められるようになったのは、少子高齢化により労働人口が少なくなったことが影響しています。近年の日本社会では、これまでのように若い世代が働くだけでは、国民の生活が立ち行かなくなる恐れがあるのです。
また、一定の経験やスキルを持つ層に働いてもらいたいという企業の思惑も、無関係ではありません。
労働政策研究・研修機構(JILPT)では、さまざまなシナリオを想定して労働力需給を推計していますが、どのシミュレーションでも労働力人口が減少していきます。
また、女性・高齢者などの労働市場への参加が進展するシナリオ、経済成長と女性・高齢者の労働市場への参加が一定程度進むシナリオの両方で、15歳以上人口に占める労働力人口の割合は2022年の水準よりも上昇する見込みです。
出典:資料シリーズNo.284「2023年度版 労働力需給の推計―労働力需給モデルによるシミュレーション―」|労働政策研究・研修機構(JILPT)
高年齢者雇用安定法の影響も
嘱託社員が求められている背景には、高齢者雇用安定法により、65歳までの安定的な雇用の確保が必要とされている点も関係しています。
政府は企業に対し高年齢者雇用安定法を定め、定年年齢の引き上げや定年制の廃止、再雇用制度・勤務延長制度など、70歳までの継続雇用制度を導入するように呼び掛けています。
定年が65歳未満の場合に、嘱託社員として再雇用する方法が採用されやすいでしょう。
出典:高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~|厚生労働省
出典:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 8・9条| e-Gov 法令検索
嘱託社員と他の働き方の違い
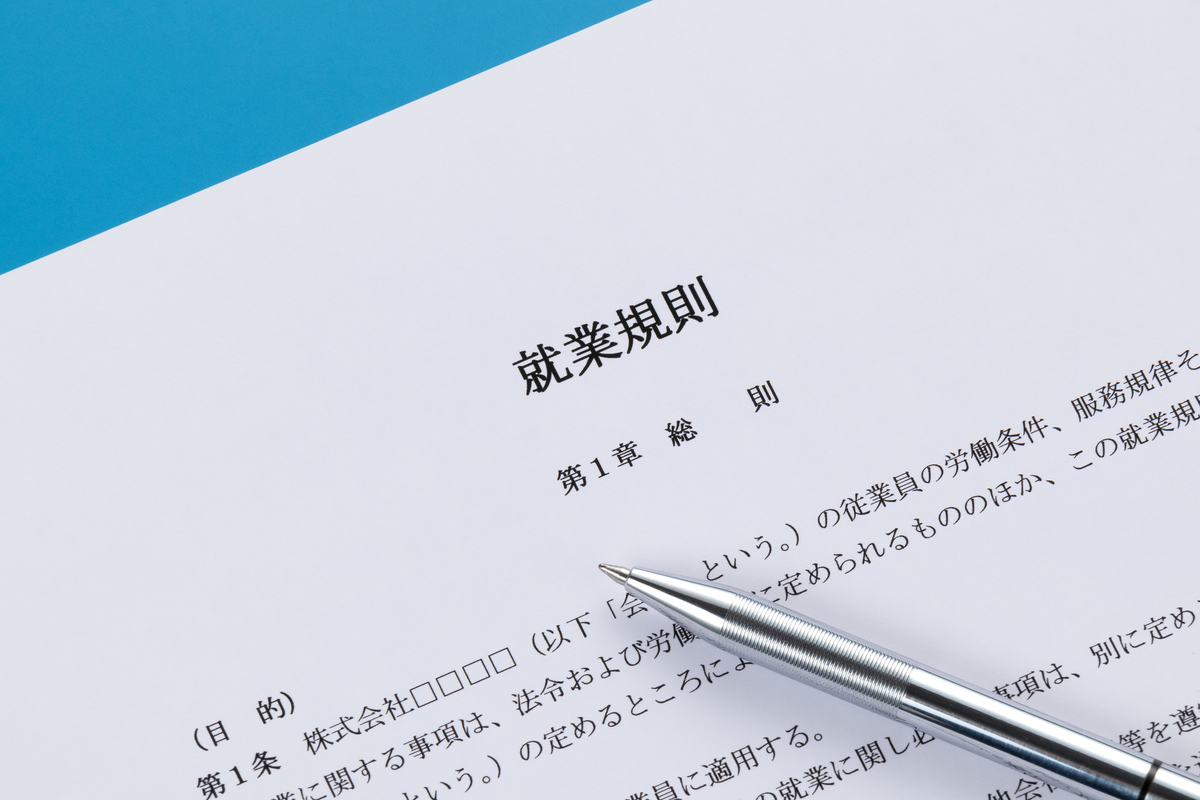
嘱託社員は法律によって明確に定義されているわけではありません。一般的な嘱託と正社員の違いや、それ以外の雇用形態との違いを見ていきましょう。
嘱託と正社員の違い
嘱託社員と正社員の共通点は直接契約であることですが、嘱託社員は非正規雇用です。両者の大きな違いは、雇用期間の有無と労働時間です。
雇用期間の定めがない正社員とは違い、嘱託社員は1〜2年などの期限が設けられています。また、嘱託社員はフルタイムでの勤務をしない場合があります。
正社員は企業側の勝手な都合では解雇できませんが、嘱託社員は契約期間が満了すれば契約更新されない可能性があり、安定性が高いとはいえない働き方です。
嘱託と派遣社員の違い
嘱託社員と派遣社員の大きな違いは、雇用契約を結んでいる相手が異なる点です。嘱託社員は働いている企業と直接契約を結びますが、派遣社員は派遣会社と契約を結んでいます。
嘱託社員は雇用されている企業から給与が支給され、契約内容もそれぞれの雇用主によって異なります。一方、派遣社員は派遣会社に給与の支払い義務があり、昇給などを決めるのも派遣元です。
企業側からすると、再雇用の嘱託社員は採用活動の手間がかからず、派遣会社への手数料が必要ないといったメリットがあります。
嘱託とパート・アルバイトの違い
嘱託とパート・アルバイトは法律上で大きな違いはありませんが、給与体系が異なるケースが少なくありません。嘱託社員は固定給、パート・アルバイトは時給制であることが一般的です。
企業によって違いはあるものの、パートやアルバイトに比べ、嘱託社員の方が正社員に近い扱いと認識されています。また、両者は無期雇用への転換方法が異なる点も押さえておきたいポイントです。
パートやアルバイトは通算の労働期間が5年を超えると、無期労働契約への転換を申し込む権利が発生しますが、嘱託社員は無期転換ルールの適用外とする特例が定められています。
出典:無期労働契約への転換
出典:無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について
再雇用における嘱託の労働条件について
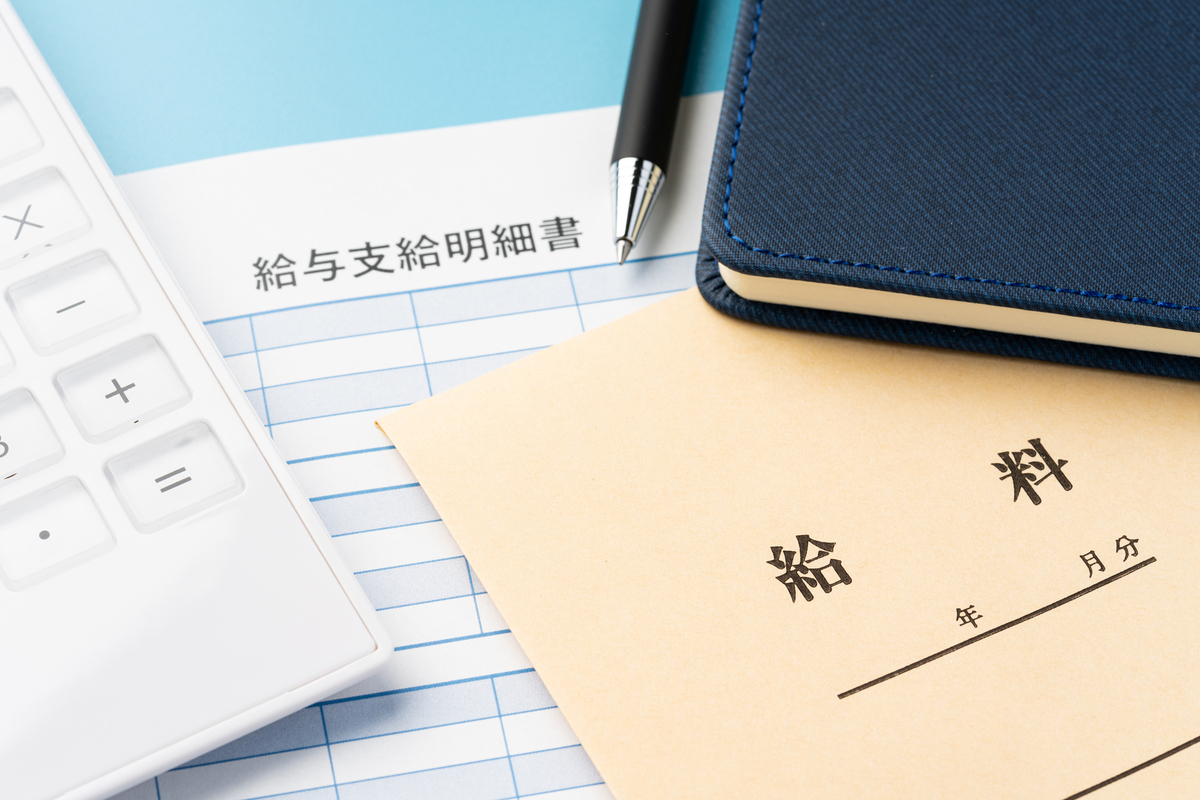
再雇用の一般的な労働条件を知っていると、交渉や検討がしやすくなります。再雇用では、どのような条件で働くケースが多いのか、見ていきましょう。
労働時間
嘱託社員の労働時間は、正社員のように法律で定められているわけではないため、企業によってさまざまなケースがあります。基本は企業と相談して決定し、社員ごとに設定した条件を契約書に記載する流れです。
厚生労働省の調べでは、約7割の嘱託社員が正社員と同じ労働時間であることが報告されています。
しかし、正社員のときと同様に働きたいと思っても、企業側の事情によっては実現できない場合があります。また、体力やモチベーションの低下などにより、これまでと同じようには働けないケースもあるでしょう。
出典:嘱託社員では1日の所定労働時間が正社員と「同じ」が7割|厚生労働省
給与
給与を決定する決まりとして同一労働同一賃金の定めがあるため、正社員と労働条件や責任の重さが同じ場合、嘱託社員だからという理由で大きく下がることはありません。
ただし、業務内容の範囲が狭まるケースがほとんどであるため、正社員のときよりも少なくなるのが一般的です。
役職から解放されたり、勤務日数・時間が短くなったりする場合、これまでと全く同じ給与はもらえないでしょう。個人差はありますが、正社員時代の7割程度になるケースが多いとされます。
賞与
嘱託社員は賞与の対象外となるケースが多く、嘱託社員を含む契約社員やアルバイト・パート社員などの非正規社員は、賞与を支給しないと定めている企業が一般的です。
企業によっては、社員の勤務形態に関係なく一定割合の賞与を支給する場合もあります。ただし、賞与が支給されたとしても、正社員に比べると少ない傾向です。
賞与の有無や金額は企業によって異なるため、就業規則を確認しましょう。
社会保険
嘱託社員であっても、条件を満たせば社会保険に加入しなければなりません。社会保険に加入する条件として、以下のようなものが挙げられます。
- 月額8万8,000円以上の給与が支給されている(残業代や通勤手当、賞与は除外)
- 週の勤務時間が20時間以上
- 2カ月を超えて勤務する予定
- 学生ではない(通信制・定時制・休学中の人は除外)
社会保険に加入すると保険料の負担が発生しますが、長期的な視点で見ればメリットもあります。例えば、けがや病気で働けなくなった際に、医療保障が充実する点は魅力です。
出典:従業員のみなさま | 社会保険の加入条件やメリットについて|厚生労働省|社会保険適用拡大 特設サイト
労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険のことで、加入は事業主の義務です。雇用形態に関係なく全ての従業員が加入します。
社会保険とは異なり、基本的には正社員と同じ扱いです。ただし、働く時間が短い場合は雇用保険の対象外となります。
これまでフルタイムで働いていた人が、再雇用などで週の労働時間が20時間未満となった場合は、事業主が資格喪失の手続きを行う決まりです。資格喪失手続きが済めば、雇用保険料の負担がなくなります。
出典:事業主が行う雇用保険の事務手続に係る取扱いの変更について | 東京労働局
有給休暇
職種や就業形態にかかわらず、一定の条件を満たしていれば有給休暇がもらえます。継続勤務年数に応じた日数が付与される決まりです。
フルタイムで勤務する場合、最大で年間20日の有給休暇が発生します。週の所定労働日数が4日以下、週の所定労働時間が30時間未満の場合も、一定の有給休暇が付与されます。
例えば、週の勤務日数が4日で1年間の所定労働日数が169〜216日の場合、最大で15日間の有給休暇を取得できるルールです。
また、嘱託社員として再雇用された場合、勤続年数を通算することが可能です。定年前の有給休暇も、2年の時効を迎えるまでは使えます。
退職金
再雇用前の定年時の退職金は、通常通り支払われます。再雇用されることが決まっている場合も勤務年数に応じた退職金を受け取れますが、嘱託社員として働いた後は必ずしも支払われるとは限りません。
非正規雇用の場合、退職金を不支給とする企業もあり、嘱託社員に関する規定によって異なります。企業ごとに条件が異なるので、就業規則を確認しましょう。
嘱託社員の場合は再雇用で労働契約を結ぶ際に、退職金の扱いについてチェックすることが大切です。
嘱託社員として働く利点

嘱託社員になると収入が減り、いつまで働けるか分からないことに不安を感じる人もいるでしょう。しかし、嘱託社員には正社員にはないメリットがある働き方です。どのような利点があるのか、見ていきましょう。
柔軟な勤務体系を利用できる
嘱託社員になる利点は、体力や集中力に応じて従来通りの働き方をしたり、勤務時間を短くしたりといった融通が利きやすい点です。
再雇用で嘱託社員になる場合、働き盛りの年齢を過ぎているので肉体的な負担を減らしたいと考える人もいるでしょう。中には、家族と過ごす時間や趣味に、多くの時間を使いたいと考える人もいるかもしれません。
嘱託社員は正社員とは違い、自分にとって働きやすい労働時間や日数を選べることが多く、仕事と私生活のバランスを取りやすいでしょう。
新しく職場や仕事に慣れる必要がない
再雇用で嘱託社員になると、慣れ親しんだ環境で仕事を続けられます。基本的には今までと変わらない環境で同じ業務に従事するケースが多いため、仕事を覚えられず苦労する心配がありません。
別の会社に再就職する場合に比べ、新しい環境に飛び込まなくて済みます。就職活動をしなくて済むところもメリットです。
一から仕事を覚え、人間関係を構築するのは大変だと感じる人にとっては、メリットが大きいといえます。
安定した収入を確保できる
正社員から嘱託社員になると収入は減るのが一般的ですが、全く新しいアルバイトやパートを始める場合と比べれば、比較的安定した収入を得られます。
定年後も生活を安定させられ、過度にお金の心配をしなくて済む点はメリットです。
年金が支給されるのは65歳以上なので、貯蓄などの余裕がない場合、節約を余儀なくされる場合もあります。無職の人に比べれば、ゆとりのある生活を送れるでしょう。
嘱託社員として働く際の注意点

嘱託社員として働く場合、正社員のときとは労働条件が変わるため、あらかじめ注意点を理解しておく必要があります。そこを怠ると、再雇用された後で後悔するでしょう。嘱託社員として働く際の注意点を紹介します。
契約が継続されるとは限らない
嘱託社員は基本的に有期雇用のため、契約の期限を迎えたときに必ず更新されるとは限りません。正社員とは違って、無期限の雇用が約束されているわけではない点に注意しましょう。
契約が更新されない場合、新しい職を探すことが難しくなるケースもあります。本人の経歴やスキルにもよりますが、60歳以上になると若い頃に比べて積極的に雇い入れてくれる企業が減る傾向です。
新しい職を探す際は、これまでと同じ職種にこだわらず、シニアが働きやすい職場を探すなどの工夫が求められるでしょう。
正社員時より給与が下がる傾向がある
定年後の再雇用では、希望してもこれまでと同じ労働条件で働けないケースもあります。同じ職場で働いていても、正社員のときより給与が下がる傾向です。
ボーナスや退職金がない場合もあり、待遇や給与に満足できない人もいるでしょう。多くの収入が欲しい人は、続けるのが難しいかもしれません。
また、正社員のようなプレッシャーがない点はメリットですが、モチベーションが低下する心配もあります。
企業が嘱託社員を採用する理由

正社員と比べ勤務日数や労働時間が減りやすい嘱託社員を、企業側が雇うのにはどのような理由があるのでしょう。企業が嘱託社員を採用する理由を紹介します。
生産性向上につながる期待
再雇用で嘱託社員を採用する理由の1つが、生産性を向上させるためです。ベテラン社員を継続して雇用すれば、業務のノウハウを蓄積できます。
即戦力として働いてもらえるので、業務効率が落ちる心配もありません。
新人に仕事を教えるには、多くの労力を必要とします。ルーティンワーク化されていない、専門的な仕事を教えられる人材は貴重です。
経験や知識が豊富な嘱託社員がいれば若手の指導を任せられ、生産性が下がらずに済むでしょう。
人件費の削減効果
新入社員を育成するときのようなコストがかからない点も、嘱託社員を採用する理由です。定年を迎えた後も、長年勤務した経験を生かして働いてもらえます。
嘱託社員は勤務日数や労働時間が減る傾向があり、基本給が低くなるだけでなくボーナスもカットできます。正社員を雇う場合に比べて人件費を下げられる点も、企業にとって大きな魅力です。
経験や知識を持った人材を安く雇うことで得られる効果は大きく、企業の競争力アップにも役立つでしょう。
企業のイメージアップ効果も
専門性の高い従業員がいると、サービスの質を向上できます。特定の分野に強みのある企業としてアピールでき、結果的に取引先や顧客からのイメージアップにつながります。取引先や顧客との信頼関係構築にも役立つでしょう。
また、取引先や顧客から「年齢に関係なく人材を大切にする企業」という前向きなイメージも持ってもらえます。
多様な人材が働ける環境が整っている企業として認知されれば、将来的な人材の確保にもポジティブな影響があると考えられます。
嘱託社員における「雇い止め」のリスクとは

嘱託社員として働く際は、雇い止めのリスクについて理解しておかなければなりません。雇い止めの意味や、拒否する方法などを見ていきましょう。
契約期間満了による雇い止めの可能性がある
雇い止めとは、あらかじめ定められた期間の労働契約が満了した後、事業者側が契約更新を拒否することです。原則として、企業側は契約期間を満了した場合に更新を拒否できます。
嘱託社員だけでなく、契約社員・アルバイト・パートなど、有期雇用で働いている人には雇い止めのリスクがあります。パート社員であっても、無期雇用で働いている場合は該当しません
労働者が更新を希望しなければ、そのまま契約満了です。ただし、一定の条件がそろえば、雇い止めを拒否できるケースもあります。
契約の更新・再契約となる「雇い止め法理」
労働契約法19条において、契約終了に関する制限が設けられています。労働者を保護する目的があり、以下のように実質無期型と期待保護型があります。
- 実質無期型:客観的に見て正社員と業務内容が変わらない場合、雇い止めを認めない
- 期待保護型:業務内容に恒常性があり、契約が更新されると期待できる言動があるなど、契約更新に合理性が認められるケースが該当する
実質無期型に当てはまらない場合でも、期待保護型に該当すれば労働者は雇い止めを拒否できます。
出典:労働契約法 有期労働契約の更新等 第十九条 | e-Gov 法令検索
正社員への道が開く「無期転換ルール」
労働者の雇用を安定させるため、以下の条件を満たした従業員が会社に対して期間の定めのない雇用契約の締結を申し込んだ場合、承諾したことになるルールが定められています。
- 有期雇用契約が1回以上更新されている
- 有期雇用契約が通算で5年を超えている
- 契約満了までの間に、無期雇用の締結を申し込む(口頭での申し込みも可)
基本的には、スペシャリストとして嘱託契約をしている人や、契約社員向けの決まりです。ただし、再雇用による嘱託社員には、無期転換ルールが適用されないという特例があります。
出典:無期転換ルールについて|厚生労働省
出典:無期転換ルールと特例について|埼玉労働局
嘱託社員に関するQ&A

嘱託社員として働くようになると、正社員との違いに戸惑うことがあります。嘱託社員に関するQ&Aをチェックし、疑問を解消しましょう。
嘱託社員も残業はある?
嘱託社員であっても法律で定められた時間外労働を超えない限り、企業が従業員に残業を依頼することは可能です。
残業をした場合、条件を満たせば給与が割り増しされます。1日8時間、週40時間を超える分に対して、通常の1.25〜1.5倍の割り増しがされる決まりです。
ただし、残業代をあらかじめ給料に含む形式を採用している企業もある点に注意しましょう。
雇用契約を交わす際に、残業についての取り決めがされるケースもあります。中には、嘱託社員に残業をさせない方針の企業もあるので、就業規則や契約書を確認しましょう。
出典:2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省
嘱託の有期契約は何年間?
いつまで嘱託社員として働けるのか、心配になる人もいるでしょう。有期雇用契約の期間は原則として3年以内です。3年を超えて働きたい場合、再度契約をしなければなりません。
ただし、厚生労働大臣が定める基準を満たすと、最長で5年以内となります。例えば、博士の学位を有する人や、特定の資格を持った人などが該当します。
満60歳以上の労働者と結ぶ労働契約の上限は5年です。また、期間が定まっている建設工事などのプロジェクト完了に必要な期間を定める契約の場合は、その期間が完了するまで働けます。
嘱託という働き方を上手に活用しよう

嘱託社員は、定年後の再雇用で働く場合に採用されるケースが多い働き方です。また、社内では解決できない問題に対応するため、専門的な知識を持った人を嘱託社員として雇うケースもあります。
嘱託社員として契約を結ぶ際は、給与や賞与、退職金などの条件面に注意が必要です。フルタイムで働く場合、社会保険料や雇用保険が必要になる点も押さえておきましょう。
正社員とは違い時間に融通が利きやすいため、ゆとりのある働き方をしたい人におすすめです。嘱託という働き方を上手に活用し、プライベートを充実させましょう。
