近年の制度改正により、パート従業員も一定の条件を満たせば厚生年金保険に加入できるようになりました。しかし、メリットはあるのか、負担が増えるだけなのか気になる人もいるでしょう。パート従業員の厚生年金加入について、詳しく解説します。
厚生年金とは?パート従業員にも関係する理由
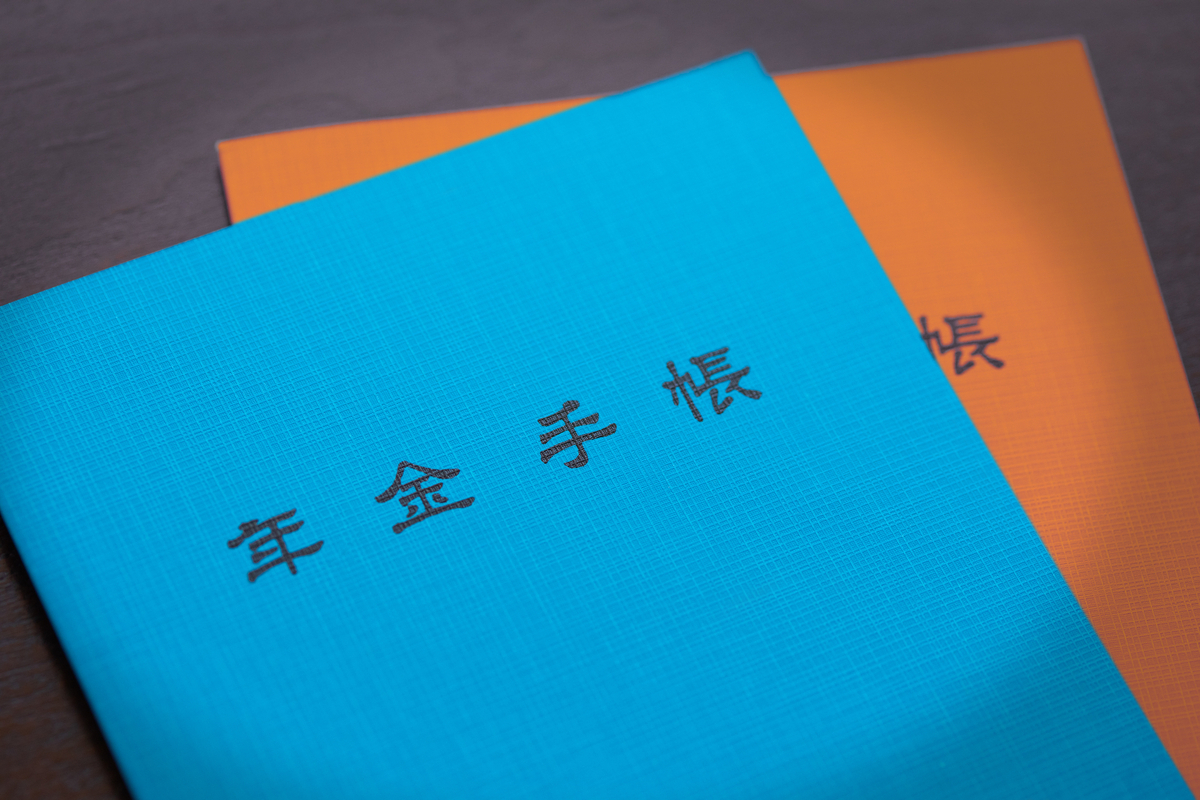
厚生年金は、会社員だけでなくパート従業員にも適用が広がっており、重要性が増しています。将来の生活を支える基盤として、その役割は一層注目を集めています。まずは、厚生年金制度の概要や具体的な仕組みについて詳しく見ていきましょう。
厚生年金保険の基本的な仕組み
厚生年金保険は、国民年金(基礎年金)の上に積み重ねられる2階部分として機能し、会社員や公務員が加入する公的年金制度です。加入者は70歳未満までの期間、毎月の給与から保険料を納めることになります。
保険料は労使で折半して負担し、事業主が一括して納付するため、加入者自身による個別の手続きは不要です。制度の目的は、老後の生活を支える安定した収入源の確保にあります。受給の種類は、以下の3つとなっています。
- 老齢厚生年金
- 障害厚生年金
- 遺族厚生年金
給付額は、加入期間や過去の賃金に応じて決定されますが、高所得者から低所得者への所得再分配機能により、現役時代の収入格差は緩和されます。
パート・アルバイトへの社会保険制度適用拡大
社会保険制度の適用拡大に伴い、一定の条件を満たすパート従業員も厚生年金に加入できるようになりました。2024年10月からは、従業員数51人以上の企業で働くパート従業員にも、加入が義務付けられています。
制度変更の狙いは、多様化する雇用形態に対応し、より多くの労働者の将来的な生活保障を強化することにあります。従業員の福利厚生の充実は、企業にとっても人材確保や定着率向上につながる機会となるでしょう。
パート従業員の厚生年金加入がもたらす効果
パート従業員の厚生年金加入は、社会保障の公平性向上と老後の生活安定に寄与する重要な施策です。
厚生労働省の「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」によると、パート従業員の1時間当たりの基本賃金の割合が、正社員よりも低い企業が41.3%にも上っています。
企業側の社会保険料負担が均等化されることで、雇用形態による待遇差が減少し、正社員への転換も促進されるかもしれません。
また、被用者にふさわしい年金保障が確立されることにより、特にパート従業員比率が高い女性の、老後の社会保障が充実することが期待されます。
出典:令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況|厚生労働省
パート従業員の厚生年金加入条件を詳しく解説

パート従業員の厚生年金加入は、労働時間と賃金による明確な基準が設けられています。「106万円の壁」や「130万円の壁」など、収入制限への理解も重要です。以下で、加入条件の詳細と収入制限の影響について、具体的に解説していきます。
労働時間と賃金による加入条件
パート従業員の厚生年金加入のためには、労働時間や賃金などに関する条件を満たす必要があります。主な加入条件は、以下の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月8.8万円以上
- 雇用の見込みが2カ月以上
- 学生ではない(例外あり)
週の所定労働時間の基準には、残業時間は含まれません。所定内賃金は月額8.8万円以上が条件となり、基本給と諸手当の合計額で判断されるので、残業代・賞与・通勤手当は対象外です。さらに、2カ月を超える雇用見込みがあることも求められます。
原則として学生は加入対象外となりますが、休学中や定時制、通信制の学生は例外的に対象となっています。
106万円の壁と130万円の壁の意味
パート従業員の就労に影響を与える収入制限として、「106万円の壁」と「130万円の壁」が存在します。106万円を超えると社会保険料負担が発生して、手取り収入が減少する可能性があります。
130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、税制上の優遇措置を受けられなくなる決まりです。政府は130万円の壁への対策として、事業主の証明があれば繁忙期の労働時間延長を認める仕組みを整備しました。
厚生年金加入のメリットとデメリット

パート従業員の厚生年金加入は、将来的な老後保障の充実など、さまざまなメリットが期待できます。その一方で保険料負担など、十分な検討が必要な事項もあるでしょう。ここでは、厚生年金加入による具体的なメリット・デメリットを紹介します。
パート従業員にとっての厚生年金加入のメリット
パート従業員が厚生年金に加入することで、老後の生活を支える年金が充実します。加入による主なメリットは、以下の通りです。
- 老齢年金の充実:報酬比例部分の上乗せ
- 障害年金の充実:3級の障害も対象に
- 遺族年金の充実:遺族厚生年金の追加支給
国民年金に加えて報酬比例部分が上乗せされ、月収8.8万円で20年間加入した場合、年間約10万円の増加が見込まれます。
障害年金においては、国民年金では対象外だった3級の障害でも給付を受けられる可能性があるでしょう。遺族年金も、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も支給されます。
また、基本的には厚生年金と同時に健康保険にも加入することになり、病気・ケガによる休業時に給与の2/3相当額が「傷病手当金」として支給されるのも利点です。出産時には、「出産手当金」も受けられます。
パート従業員にとっての厚生年金加入のデメリット
厚生年金に加入する場合、手取り額の減少を考慮する必要があります。厚生年金保険料は、毎月の給与から天引きされるのが基本です。
また、配偶者の扶養から外れることになるので、税金や社会保険料の負担が増える可能性もあります。
さらに、厚生年金加入により、確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額が変更されることも覚えておきましょう。一方で、将来の年金受給額増加というメリットもあります。
現在の負担と将来の利点を、長期的な視点で検討することが重要です。
パート従業員の厚生年金加入手続きと保険料
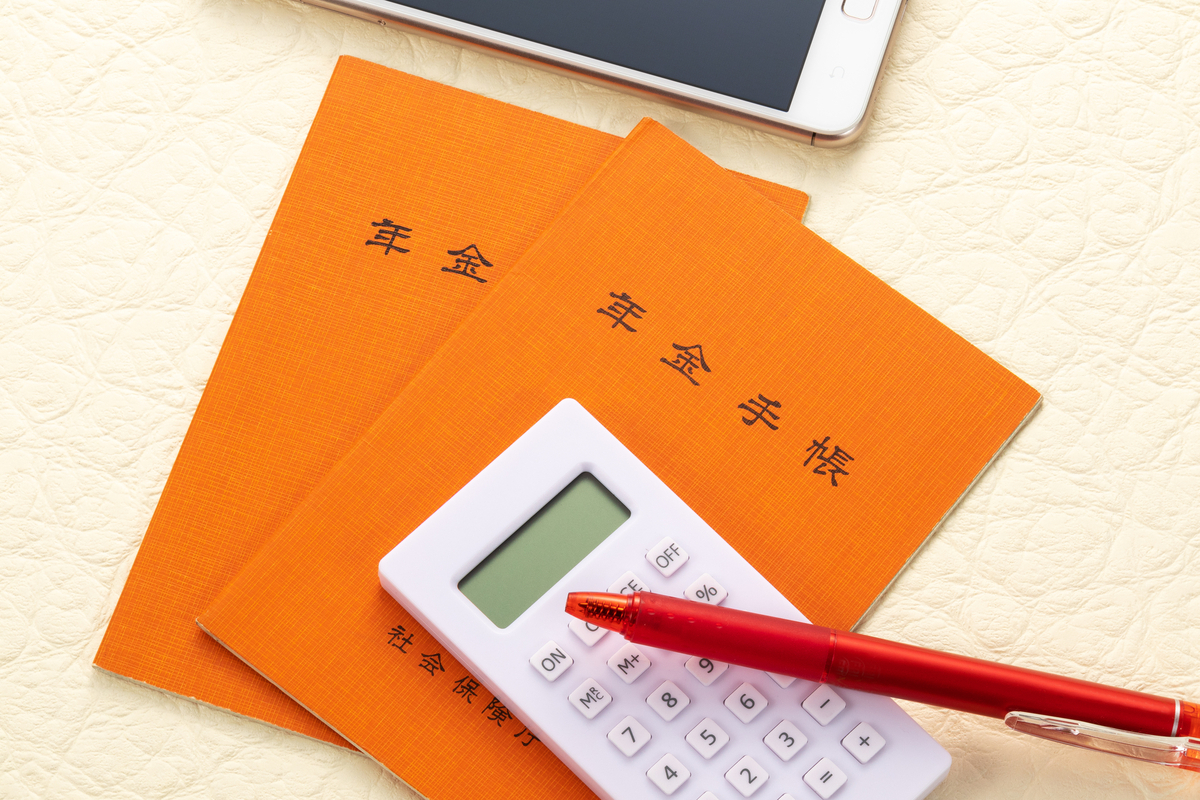
パート従業員の厚生年金加入には、どのような手続きが必要となるのでしょうか?保険料の計算や納付方法など、具体的な知識も重要です。以下では、加入手続きの流れと保険料に関する情報を解説します。
厚生年金加入の具体的な手続き方法
厚生年金加入の手続きは、主に勤務先の企業が行います。従業員は、年金手帳(または基礎年金番号通知書)のコピーを会社に提出することが必要です。
勤務先は提出された書類を基に、加入条件を満たしてから5日以内に管轄の年金事務所へ「被保険者資格取得届」を提出します。
手続き完了後、従業員には「健康保険被保険者証」が交付されます。医療機関での受診時に必要となるため、大切に保管しましょう。
手続きの進捗状況については、会社の担当者に確認することができます。
厚生年金保険料の計算方法と納付
厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率18.3%を乗じて算出され、労使折半により従業員と事業主がそれぞれ9.15%ずつ負担する仕組みです。
標準報酬月額が28万円の場合、従業員負担分は2万5,620円となり、賞与に対しても同様の計算方法が適用されます。
保険料の納付は、事業主が従業員分・事業主負担分を合わせて行うのが通常です。従業員側としては、保険料が毎月の給与から天引きされます。
出典:保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険) |日本年金機構
パート従業員の厚生年金加入に関する疑問解消
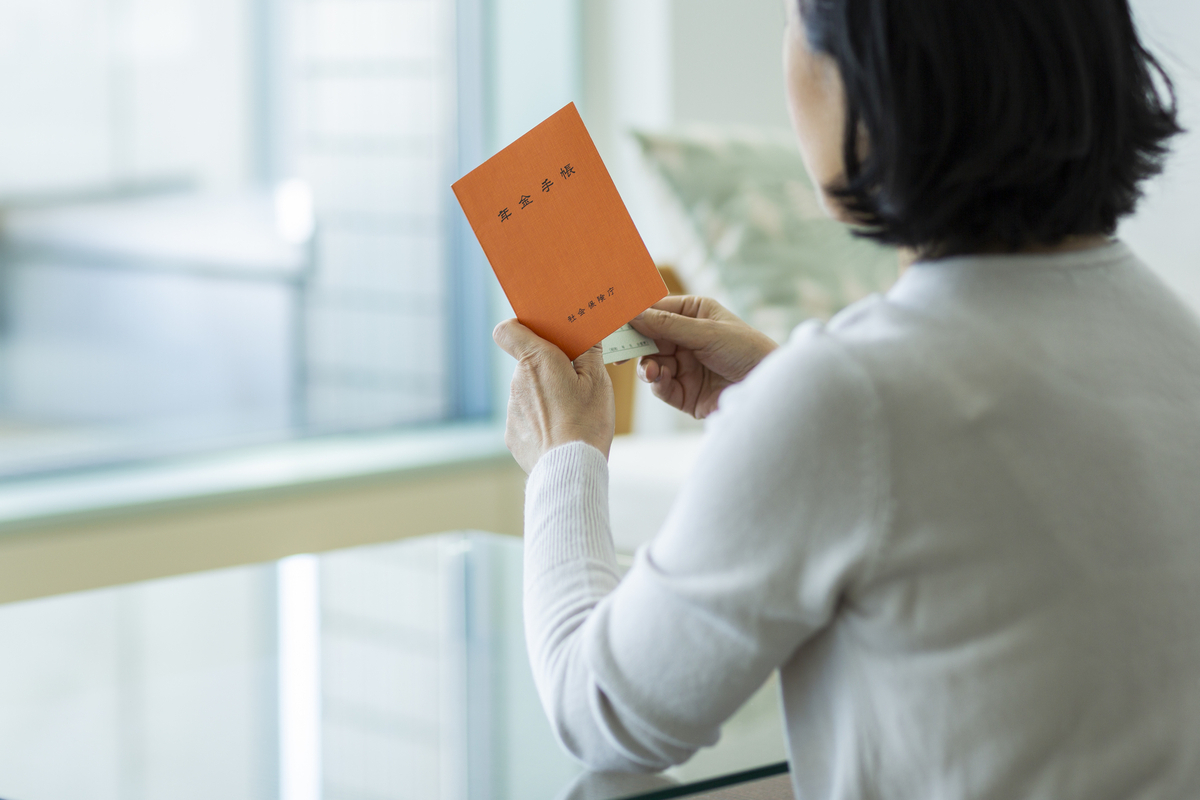
パート従業員の厚生年金加入に関して、保険料負担や他制度との関係について不安を感じている人もいるでしょう。退職金や雇用保険など、制度間の関連性を理解することも欠かせません。最後に、よくある疑問と回答をまとめました。
厚生年金と国民年金は併用できる?
日本の公的年金制度は、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2階建て構造で成り立っています。同じ支給事由の場合は、基礎年金に厚生年金が上乗せされる形で受給できます。例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に受け取ることが可能です。
老齢給付・障害給付・遺族給付など支給事由が異なる場合は、いずれかを選択しなければなりません。ただし、65歳以上の場合に限り、特例的に複数の年金を受給できるケースもあるようです。
また、iDeCoなどの私的年金を公的年金に上乗せすることで、より充実した老後の資産形成を実現できるでしょう。
厚生年金に加入すると、国民年金の支払いはどうなるの?
厚生年金への加入により、国民年金の被保険者種別は第1号被保険者から第2号被保険者に自動的に切り替わります。国民年金の保険料は、厚生年金保険料に含まれる形で給与から天引きされるため、個別に納付する必要はありません。
将来の年金受給については、以下のようになります。
- 老齢基礎年金(国民年金)の受給権は継続して確保
- 老齢厚生年金が新たに上乗せされる形で受給可能
配偶者がいる場合、年収130万円未満であれば第3号被保険者となり、保険料の個別納付は不要です。ただし、年収130万円を超えると配偶者も第1号被保険者となり、個別に保険料を納める必要が生じます。
加入手続きは勤務先が一括して行うため、従業員自身による国民年金の手続きは特に必要ありません。
厚生年金加入後の退職金や雇用保険への影響は?
退職金制度がある企業では、厚生年金加入により退職金の算定基準が変更され、多くの場合、支給額が増加する傾向にあります。
雇用保険は、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用見込みがあれば、厚生年金加入の有無にかかわらず対象となります。
雇用保険の失業手当の受給には待機期間があり、自己都合退職の場合は原則2カ月、会社都合退職の場合は7日間です。なお、2025年4月からは、自己都合退職でも待機期間が原則1カ月、教育訓練を自ら行った場合には待機期間が解除される予定です。
出典:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について|厚生労働省
まとめ

パート従業員の厚生年金加入は、社会保険制度の適用拡大による重要な制度変更です。加入条件は、労働時間と賃金に基づいており、106万円や130万円の収入制限にも注意しましょう。
年金受給額の増加や障害年金の受給資格取得などのメリットがある一方で、手取り額減少や保険料負担の増加といったデメリットもあります。将来設計に合わせて、メリット・デメリットを慎重に検討することが大切です。
