法医学者は、司法解剖を通じて死因を究明する専門家です。ドラマなどでは、事件を解決に導くキーパーソンとして描かれることがありますが、実際はどうなのでしょうか?役割や業務内容、目指す道のりを解説します。検視官や監察医との違いも、確認しましょう。
法医学者とはどのような職種?

法医学者は、警察や捜査機関などから依頼を受け、死因究明に当たる職種です。日常生活で接する機会がほとんどないことから、仕事内容や働き方を知らない人も多いのではないでしょうか?
※本記事では、法医学者を「法医学医」と同一の職種として解説します。
法医学のプロフェッショナル
法医学者とは、法医学を専門とする者のことです。法律に関わる問題に医学的な解明・助言が必要となった際、解剖・薬毒物検査・親子鑑定などの手法を通じて、公正な医学的判断を下します。
例えば、事件性が疑われる変死体が発見された場合、警察は法医学者に司法解剖を依頼します。解剖で死因や死亡状況などが分かれば、事件解決の糸口が見つかるかもしれません。
実務では死体解剖を伴うため、基本的には医師免許のほか死体解剖資格などが必要です。医師ではありますが、けが・病気の治療は行わず、監察医務院・病院・大学の法医学教室などに勤務して、解剖や検査などを行うのが一般的です。
社会の複雑化と高齢化で需要は増加
死体を解剖する法医学者に対し、患者の診察・治療を行う医師を「臨床医」と呼びます。臨床医と比べ、法医学者の数は圧倒的に少ないものの、需要がないわけではありません。
超高齢社会に突入した日本では、高齢者の孤独死が増加傾向にあります。身元不明・死因不明の死体は、法医学者による鑑定が必要なため、社会における需要は増えているといえるでしょう。
虐待・DVが疑われる人の外傷を診るのも、法医学者の仕事です。被害者が暴行を隠す、または加害者が暴行を認めないケースも多く、公正な医学的判断が求められます。
近年は、児童相談所と法医学者が連携する重要性が認識されており、社会の複雑化に伴って活躍のフィールドは増えると考えられます。
法医学の基礎知識

法医学とは文字通り、法学と医学の両方を扱う分野です。法医学者には、医師としての資質はもちろん、法学的な知識・思考も求められます。法医学の基礎知識について見ていきましょう。
法医学の定義と目的
日本法医学会では、法医学の目的を以下のように定めています。
法医学とは医学的解明助言を必要とする法律上の案件、事項について、科学的で公正な医学的判断を下すことによって、個人の基本的人権の擁護、社会の安全、福祉の維持に寄与することを目的とする医学である。
法医学は、死因の究明や外傷を負った経緯を、医学的に判断する学問です。明治時代にドイツから導入された当初は、「裁判医学」と呼ばれていました。
医学的・科学的な知見は、裁判官が適正な判決を下すのに役立ちます。法医学者による死体解剖は、死者の声を聞き、その人権を守ることでもあります。
虐待が疑われる児童がいた場合、臨床医は診察・治療をしますが、法医学者は治療には携わらないのが基本です。「何が原因で生じた傷なのか」を調べ、鑑定書や証明書を作成します。
主な鑑定の対象
法医学者の主な実務には、以下が挙げられます。
- 死因の診断
- 死後経過時間の推定
- 身元不明死体の個人識別
- 親子鑑定
- DNA鑑定
鑑定の対象は、生体・死体・物体・現場・記録と多岐にわたりますが、メインとなるのは死体です。
医師に病死と判断された内因死以外の死体は、「異状死体」と呼ばれます。異状死体の可能性がある場合、まずは警察による検視が行われます。他殺や自殺、交通事故など、何らかの事件性が疑われれば、法医学者が司法解剖で死因を究明する流れです。
法医学者になるには?
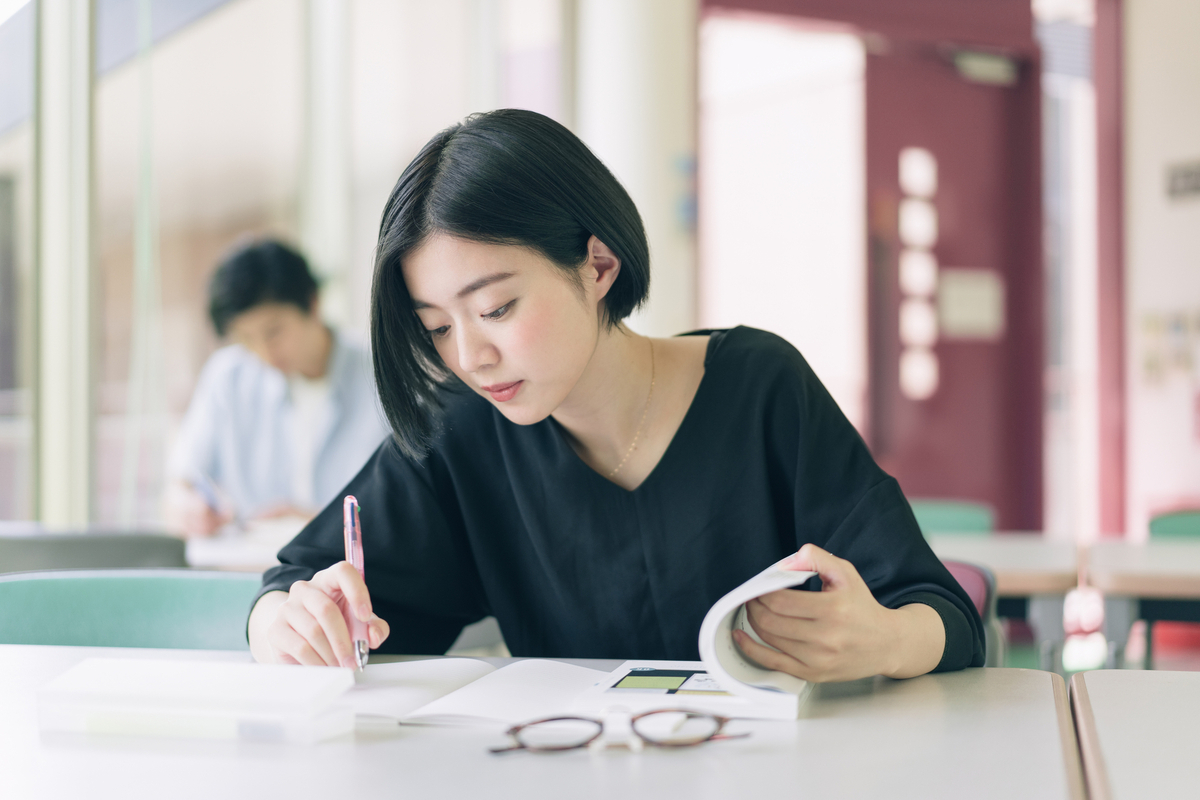
法医学者になるための道のりは長く、医師免許を取得して初めてスタートラインに立てます。これから目指す人は、長い時間がかかることを覚悟した上で、計画的に勉強を進めていく必要があります。
医科大学を卒業して医師免許を取得する
医科大学や大学の医学部を卒業し、医師免許を取得するのが最初のステップです。医師免許を取得するには、医師国家試験に合格しなければなりません。
受験資格があるのは、「大学で医学の正規の課程を修めて卒業した者」や「医師国家試験予備試験に合格し、1年以上の診療および公衆衛生に関する実地修練を経た者」などです。
法医学者は患者の治療をしませんが、臨床医学の知識は不可欠です。医師免許の取得後に2年間の初期臨床研修(卒後臨床研修)を受け、医師としての基礎を身に付けます。
大学院で法医学の知識を深める
臨床研修の後は、法医学に関する専門知識を身に付けるために、大学院に進学するのが一般的です。大学院では、法医学の知識を習得しながら「死体解剖資格」を取得し、法医解剖の経験を積みます。
死体解剖資格は、「医学・歯学に関する大学において一定の解剖経験を有する医師」「歯科医師」「大学の専任講師」などが取得できる資格です。申請手続きには、解剖経験証明書や医師免許証の写しのほか、指導医の推薦状が必要です。
経験を積んで法医認定医を目指す
死体解剖資格を取得した後は、経験を積みながら研究論文などを提出します。大学院修了後は、大学医学部に属する法医学教室や監察医務院に就職し、法医学者としてのキャリアをスタートさせる人が多いでしょう。
一人前の法医学者として認められるために、ほとんどの人は「法医認定医」の資格取得を目指します。法医認定医とは、専門領域における医師の水準の維持・向上を目的として、日本法医学会が2002年に設置した制度です。
認定を受ける者は、4年間の法医学の研修を経た後、運営委員会による資格審査および認定試験に合格しなければなりません。
法医学者に求められるもの

法医学者には、法医学の高い専門知識と技術が必要です。そのほかに、どのような資質・スキルが求められるのでしょうか?
真実を追い求める探究心
法医学者の仕事は、死体解剖や検査を通じて、法的判断の根拠となる医学的・科学的な事実を提供することです。声なき死者の代弁者としての役割があるため、真実をとことん追求する探究心・熱意が欠かせません。
ドラマなどでは、事件を解決に導く法医学者の活躍が描かれますが、実際はそれほど華やかな世界ではないようです。
解剖や検査は長時間にわたる上、時間をかけても死因究明に至らないケースもあります。判断を誤れば、犯人を逃したり、えん罪を生んだりする恐れもあるでしょう。
知力・体力・精神力が備わった者でなければ、現場で活躍し続けるのは難しいかもしれません。
人としての高い倫理観
法医学者の使命の1つは、法医学を通じて死者の人権を守ることです。社会への影響が強く、他者の人生や生活、安全に大きく関わる職種であるがゆえに、高い倫理観が求められます。
倫理観とは、人として守り行うべき道についての考え方を指します。倫理観が欠如すれば、「業務で知り得た情報を他人に話す」「自らが接した事例をSNSに書き込む」といった行為につながる可能性があるでしょう。
法医学者は、死者を含めた個人や遺族に配慮し、ルール・道徳をしっかり守って業務を遂行しなければなりません。
法医学者と関連性のある職種

法医学者と混同されやすい職種に、「検視官」や「監察医」があります。どちらも人の死に関わりますが、必要な資格や業務内容は大きく異なります。
検視官
検視官は、警察官の役職の1つです。病院以外で人が亡くなった場合、最初に検視官が検視をし、事件性の有無や死因を調べます。医師免許はなく、死体解剖を行う権限もありません。
事件性がない場合は、検視官が死体検案書を作成して完了となりますが、死因の特定ができなかったり事件性が疑われたりする場合は、解剖による検査へと進みます。
検視官の役職に就くには、「階級」と「刑事部門での捜査経験」の2つの条件をクリアする必要があります。やむを得ないケースを除いては、警察大学で法医専門研究科を修了した「警部」が任用される決まりです。
出典:検視官等の体制整備及び適正な死体取扱業務の推進について
監察医
事件性はないものの、検視で死因が特定できない場合は、監察医による「行政解剖」が行われます。行政解剖の目的は、公衆衛生を向上させることであり、犯罪捜査には関わりません。
監察医制度は、東京23区や大阪などの限られた地域で実施されています。監察医になるには、医師免許と死体解剖資格を取得した後、監察医務院に就職するのが一般的です。
行政解剖に対し、事件性が疑われる場合の解剖を「司法解剖」と呼びます。司法解剖は、大学の法医学教室などに在籍する法医学者が行います。
法医学者は社会への貢献度が高い仕事

法医学者は、死体解剖や検査を通じて、法的根拠となる医学的・科学的な結果を提供します。事件捜査はもちろん、災害や孤独死による身元調査にも協力しており、社会への貢献度は高いといえるでしょう。
法医学者として活躍するには、医師免許や死体解剖資格のほかに、法医認定医の資格が必要です。長く険しい道のりですが、その分やりがいは大きいといえます。高齢化に伴う社会のニーズも増えており、今後さらに注目が集まるでしょう。
