新入社員として企業に入社し、初任給が意外と低くて驚いた、という人もいるのではないでしょうか?初任給がどのくらいかを把握しておけば、一人暮らしの必要資金や貯金ができるかどうか考えやすくなるでしょう。初任給の現状や仕組み、ケース別の平均を紹介します。
この記事のポイント
- 初任給はいくら受け取れる?
- 給与は基本給と手当で構成され、税金(所得税と住民税)や社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)が差し引かれた金額が手取りとなります。入社1カ月目は所得税と雇用保険料のみが引かれる企業が一般的です。
- 一人暮らしや貯金はできる?
- 一人暮らしに必要な1カ月の生活費は約15万円とされています。一人暮らしに加え、貯金もするとなると額面換算で初任給は約20万円以上は必要だといえます。
- 初年度のボーナスは受け取れる?
- 一般的に、ボーナスの支給額は査定期間の評価に大きく影響されます。ボーナスが年2回支給される場合、それぞれの査定期間は半年間になるのが基本となるため、4月入社の新入社員の場合、規定通りのボーナスをもらえるのは冬からとなることが一般的です。
初任給はいくら受け取れる?
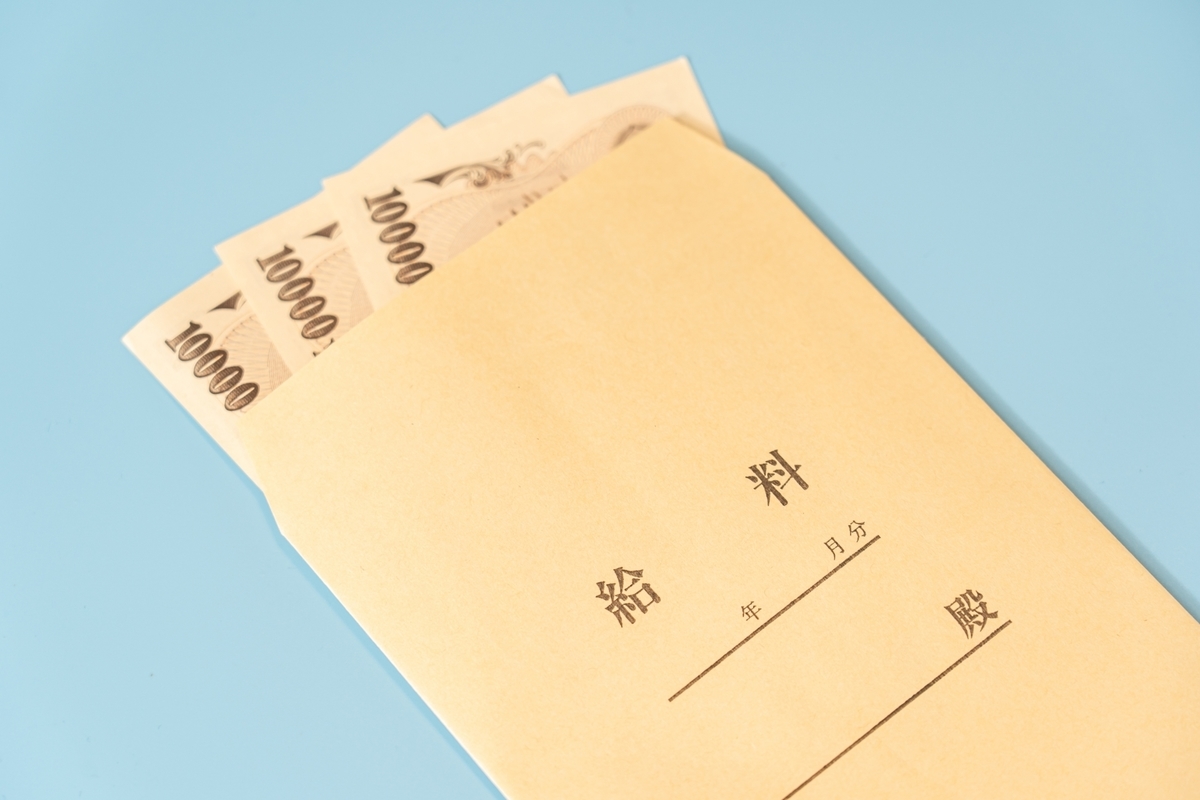
初任給の具体的なデータを見る前に、まずは給与の構成や手取りについて理解を深めておきましょう。1年目から一人暮らしや貯金ができるものなのかも解説します。
給与の構成
初任給とは、会社に入って最初にもらう給与のことです。給与は基本給と手当で構成されており、求人票に『基本給18万円』と記載されている場合、基本給に諸手当を足した金額が毎月の給与額になります。
基本給とは、能力・年齢・勤続年数などをもとに決められた、給与のベースとなるものです。手当に該当するものには、住宅手当・残業手当・通勤手当・扶養手当などが挙げられます。
初任給は基本給+諸手当の金額となるため、基本給が同じ金額でも初任給が同じ金額になるとは限りません。諸手当の種類や金額はその人の環境や会社の制度によって大きく異なるためです。
1カ月目の総支給額と手取り
給与はあくまでも会社が支給する総額であり、給与の全額を手取りとしてもらえるわけではありません。通常は給与から税金と社会保険料が天引きされます。
給与から差し引かれる税金は所得税と住民税、社会保険料は健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料です。このうち健康保険料と厚生年金保険料は、大半の会社で2カ月目から天引きされます。
また、住民税は前年度の所得をもとに課税されるものであり、前年度に一定以上の所得がなければ発生しません。前年度に一定の所得があり特別徴収を希望する場合は、6月の給与から天引きされることになります。
つまり、基本的には1カ月目の給与では、所得税と雇用保険料が天引きされた額が手取りとなるのです。
賃金計算期間を確認
1カ月目の総支給額と手取りを考える際は、賃金計算期間を確認しましょう。賃金計算期間とは、『いつからいつまで働いた分を毎月の給与とするか』を示す期間のことです。
賃金計算期間が『15日締め』となっている場合、毎月16日からその翌月の15日までに働いた分が月の給与となります。4月入社なら4月1日から計算することになるため、初任給は約半月分しかもらえません。初任給は1カ月分もらえない可能性があります。
就業規則や雇用契約書の給与規定を確認すれば、会社の賃金計算期間がどのようになっているのかが分かります。給与規定を見る際は、締め日だけでなく支払日もチェックしておきましょう。
2カ月目以降の総支給額と手取り
先にも述べたように、入社1カ月目にもらえる初任給では、基本的に所得税と雇用保険料が天引きされています。2カ月目以降は、さらに健康保険料と厚生年金保険料も差し引かれるため、手取り額はより少なくなるでしょう。
前年度に一定の所得がなかった場合は、2年目から住民税が毎月の給与から差し引かれるようになります。税金と社会保険料がすべて引かれる場合の手取りは、総支給額の約80%が目安です。
例えば2年目の給与が20万円の場合、手取りの目安は20万円×約80%=約16万円となります。税金と保険料の金額は扶養家族の有無により変わるため、実際には総支給額の約75~85%が手取りになるでしょう。
初任給がいくらなら一人暮らしや貯金はできる?
一人暮らしや貯金をするには、初任給がいくらくらいあれば可能なのでしょうか?総務省の家計調査によると、一人暮らしに必要な1カ月の生活費は約15万円とされています。手取り16万円とするには、額面換算すると初任給は約20万円は必要だということになるのです。
初任給20万円の場合、一人暮らしの家賃の目安は手取りの1/4から1/3が相場と考えると16万円×1/4=4万円からとなります。
また貯金に関しては、金融広報中央委員会が公表している資料を見ると、20代の貯金額の平均値は179万円、中央値は20万円となっています。
平均値より中央値のほうが、より現実に即したデータと捉えられるため、実際には多くの20代が20万円程度の貯金しかできていないことが分かるでしょう。
一人暮らしに加え、貯金もするとなると初任給20万円では心許ないかもしれません。
参考:
統計局ホームページ/家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)
「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和3年)」|金融広報中央委員会
初任給は上がっている?

初任給は年々上がってきているものなのでしょうか。近年における初任給の実態と、企業が初任給を決める際に重視している要素を解説します。
初任給は上昇傾向
少子高齢化、団塊の世代の定年退職などの影響により、企業では若年層の人材が不足しているため、近年の初任給は上昇傾向にあります。厚生労働省の学歴別調査結果を見ると、高卒や高専・短大卒の初任給は、2019年までの4年間で、高卒が約4.0%、高専・短大卒は約4.7%の上昇率で微増でした。
「前年の初任給から引き上げた」企業の割合は、2021年が29.9%だったところ、2022年は41.0%と上昇しており、引き上げの理由も「人材確保のため」が最多となっています。
参考:
令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給|厚生労働省
「2022年度 決定初任給調査」| 産労総合研究所
初任給はどのように決められるのか
日本経済団体連合会の調査では、初任給決定にあたり最も考慮した判断要因を各企業に聞いています。
割合が最も多かった判断要因は『世間相場』です。以下、『在籍者とのバランスや新卒者の職務価値』『人材を確保する観点』『賃金交渉の結果による配分』と続きます。
競合他社より自社の初任給を下げてしまうと、優秀な人材が他社に流れてしまうでしょう。少なくとも給与面で自社の魅力を下げないよう、初任給決定の判断材料として世間相場が重視されているのです。
なお、かつて初任給の世間相場は厚生労働省のサイトを見れば把握できていましたが、2019年の調査をもって厚生労働省による調査は終了しており、2021年までは経済団体連合会、2022年からは産労総合研究所により調査が行われています。
参考:2021年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要 | 日本経済団体連合会
初任給のデータを見てみよう

国が公表する各種資料から初任給のデータが分かります。学歴別・男女別・産業別・企業規模別の平均や地方公務員の初任給を見ていきましょう。
学歴、男女別の平均初任給
学歴別や男女別の平均初任給は、厚生労働省の調査結果が参考になります。2019年のデータは以下の通りです。
| 高卒 | 高専・短大卒 | 大学卒 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 16万8900円 | 18万4700円 | 21万2800円 |
| 女性 | 16万4600円 | 18万3400円 | 20万6900円 |
| 男女計 | 16万7400円 | 18万3900円 | 21万200円 |
学歴が高くなるほど初任給も高くなっていることが分かります。ただし、最近では学歴別初任給制を廃止した企業もあります。学歴にかかわらず初任給を一律とし、さらに保有スキルなどにより初任給を増額しているのです。
また、女性より男性のほうが初任給が高いことも特徴でしょう。
厚生労働省の調査によると、2014年採用における総合職の採用比率は男性約8割:女性約2割、一般職は男性約2割:女性約8割です。総合職の初任給は一般職より高い傾向があります。
参考:令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給|厚生労働省
参考:平成26年度コース別雇用管理制度の実施・指導状況(確報版)を公表します |報道発表資料|厚生労働省
産業別の平均初任給
次に、産業別の初任給について見ていきましょう。自分の希望する産業の初任給平均を知ることで、今後のキャリアプランの参考になるでしょう。厚生労働省の資料から分かる2019年の産業別平均初任給を紹介します。
| 高卒 | 高専・短大卒 | |
|---|---|---|
| 建設業 | 17万6100円 | 18万9400円 |
| 製造業 | 16万6300円 | 18万3200円 |
| 情報通信業 | 17万1000円 | 19万200円 |
| 運輸業、郵便業 | 16万6800円 | 17万6600円 |
| 卸売業、小売業 | 16万8400円 | 18万500円 |
| 金融業、保険業 | 15万8500円 | 17万2300円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 16万7400円 | 18万円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 16万7800円 | 17万6500円 |
| 教育、学習支援業 | 16万8100円 | 18万3100円 |
| 医療、福祉サービス業 | 16万5400円 | 18万9400円 |
参考:令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:3 主な産業別にみた初任給|厚生労働省
企業規模別の平均初任給
初任給は企業規模が大きくなるほど高くなる傾向があります。厚生労働省の調査結果によると、2019年の企業規模別平均初任給は以下の通りです。
| 高卒 | 高専・短大卒 | 大学卒 | |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 16万8500円 | 18万5600円 | 21万3100円 |
| 中企業 | 16万6100円 | 18万3600円 | 20万8600円 |
| 小企業 | 16万8600円 | 18万3200円 | 20万3900円 |
分類の仕方は、常用労働者1000人以上が大企業、100~999人が中企業、10~99人が小企業です。ブランド力により採用コストを抑えられることや売上が安定しやすいことが、大企業の初任給が高くなる主な理由として考えられます。
参考:令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:2 企業規模別にみた初任給|厚生労働省
地方公務員の初任給
地方公務員の初任給も確認しておきましょう。総務省が公表しているデータを見ると、2020年における地方公務員の地域別初任給が分かります。
例えば、千葉市における一般行政職の初任給は、高卒が15万4900円、短大卒が16万8900円です。どちらも採用方法による初任給の差はありません。
地方公務員の採用方法には『試験』と『選考』の2種類があり、どの方法を用いているかは地域により異なります。採用方法の違いで初任給に差が生じる場合、基本的には試験で採用されるほうが初任給は高めです。
なお、令和2年以降は統計の調査項目が変わったため、項目がより細かい令和元年度の統計を参考として紹介しています。最新の情報については、産労総合研究所の調査をご確認ください。
参考:2022年度 決定初任給調査 | 決定初任給調査 | 賃金制度・春闘 | 産労総合研究所
地域による差も

初任給は地域によっても差があります。初任給の高い地域や低い地域を紹介し、地域差が生まれる理由についても解説します。
人が集まる地域の初任給が高い
人が集まる地域は初任給が高めです。関東では東京・神奈川・千葉・埼玉、関西なら大阪が該当します。逆に、沖縄・宮崎・長崎・秋田・青森は初任給が低めです。
厚生労働省の資料によると、2019年における高卒の初任給は東京が最も高く17万8100円、次いで大阪が17万6100円となっています。
一方、最も初任給が低いのは沖縄の14万5200円、次に低いのが秋田の14万9900円です。最も高い東京と最も低い沖縄では、3万円以上の差が生じています。
参考:令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況 付表3 都道府県、性、学歴別初任給及び都道府県間格差|厚生労働省
地方の初任給と差がある理由
地域により初任給に差が生じているのは、地域ごとの生活費を考慮して公平性を保つためです。初任給が高い地域は、物価や家賃なども高くなっています。
地方に住んでいる人が都市部の初任給を見ると、都市部で就職したいと思うこともあるでしょう。実際に、初任給の低い地域から高い地域への人口流入のリスクも指摘されています。
ただし、初任給が高い地域は生活費の負担も増すため、都市部に引っ越したからといって生活が楽になるとは限りません。初任給の地域差にはそれなりに理由があることを覚えておきましょう。
初年度のボーナスは受け取れる?

新入社員にとっては、初任給と併せてボーナスに関することも気になるでしょう。ボーナスは初年度からもらえるのか、もらえるとしたらいつから、いくらくらいなのかを解説します。
仕事の成果や査定期間による
初年度から規定通りのボーナスを受け取れることはほとんどないでしょう。仕事の成果を出せていないことや査定期間が足りていないことが主な理由です。
一般的に、ボーナスの支給額は査定期間の評価に大きく影響されます。ボーナスが年2回支給される場合、それぞれの査定期間は半年間になるのが基本です。
例えば、7月のボーナスの査定期間が6月までの半年間なら、4月入社の場合、初年度は6月まで半年分働いていないことになります。7月のボーナスをもらえたとしても、規定通りには支給されないでしょう。
多くの場合、初めてのボーナスは冬
4月入社の新入社員の場合、基本的には規定通りのボーナスをもらえるのは冬からでしょう。
ボーナスが年2回で月給4カ月分となっているなら、冬のボーナスでもらえるのは月給2カ月分になると考えられます。
初年度ということが考慮されれば、2カ月分より少ない金額になる可能性もあります。初年度のボーナスは高望みせずに考えておくのが無難です。
求人を見るときのポイント

就職活動時に求人を見るときには、初任給以外の要素にも注目しましょう。求人を見る際に意識したいポイントを紹介します。
残業代の取り扱い
求人を見るときには、残業代の取り扱いがどのようになっているのか確認しましょう。固定残業代が給与に含まれている場合、一定時間までは残業代がプラスされません。
固定残業代とは、一定時間の残業が毎月発生することを見越した上で、あらかじめ給与に含める残業代です。例えば、20時間分の固定残業代がある会社では、残業が20時間を超えなければ給与以外に残業代をもらえないことになります。
初任給だけで就職先を探してしまうと、残業しても残業代が発生しない会社を選びかねません。他社と比べて初任給が高い場合は、固定残業代が含まれていないかチェックしましょう。
各種手当
各種手当が支給されている会社なら、生活レベルを高められる可能性があります。求人を見る際は、どのような手当が支給されるのかも確認しましょう。
初年度から一人暮らしをしたい場合は、住宅手当をもらえると生活の負担が大きく軽減されるでしょう。家賃の一部だけでなく、水道光熱費を補助してもらえるケースもあります。
通勤手当や家族手当も、状況によっては生活レベルを大きく変えられる手当です。これらの手当は給与とは別にもらえるため、支給条件を満たしているなら大いに活用できます。
評価方法
入社後に努力して収入を大きく伸ばしたいなら、就職先の評価方法もチェックしておきましょう。インセンティブを導入している会社を選べば、能力や実績に応じた給与をもらえます。
高卒でも採用されやすい成果主義の職種が不動産や保険の営業です。未経験でも採用される可能性がある上、成果を出し続ければ収入を大きく伸ばせるでしょう。
ただし、成果主義の仕事は失敗が許されないというプレッシャーも感じやすくなります。実力を出せずに降格してしまうリスクを回避したいのなら、安定した収入を得られる会社を選ぶのが無難です。
給与の仕組みを知って今後に生かそう

初任給の平均は、学歴・性別・産業・企業規模・地域などにより異なります。高卒や専門卒の平均初任給は、大卒・院卒より低くなるのが一般的です。
初任給が平均より低かった場合でも、今後の年収は社内でのキャリアアップや実力次第で変わる可能性は十分あります。
毎月の手取り額だけでなく、残業代や手当などに関する給与の仕組みもしっかりと理解しておけば、今後、転職活動をする際にも役に立つことでしょう。

労務トラブルを未然に防ぐ社会保険労務士・行政書士。行政書士法人グローアップ代表、社会保険労務士法人トップアンドコア役員。大学卒業後、日本マクドナルドに入社。幅広い年齢層と共に働くことで、法律や制度だけではない労務管理・組織運営に興味を持ち、弁護士事務所等で経験を積む。自身も喫茶店を経営した経験から、労務トラブル予防の労務相談を得意とする。
All Aboutプロフィールページ
公式サイト
