医療事務の仕事に興味を持っているけれど、ネガティブな経験者の声を目にして応募を迷っているという人もいるでしょう。やめとけといわれる理由や医療事務を取り巻く現状を理解し、自分に適しているかどうかを判断しましょう。
この記事のポイント
- 「医療事務はやめとけ」といわれる理由
- 業務の幅が広く、さまざまなスキルが要求される一方で、平均給与が低い傾向にあります。
- 医療事務のやりがいやメリット
- 医療サービスの需要は少子高齢化社会で伸びていくと予想されており、将来性は安定しています。未経験でも始められ、柔軟な働き方ができる点も魅力です。
- 医療事務に向いている人の特徴
- 積極的なコミュニケーションができる、パソコンの操作が得意、何があっても落ち着いている人は医療事務に向いています。
「医療事務はやめとけ」といわれる理由は?
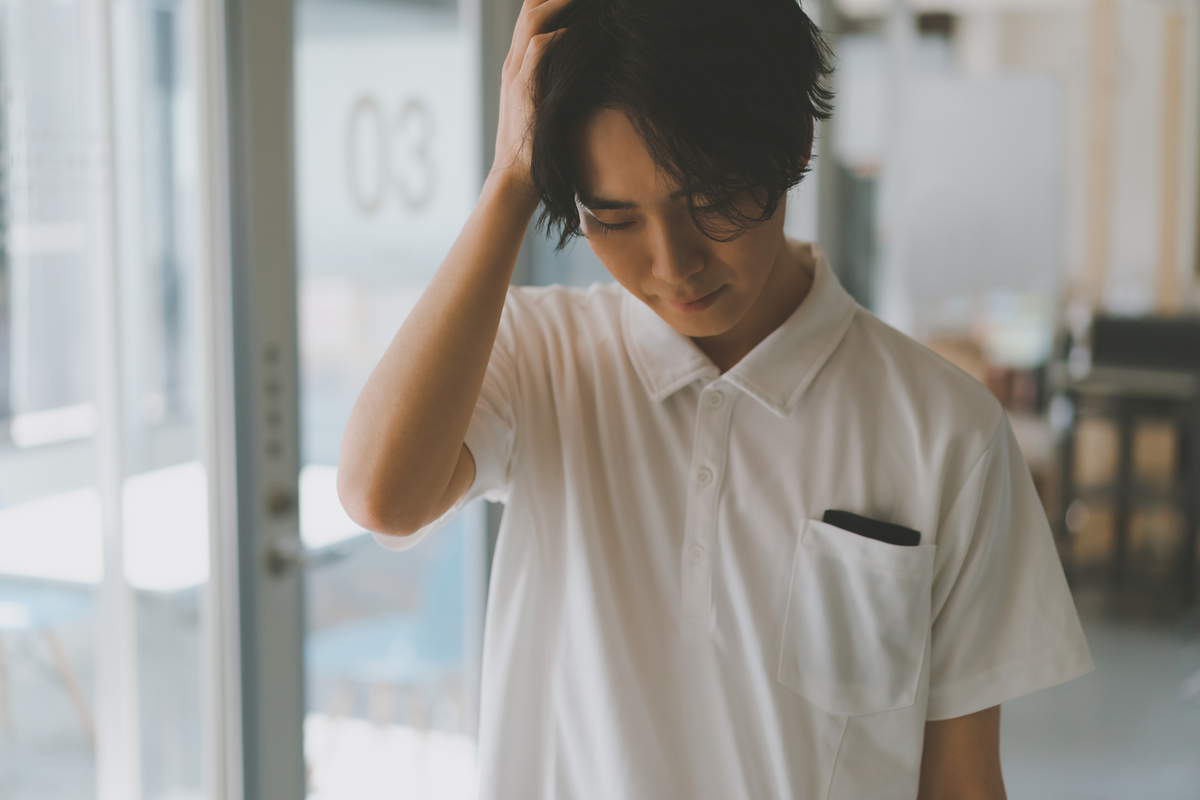
医療事務は、病院やクリニックなどの医療機関で事務作業をする仕事のことを指します。受付や会計など、医療事務の仕事は多岐にわたりますが、経験者から「医療事務はやめとけ」という声も聞かれます。ネガティブな意見を聞くと、医療事務に就くことを不安に思うこともあるでしょう。
では、経験者が医療事務をおすすめできないと思う理由はどのような点にあるのでしょうか。ここでは、主な理由は4つの原因について解説します。原因を理解すれば不安も解消できるでしょう。
仕事が激務・イメージと異なる
医療事務の仕事は、患者対応からカルテの準備や整理、会計、診療報酬の請求など業務の幅広さが特徴です。一般的な事務職とは業務内容が異なるため、採用後のギャップに戸惑うかもしれません。
医療業界以外では耳にしない専門用語も多く、業務をこなせるようになるまでに時間がかかることも多いようです。必要な専門知識を知らなければ、患者や医師とのスムーズなコミュニケーションもできません。
高度な専門知識は不要ですが、患者からの質問や医師と処置内容の確認ができる程度の知識が必要です。分からないからといって曖昧なまま仕事を進めると、認識違いやミスの発生につながってしまうこともあります。
一般事務の中には、机に向かって淡々と仕事をするケースも多く見受けられるため、同じイメージで応募すると、思っていた仕事と違うと感じるケースもあるようです。
ブラックな病院の存在
人手が十分ではない病院では、1人1人にかかる業務負荷が高くなります。感染症流行などにより患者数が増加したときや診療報酬提出時期などは、短時間に多くの作業をこなさなければなりません。
医療事務は基本的に長時間の残業や休日出勤は発生しません。しかし、定時に処理が終わらない場合は、残業をすることもあるでしょう。人手が少ない病院では、サービス残業が常態化しているケースもあるようです。
また、人手不足の問題を抱える病院では業務全体に余裕がなく、それぞれが自分の担当業務で精いっぱいです。そのため、病院によっては質問しても思うような対応を得られず人間関係がギクシャクしてしまうことも見受けられます。
また、ハラスメントが多い環境も人手不足を加速させる要因の1つです。高ストレスの労働環境を放置する病院では、全体のモチベーションも低下してしまうでしょう。
人間関係のストレスが多い
業務範囲が広くシフト制の職場も多いため、スタッフ間の連携も良好でなければなりません。しかし、職場環境の悪さから人間関係に悩みを抱える人もいます。
例えば、他人のミスや間違いに厳しい態度を取る、自己中心的で周囲をサポートする姿勢がない職場もあります。協調性がない職場ではコミュニケーションが少なく、働きにくさを感じるでしょう。
病院の医療事務は他部門へ異動する機会がないため、基本的に同じメンバーで業務を行います。気の合わない人がいても、ストレスを抱えながら働かなくてはなりません。
また、患者や付き添いの家族から理不尽なクレームを受けることもあります。長時間待たされた患者などから不満をぶつけられることに、ストレスを感じる人も多いようです。
業務負担は大きいのに平均年収は低い
スタンバイには、2025年2月1日~2月28日まで掲載された医療事務求人の統計情報があります。正社員の平均年収は304万円、年収中央値は294万円です。
一方、一般事務の統計を見ると正社員の平均年収は337万円、中央値は328万円となっています。2月の医療事務の平均年収は一般事務よりも33万円低く、2024年9月以降も同じ傾向です。
医療事務は、未経験や無資格でもスタートできます。しかし、未経験の場合は対応できる業務範囲が限定されるため、年収は低くなります。
年収を上げるには、経験を積んで業務範囲を広げ、関連する資格を取得する必要があるでしょう。資格を保有することで、資格手当を支給する病院もあります。
医療事務の仕事には向き不向きがある

どのような職業においても向き不向きは存在します。自分の性格や考え方に合わない仕事を続けると、ミスの発生や効率の悪化などにより疲れてしまうでしょう。
ここでは、医療事務の業務内容や向いていない人の特徴を紹介します。医療事務を希望しつつ不安を感じている人は、事前に適性を確認してみるとよいでしょう。
医療事務の業務内容
主な仕事の1つは、来院した患者の受付です。保険証や診察券を受け取り、簡単な病状の確認やカルテの作成を行います。幅広い問い合わせに対応するため、病院の印象に直結する重要な役割です。
診察終了後には、かかった費用を請求するための会計業務を担います。診療内容や検査に応じた正確なデータ入力や計算を行い、支払処理を実行する流れです。
診療報酬明細書(レセプト)の請求は、専門知識と経験が必要な業務です。レセプトは、病院が健康保険組合に医療費を請求するために作成します。病院の収益に関わるため、正確性が重視されます。
円滑に病院運営を進めるためのクラーク業務も欠かせません。来院時の患者や家族の対応、医師や看護師の事務作業サポートなどにも対応します。
医療事務に向いていないケース
医療事務は、限られた時間で効率的に業務をこなす能力が求められます。マニュアル通りに実施する患者情報の管理や費用処理などほとんどの業務は、毎回変わることのない定型業務です。
同じことを毎日何度も繰り返すことが苦手な人にとって、医療事務は苦痛に感じるかもしれません。集中力を維持できないとミスが発生し、病院の運営に悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
また、仕事中は患者や医師、看護師などとのコミュニケーションの連続です。相手のレベルに合わせて会話し、迅速に行動しなければなりません。
多様な性格の相手と毎日接すると疲れてしまう人もいます。その場合、応募は避けた方がよいかもしれません。
「医療事務はやめとけ」とはいい切れない!やりがいやメリット

他業界よりも難しい要素はあるものの、やりがいやメリットもあります。自分のキャリアプランなどを考慮して、ポジティブな面にも目を向けてみましょう。
ここでは、医療事務の3つのメリットを紹介しますので、自分なりのやりがいを探してみましょう。
医療業界は需要も高く将来性がある
就職や転職の際に考慮する要素の1つに、仕事の安定性や将来性があります。医療は他の業界に比べて需要が安定しており、景気に左右されにくい業界です。
高齢化社会の日本では、医療サービスの内容も多様化しています。そのため、医療事務が活躍できる環境は今後も増加するでしょう。
AIの発展や普及が進む中、医療業界でもAI技術を導入して効率化を図る病院も出てきました。しかし、AIは患者に寄り添った対応や、突発的なトラブルに迅速に対応できません。
病院は、事故や病気になった人が心身ともに回復を求める場所です。人間のきめ細かい対応
が完全にAIへ置き換わることはない点も将来性があるといわれるポイントです。
未経験でも働ける
医療事務は、未経験でもキャリアをスタートできます。業務遂行に必須の資格も特にありません。適性と熱意があれば、比較的始めやすい職業といえるでしょう。
もちろん、経験がある人は未経験よりも採用される可能性は高まります。しかし、業界全体で人手が不足しているため、未経験の人にも採用枠を広げているのが実情です。
教育や研修制度をしっかり行っている病院もあります。このような求人に応募すれば、採用後も安心して仕事に就けるでしょう。
また、病院によって、ルールや業務の方法が異なる作業もあります。経験者であっても、新しい環境ではそのルールに従って業務を遂行しなければなりません。
先入観や自分なりのルールを持つ経験者より、既存の考え方にとらわれず行動できる未経験者を採用したいと考える病院もあります。未経験者でも働きやすい環境を見つければ、仕事へのやりがいもアップするでしょう。
働き方を柔軟に選べる
医療事務の働ける環境は全国各地にあるため、働き方を柔軟に選べます。病院やクリニックでの仕事は標準化されているため、地域によって大きく異なることはありません。
結婚や出産、引っ越しなどライフスタイルの変化によって一時的に仕事を離れることもあるでしょう。そのような際でも、経験を生かして再就職できるため、生涯にわたってキャリアアップが可能です。
子育てや介護などでフルタイム勤務ができない場合でも、アルバイトや契約社員などの働き方を選べます。子育てが一段落した段階で、正社員になる人もいます。
配偶者の転勤があっても、転勤先で比較的容易に再就職先を見つけられるでしょう。自分や家族の状況に合わせて勤務できるのは、大きなメリットです。
医療事務に向いている人は?

仕事内容や求められる要素が自分に合っていれば、高いモチベーションを持って生き生きと働けるでしょう。
ここからは、医療事務に向いている人の特徴を解説します。自分の特性と一致しているか確認してみましょう。
パソコン操作や入力作業が得意
患者情報や診療情報など、日常的にデータ入力や確認作業の機会が多くあります。最近では、医療業界もIT化が進み、パソコン上でデータのやりとりをすることが多くなりました。
入力操作をミスなく迅速にできると、それだけ業務が効率的になります。電子カルテやレセプト作成ソフトウェアの操作に慣れれば、毎日の業務を素早くこなせるでしょう。
今後も、予約システムなど新しいシステムの導入や更新が予想されます。パソコンやタブレットなど、さまざまなデバイスやソフトウェアの操作に慣れている人は有利です。
将来、AIを使った自動化システムも普及するでしょう。ITの知識や経験が豊富な人の方が、トラブル発生時の対応や患者へのサポートなどもスムーズに対応できます。
コミュニケーション能力が高い
患者だけでなく、その家族や医師、看護師などさまざまな人とコミュニケーションを図りながら業務を行います。時には患者と医師の間で板挟みになるなど、難しい状況に陥ることもあるでしょう。
円滑な病院運営にとって高いコミュニケーション能力は大きな助けとなります。専門用語を使い分け、相手の立場によってコミュニケーションスタイルを変えるなどの能力が役立ちます。
シフト制の環境で働く場合、情報の引き継ぎも日々発生します。職場内で密接なコミュニケーションが取れなければ、ミスや業務の遅延などを引き起こすきっかけにもなるでしょう。
また、費用の内訳など患者への丁寧な説明が求められることもあります。思いやりを持って丁寧に接することで、クレームの減少や病院の評価向上につながります。
落ち着いていて几帳面
業務で重要な要素は、ミスのない正確な作業です。また、少ない人数で多数の患者に対応するため、無駄のない効率的なタスク処理が求められます。
周囲が慌ただしい環境であっても、惑わされずに落ち着いて業務を遂行しなければなりません。突発的な事象が起きたときに冷静に対処できる能力は、早期の事態収束に役に立つでしょう。
焦って入力を間違えたことに気付かないと、後々大きな問題に発展する可能性もあります。レセプトの内容を間違えれば、病院の収益にも大きく影響します。
また、几帳面であることも重要な要素です。書類をデスクの上に乱雑に置く、元の場所に書類や道具を戻さないなどの行為はミスを引き起こしやすく、全体の効率も悪くなります。
医療事務の仕事に就くには?

自分には適性があり、病院で医療事務として働きたいと思う人もいるでしょう。しかし、知識や経験がないため不安に感じるかもしれません。
ここでは、医療事務の仕事に就く方法を解説します。しっかりと準備すれば、自信を持って応募できます。
資格がなくても挑戦できる仕事
経験や資格を有していなくても、医療事務の仕事に就くことは可能です。採用後に研修などを用意している病院では、スムーズに業務を開始できます。
積極的にコミュニケーションを取り、常に学ぶ姿勢で取り組むと、必要なスキルを早期に吸収できます。また、知らない専門用語も時間をかけずに強化できるでしょう。
未経験の人は、未経験者歓迎と書かれた求人を優先的に選ぶことをおすすめします。記載がない求人にも応募はできますが、経験者の応募があった場合に採用される可能性が低くなります。
いきなりフルタイムで勤務するのが不安という人は、契約社員やアルバイトで応募し、限定的な範囲からのスタートも可能です。経験を積んで自信を付けてから、正社員として働く方法もあります。
資格を取得すると採用率が高まる
関連する資格を保有すれば、一定の知識があると証明できるので採用に有利です。代表的な資格は以下の4つです。
- 医療事務技能審査試験
- 医療情報実務能力検定試験
- 診療報酬請求事務能力認定試験
- 医療事務管理士
医療事務技能審査試験は、診療報酬請求事務技能や窓口業務での患者対応など、実務で必要な知識が広く問われます。合格するとメディカルクラークの称号が与えられます。
医療情報実務能力検定試験は、診療報酬請求事務の担当者に必要な能力があることを証明する資格です。1級を受験するには2級に合格する必要があります。
診療報酬請求事務能力認定試験は、公益財団法人日本医療保険事務協会が実施する試験です。学科試験と実技試験があり、診療報酬請求事務に関する資格の中でも難易度が高くなります。
医療事務管理士は、医療事務全般のスキルを証明する資格です。幅広く医療機関に認知されており、求人応募の際に役立ちます。
出典:医療事務技能審査試験|一般財団法人 日本医療教育財団
出典:医療情報実務能力検定試験|特定非営利活動法人 医療福祉情報実務能力協会
出典:診療報酬請求事務能力認定試験|公益財団法人 日本医療保険事務協会
出典:医療事務管理士|株式会社技能認定振興協会
医療事務でやめとけといわれる求人とは

需要が多いため、医療事務の求人は比較的多くあります。ブラックな職場を避けるために求人票では以下の項目をチェックしましょう。
- 年間休日日数
- 平均勤続年数
休日日数は、心身の健康やワークライフバランスを保つ上で重要な要素です。年間休日日数が記載されていない求人に応募すると、思うように休みが取れず悩むかもしれません。
平均勤続年数が長い職場には、スタッフが働き続けたいと思える環境があります。勤続年数が極端に短い、または記載がない求人には問題があるかもしれません。
医療事務は自分に合った働き方が重要

「医療事務はやめとけ」という声を、真に受ける必要はありません。しかし、長時間労働の慢性化やハラスメント問題を抱えている病院があることも事実です。
そのような環境を避けるため、求人票を注意深くチェックして悪い環境で働くリスクを低減しましょう。医療事務は未経験から応募可能で、地域やライフスタイルに合わせた働き方もできます。
今後も需要は続くことが予想されています。契約社員やアルバイトから徐々に経験を積むこともできるため、まずは国内最大級の仕事・求人情報一括検索サイト「スタンバイ」で求人を検索してみてはいかがでしょうか。
