社会福祉士は福祉系国家資格の1つです。資格の取得は社会福祉関係の仕事に就く上で有利に働く場合が多く、有資格者は給料も高くなる傾向があります。社会福祉士の給料や、社会福祉士の資格を取得するための勉強法・年収アップのコツを紹介します。
この記事のポイント
- 社会福祉士の給料は高い?
- 社会福祉士を含む社会福祉関連の有資格者は、無資格の福祉職員と比較すると給料が高い傾向です。試験の難易度は高めですが、その分有資格者への評価は高いといえます。
- 社会福祉士の資格取得方法
- 社会福祉士の資格を取得するためには、国家試験に合格し登録申請を行う必要があります。国家試験を受ける際の資格は、4大・短大・福祉系の大学によって異なります。ご自身のルートを確認しましょう!
- 社会福祉士として年収を上げるには
- 介護施設や病院などの現場より、地方自治体で働く方が給料は高く安定しています。社会福祉士の資格を生かしつつステップアップしたい人は、公務員試験をパスして、地方自治体での就職を目指すのも1つの手です。
社会福祉士の給料は高い?

社会福祉士の資格を持っている人は、無資格の福祉系職員よりも高い給料を得やすくなります。社会福祉士の給料について確認しましょう。
なお、本来であれば給料は基本給を指し、残業代などの諸手当を含めません。しかし本記事では、諸手当を含めた賃金を「給料」として扱います。
月の給料はおよそ「28万円」
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」(2021年)によると、「企業規模計(10人以上)」に属する「その他の社会福祉専門職業従事者」の「きまって支給する現金給与額」は27万8,300円です。年収に換算すると、403万7,000円となります。
「賃金構造基本統計調査」の「その他の社会福祉専門職業従事者」における「きまって支給する現金給与額」を12倍し、「年間賞与その他特別給与額」を足して算出しました。
ただし注意したいのは、その他の社会福祉専門職業従事者には社会福祉士以外も含まれている点です。後述しますが、社会福祉士は就いている職種によって収入が異なります。実際には、上記の給料よりも多くの額面を得ている人も多いでしょう。
他の介護職よりは給料が高い傾向
社会福祉士を含む社会福祉関連の有資格者は、無資格の福祉職員と比較すると給料が高い傾向です。
2021年の「賃金構造基本統計調査」によると、施設などで介護業務に従事する介護職員(医療・福祉施設等)の年収は、352万8,000円とされます。
「賃金構造基本統計調査」の「介護職員(医療・福祉施設等)」における「きまって支給する現金給与額」を12倍し、「年間賞与その他特別給与額」を足して算出しました。
その他の社会福祉専門業従事者の年収403万7,000円と比較すると、約50万円の開きがあり、社会福祉士資格を含む有資格者の方が、高い給料を得やすいことが分かります。
職場や業務内容によって異なる点もチェック
社会福祉士は国家資格ではあるものの、資格を取得しただけで高い給料を得られるわけではありません。安定して高い収入を得るためには、就業先を選ぶ必要があります。
社会福祉士資格を取得した場合、主に以下の施設や団体で働くことが可能です。
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 障害者支援施設
- 児童相談所
- 病院
- 社会福祉協議会
- 保護観察所・地方更生保護委員会
- 都道府県庁
どちらかというと介護施設や病院などの現場より、地方自治体で働く方が給料は高く安定しています。社会福祉士の資格を生かしつつステップアップしたい人は、公務員試験をパスして、地方自治体での就職を目指すのも1つの手です。
社会福祉士の資格の特徴
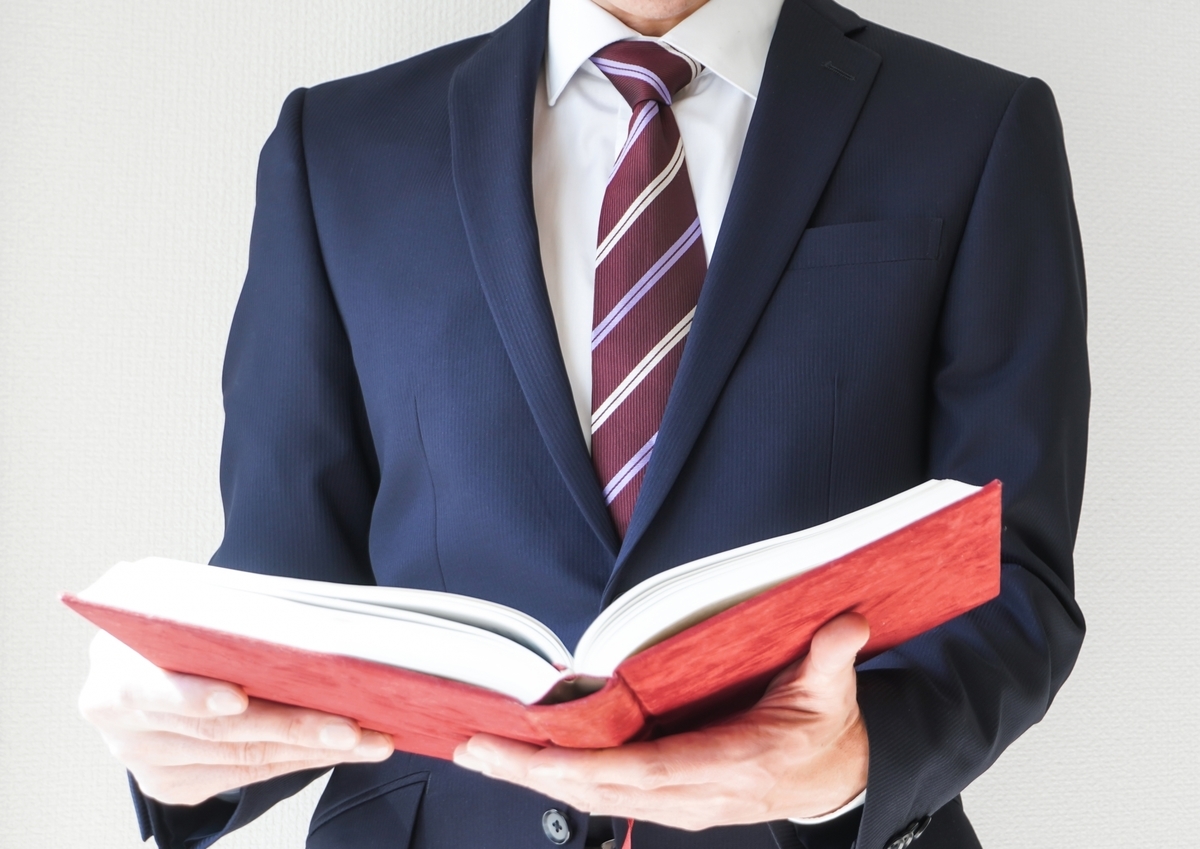
すでに超高齢化社会に突入している日本において、社会福祉士のニーズはますます高まっていくと考えられます。資格取得を考えている人は、社会福祉士資格の特徴や資格取得の難易度について確認しておきましょう。
相談援助に関する専門知識を担保
社会福祉士は、社会福祉分野における相談援助の専門家です。「社会福祉士及び介護福祉士法」によって定められており、介護福祉士・精神保健福祉士と並ぶ、数少ない福祉系国家資格の1つに数えられます。
社会福祉士が相談援助の対象とするのは、高齢者・身体障害者・生活困窮者・子ども・シングルマザーなど、社会的に弱い立場に置かれた人々です。活躍の場は高齢者施設から医療機関・児童施設まで幅広く、さまざまな分野の相談援助業務をカバーします。
なお社会福祉士と名乗れるのは、国家試験をクリアして社会福祉士登録を行った人のみです。資格の希少性・信頼性から、有資格者は社会福祉分野での就業・昇進において有利になるケースが多々あります。
福祉系資格の中では合格率が低い難関資格
2022年に実施された第34回社会福祉士国家試験の合格率は、31.1%でした。合格率の低さを見れば、社会福祉士国家試験の難易度が高いことが分かるでしょう。
公益財団法人社会福祉振興・試験センターによると、合格するためには以下の2項目をクリアする必要があります。
- 問題の総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正した点数以上を得点した人
- 1の条件を満たした人で、「人体の構造と機能及び疾病」をはじめとする18科目群すべてにおいて得点した人(社会福祉士及び介護福祉士法の規定により試験科目の一部免除を受けた人は7科目群)
第34回社会福祉士国家試験の合格基準点は150点満点中105点と高く、合格するには総得点の70%を取得する必要がありました。確実に合格を手にするためには、社会福祉に関する広範囲の知識習得が必要です。
ただし厚生労働省は社会福祉士養成課程でのカリキュラム改定に伴い、2024年より試験問題にも新カリキュラムを取り入れるとしています。2024年以降に社会福祉士国家試験を受験する場合は、新カリキュラムへの準備も進めましょう。
参考:
第34回社会福祉士国家試験合格発表|厚生労働省
[社会福祉士国家試験]合格基準:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
社会福祉士国家試験の今後の在り方について|厚生労働省
社会福祉士の資格取得方法

社会福祉士の資格を取得するためには、国家試験に合格し登録申請を行う必要があります。社会福祉士になるための流れを具体的に見ていきましょう。
受験資格を確認する
社会福祉士の国家試験を受けるには、受験資格が必要です。自分がどのルートに該当するのか確認しましょう。
福祉系短期大学を修了した人は、基礎科目履修後、1年または2年の相談援助実務を行い、短期養成施設などで6カ月以上の学習が必要(指定科目を履修ならば短期養成施設などでの学習は不要)です。一方、福祉系4年制大学を修了した人は、相談援助の実務経験なしで短期養成施設に入れます。
一般の短期大学を修了した人は、1年または2年の相談援助実務に就き、一般養成施設などで1年以上の学習が必要です。4年制の一般大学を修了した人は、実務経験がなくても一般養成施設などで学べます。
その他のルートとしては、「社会福祉主事養成機関→短期養成施設」「児童福祉司などで4年の実務→短期養成施設」「相談援助で4年の実務→一般養成施設」があります。
参考:[社会福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図):福祉系大学等:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
試験合格後は登録申請が必要
国家試験に合格すると、合格通知とともに社会福祉士の申請書類が届きます。社会福祉士と名乗れるのは、申請が受理され、登録証が交付されてからです。
登録申請を行うには、簡易書留で必要書類を公益財団法人社会福祉振興・試験センターに送付しなければなりません。このときに必要となるのは、以下の書類です。
- 登録申請書(1万5,000円の収入印紙を貼付)
- 貼付用紙(登録手数料「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本を貼付)
- 本籍が記載された住民票・戸籍抄本・戸籍の個人事項証明書の原本のいずれか1通
- 介護福祉士養成施設の卒業証明書の原本
社会福祉士の登録手数料は4,050円です。ゆうちょ銀行などで支払い、振替払込受付証明書をもらいましょう。
公益財団法人社会福祉振興・試験センターが審査を行って問題ないと判断すれば、合格者の名前が登録簿に登録されます。合格者は社会福祉士の登録証を受け取った後、晴れて社会福祉士を名乗ることが可能です。
特に問題がない場合、登録申請の書類提出から登録証の受け取りまでは、約1カ月かかると考えましょう。
参考:[資格登録]新規登録の申請手続き|公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
社会福祉士国家試験のための勉強方法

社会福祉士国家試験は難易度が高く、合格のためにはポイントを押さえた勉強が必要です。スムーズに合格を勝ち取るための、勉強のコツを紹介します。
計画的な勉強が必要
一般的に、社会福祉士国家試験に合格するためには、300時間の学習時間が必要といわれています。年に1回しかない試験チャンスを逃さないよう、学習プランを綿密に立てましょう。
1日2時間毎日勉強する場合は、試験日の5カ月前に試験勉強を始めれば300時間を確保できます。一方で、仕事などが忙しく1日1時間しか確保できない場合は、10カ月前から試験準備が必要です。
また社会福祉士国家試験の範囲は広く、基本問題から応用問題までさまざまな問題に取り組む必要があります。合格するためにはすべての科目でまんべんなく得点しなければならいため、「どの科目にどれだけの時間を割くか」という点も非常に重要です。
試験勉強を始める際には、基本問題を○日、応用問題を○日、復習期間を○日などと、具体的な進捗の目安を決めましょう。
テキスト・問題集は最新のものを
独学で勉強する場合は、テキストや問題集の発行年月日に注意しましょう。古いものを利用してしまうと、最新の法律が反映されていない恐れがあるためです。
社会福祉分野・医療分野は、法律の改定・見直しが頻繁に行われています。改定前の法律を一生懸命覚えても、得点にはつながりません。万が一法律関連の項目をすべて落としてしまうと、他の科目で得点を稼いでも不合格になってしまいます。
テキストや問題集に掲載されている情報に不安がある場合は、厚生労働省のホームページなどでこまめに確認するのがおすすめです。
過去問も有効活用
社会福祉士国家試験の合格には、過去問の活用が必要不可欠です。社会福祉士に求められる基本的な知識や情報は、受験年によって大きく変わるものではありません。過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や重要ポイントが見えてくるはずです。
また本試験の雰囲気をつかめるのも、過去問に取り組むメリットといえます。本番と同じ時間で過去問に取り組めば、時間がかかるポイントを把握できます。
どこを重点的に復習すべきか・どこまできちんと理解できているかがよく分かり、学習の最適化が可能です。
社会福祉士として年収を上げるには

社会福祉士資格を取得すれば、年収アップも難しくはありません。社会福祉士として、より高い年収を得るためのポイントを紹介します。
管理職を目指す
現場で年収を上げたいなら、リーダーや主任を目指しましょう。管理する側の職に就くことで、役職手当が支給されます。事業所や会社にもよりますが、1~10万円は月給の額面が増えるでしょう。
ただし管理職に就くと、業務負担も大きくなります。役職手当が少額なら、「まったく割に合わない」「役なしの方がよかった」といったケースもあるかもしれません。
資格手当で給料アップ
多くの事業所や会社では、業務に有益な資格を取得している職員に対し、資格手当を支給しています。社会福祉士の資格を取得したら、速やかに職場に申請しましょう。月々の給料に資格手当が加算されるはずです。
一方「資格手当だけでは物足りない」という人は、社会福祉士以外の資格にもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
例えば、介護支援専門員(ケアマネジャー)や介護福祉士などは、介護職では高く評価されます。社会福祉士資格と合わせてダブルライセンスとすれば、業務の幅を広げることが可能です。より給料の高い業務に就きやすくなるでしょう。
待遇・給料のよい施設に転職する
現在の職場で大幅な給料アップが期待できない場合は、転職を検討してもよいでしょう。社会福祉士の有資格者を求める事業所や会社は数多くあります。中には高額な給料・好待遇を提示するところもあり、今以上に満足できる働き方が実現するはずです。
「どうやって転職先を探せばいいんだろう」という人は、国内最大級の仕事・求人探しサイト「スタンバイ」を活用してみましょう。
スタンバイなら、全国各地の社会福祉士の求人を探せます。働き方や給与の条件とともに検索すれば、理想の職場を見つけるのも難しくありません。まずはどのような求人があるのか、気軽に検索してみましょう。
資格取得で給料を上げて仕事の幅を広げよう

社会福祉士資格は、福祉系では数少ない国家資格の1つです。試験の難易度は高めですが、その分有資格者への評価は高いといえます。
社会福祉士資格があれば、資格手当で給料アップが期待できます。より高度な職や好条件の職場へも転職しやすく、一般的な介護職以上の給料を得ることも難しくありません。
社会福祉士資格を取得して、キャリアアップ・給料アップを目指しましょう。
