退職金は仕事を辞めた後の生活を支えてくれるものです。自己都合退職の場合、いつもらえるのか、相場はどの程度かなど、気掛かりになる人もいるでしょう。退職金がもらえる時期や、会社都合退職の場合との金額の違いなどを紹介します。
自己都合退職での退職金はいつもらえる?

自ら退職を希望する場合、退職理由は自己都合となります。転職活動中の資金源として、退職金を当てにしている人もいるでしょう。自己都合で退職する人が、退職金を受け取れる時期について紹介します。
一般的には退職から1~2カ月後
通常、退職した日から退職金が入金されるまで、1~2カ月かかります。中には、退職した翌月に、最後の給与と同時に振り込む形式になっている企業もあります。
退職金は給与や賞与などと同じように、あらかじめ指定した口座に振り込まれることが一般的です。
「人手不足などの問題がある」「繁忙期に退職する」などのケースでは、書類上の処理に時間がかかることがあるでしょう。また、担当者の勘違いやミスなどが原因で遅れる可能性も考えられます。
退職金制度の内容は企業によって異なる
退職金制度は企業が独自に設けるものであり、いつもらえるかも法律で明確に決まっているわけではありません。支払時期や金額については、就業規則の退職金の項目を確認してみましょう。中には、退職金を導入していない企業もあります。
退職金制度が設けられているか、どの程度もらえるかなどは、老後の暮らしを設計する上で重要な要素です。転職時には求人票を見て、退職金制度の有無をチェックしておきましょう。
自己都合退職での退職金は減額されることも
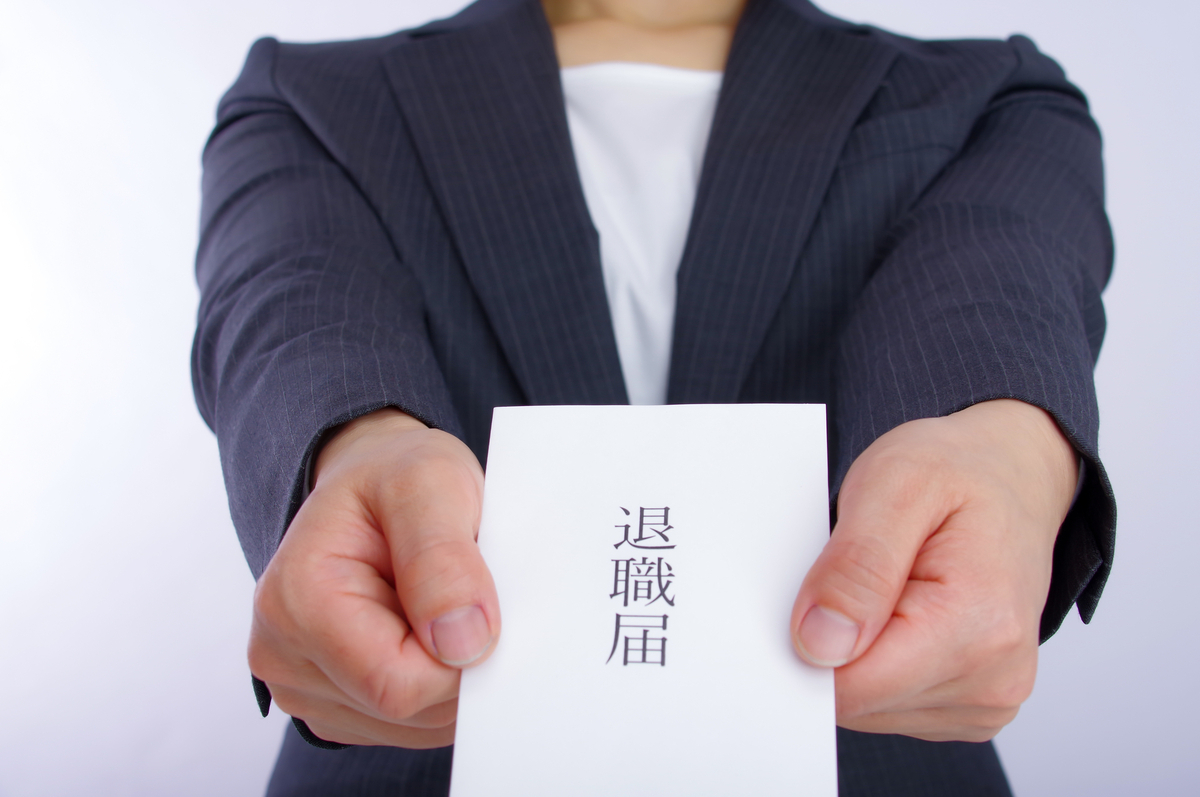
自己都合で退職した人と、会社都合で退職した人を比べると、退職金の額に差が出ることが一般的です。退職金が減額される理由や差額の程度を知る方法について見ていきましょう。
会社都合退職に比べて減額されることが一般的
退職金制度をどのような内容にするかは、企業次第です。法律で定められている制度ではないため、減額したとしても罰則はありません。
通常、退職金の額は事業所の規模や従業員の勤続年数・貢献度・学歴などによって決まります。退職金制度は、長く勤めてくれた従業員に対するお礼のようなものです。企業側が自己都合での退職を歓迎しない場合は、減額される可能性があります。
自己都合による減額がどの程度か知りたい場合、退職金が適用される従業員の範囲や条件などを、就業規則で確認しておくことが大切です。
先に退職した先輩などから話を聞くとイメージしやすい
退職金の減額について不明点があれば、総務部や人事部に問い合わせましょう。直接聞きづらい場合、先に退職した先輩の話や、求人サイトなどの企業の口コミを参考にする方法もあります。
通常、就業規則は従業員が自由に閲覧できるようになっています。しかし、退職規定と自分の状況を照らし合わせたとき、該当しているのかどうか分からない場合もあるかもしれません。
もらえると思っていた退職金がないと、仕事を辞めてからの生活が不安になるでしょう。会社の経営状況などによって内容が変更されるケースもあるので、退職する時点でいくらもらえるのかは、事前にしっかりと確認しておきたい部分です。
自己都合退職による退職金の相場

東京都産業労働局では、中小企業向けにモデル退職金を公表しています。モデル退職金とは、学校を卒業後に就職した人が、一般的な能力で勤務したケースの退職金水準を指す言葉です。
学歴や勤続年数の違いなどを踏まえた、退職金の額を見ていきましょう。
高校卒で勤続年数10年の場合は約100万円
東京都産業労働局が2024年12月に公表した「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」を見ると、高校卒で勤続年数10年の人が自己都合退職した場合のモデル退職金は98.5万円です。
学歴や勤続年数は同じで、会社都合で退職した場合は126.4万円となっており、自己都合退職と比べると27.9万円の差があることが分かります。
また、高校卒で定年まで勤めたときのモデル退職金は、974.1万円です。このことから、長く勤めるほど大きな金額差が出るといえるでしょう。
出典:中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)PDF39枚目 <図表8-1>モデル退職金
大学卒で勤続年数20年なら300万円を超えることも
大学卒で勤続年数20年の場合、自己都合退職のモデル退職金は346.8万円です。学歴や勤続年数は同じで、会社都合での退職となった場合は408.1万円で、金額差は61.3万円となっています。
学歴が高く勤続年数が長いほど、退職金が高額になる傾向といえるでしょう。
なお、大学卒で定年まで勤めた場合は1,149.5万円です。高校卒と比較すると、175.4万円も多くもらえることになります。
出典:中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)PDF39枚目 <図表8-1>モデル退職金
勤続年数3年以下ではもらえないケースも
退職金の性質を考慮すると、勤続年数が短い人に支給される可能性は低いといえます。勤続年数が半年〜1年など短期間の場合、退職金はもらえないことが一般的です。
「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」によると、自己都合・会社都合ともに退職金を受け取るための最低勤続年数を、3年に設定している企業が多いことが分かります。
勤続年数が3年以下でも退職金を用意している企業もありますが、長く勤めた人に比べると少額になる点は心に留めておきましょう。
出典:中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)PDF37枚目 <図表7-5>退職一時金を受給するための最低勤続年数
自己都合の退職金についてのQ&A

どのような状況で退職をするかは人によって異なり、さまざまなケースがあると考えられます。自己都合による退職で、退職金をもらう場合にありがちな疑問を解消しておきましょう。
「中退共制度」に加入している場合はどうなる?
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、国が中小企業向けに設立した退職金制度です。中小企業の振興や従業員の福祉のため、1959年に設立されました。
事業主が毎月の掛け金を中退共に納付することで、従業員が退職するときに、中退共から直接その従業員に退職金が支払われる仕組みです。
この制度を利用すれば退職金の管理をしなくてよいため、企業側の負担を減らせる点がメリットです。
中退共制度に加入している場合、退職金がもらえる時期は請求してから約4週間後です。退職する月の掛け金の入金を確認後に支払い手続きがされ、明細や振り込み予定日は、請求人と事業主の双方に通知されます。
退職金が差し押さえられることはある?
税金や借金の滞納などがあると、民事執行法第152条第2項にのっとった範囲内で退職金が差し押さえられるケースがあります。
退職金を既に受け取っている、あるいは受け取ることが確実である場合には、債務を履行するための資金源として扱われることがあるでしょう。
心当たりが何もないのに急に退職金が差し押さえられることはありませんが、借金の返済や離婚裁判などを控えている場合には、注意が必要です。
出典:民事執行法 第152条 第2項 | e-Gov 法令検索
トラブルが起こった場合は?
就業規則で退職金をもらえる条件に当てはまっているにもかかわらず、いつまでたっても支払いがされないといった事態に陥ることもあります。
問題が起きたときは、まずは企業の担当部署に問い合わせましょう。しかし、企業や担当者と連絡が取れない状態になることもあるかもしれません。
退職金に関するトラブルが起き、企業との話し合いで解決しないときには、労働基準監督署に相談する方法があります。労働基準監督署は、労働に関する法令に基づいて企業を監視するために設置されている機関です。
就業規則に自己都合でも退職金がもらえると記載されているのに支払われない、担当者と連絡が取れないなどのケースに当てはまる場合は、労働基準監督署に問い合わせてみましょう。
退職金制度の内容をよく確認しよう

退職金制度を設けているかどうかは企業によって異なり、対象範囲や金額などもさまざまです。企業が独自に設ける制度のため、受け取れる金額やいつもらえるかは就業規則の退職規定などで確認できます。
自己都合での退職の場合、会社都合よりも減額されることが多いので、事前に確認しておく方が、退職後の生活設計がしやすくなるでしょう。
これから退職金制度のある企業への転職を考えている場合は、国内最大級の求人情報一括検索サイト「スタンバイ」の利用が便利です。理想の職場探しにぜひお役立てください。
