近年、FPの資格取得を目指す人が増えています。しかし、FPとは具体的に何をする人なのか、またどのような知識が必要なのかよく分からない人も多いでしょう。FPの資格を取得することで身に付く知識や、メリットについて解説します。
FPとは?

「FPはお金に関係する知識が身に付く資格」という、漠然としたイメージを持つ人は多いでしょう。まずは、具体的な仕事内容や、資格の種類について解説します。
お金に関してアドバイスをする専門家
FPとは、一般的に「ファイナンシャル・プランナー(Financial Planner)」のことを意味します。相談者の財務状況を分析し、ライフプランに合わせた資金計画などを提案する専門家です。
お金に関する相談に対し、長期的・総合的な視点からアドバイスを行います。FPが対応できる相談内容は、日常的な家計管理のほか、教育資金や老後の生活資金の準備方法・住宅ローン・資産運用・保険・年金・不動産・税務などさまざまです。
相談者がかなえたい夢・目標を実現させるために、「お金」という側面からサポートするのがFPの仕事です。
国家資格と民間資格の2種類がある
FPには、国家資格と民間資格の2種類があります。国家資格とされているのは「FP技能士」と呼ばれるもので、取得することでFPとしての技能が証明されるものです。
FP技能士は1~3級に分かれており、NPO法人日本FP協会(以下、日本FP協会)と一般社団法人金融財政事情研究会(以下、きんざい)の2団体が試験を実施しています。
民間資格とされているのは、日本FP協会が認定する「AFP資格」と「CFP資格」の2種類です。どちらも、FP技能士としての知識を継続的にアップデートすることを目的として、設置されています。
AFP資格を取得するには、2級FP技能検定に合格し、さらにAFP認定研修も修了することが必要です。また、CFP資格は、AFPの認定者がCFP資格試験の合格後にCFPエントリー研修を修了し、CFP資格審査試験全6課目合格日前10年~CFP資格認定日までに通算3年以上の実務経験を経ると登録申請ができます。
FPに必要な知識【資金計画・資産運用】

資金計画・資産運用に関する知識には、「ライフプランニングと資金計画」「リスク管理」「金融資産運用」の3つが含まれます。それぞれどのようなことを学ぶのか、具体的に見ていきましょう。
ライフプランニングと資金計画
ライフプランニングとは、将来どのような生活を送りたいか、具体的に考えることを指します。そして、思い描いたライフプランを実現するために必要となる資金を算出し、調達方法などを検討するのが資金計画です。
具体的には、ライフプランニングを考えるための手法として、ライフイベント表・キャッシュフロー表・バランスシートの作り方などについて学びます。
公的年金・健康保険・住宅ローン・教育ローン・介護保険などの、仕組みに関する知識も必要です。この分野の知識を身に付けることで、将来思い描いている生活を実現させるための資金計画を、立てられるようになります。
リスク管理
リスク管理では、病気・事故・天災など、将来起こり得るリスクに対して備えるための知識を学びます。将来に備えるにはさまざまな方法がありますが、この分野で学ぶのは、生命保険・損害保険といった民間の保険に関する知識です。
生命保険・損害保険の種類や特徴、ライフプランに合った保険の選び方などについて学びます。また、個人契約だけでなく、法人契約による保険の仕組みや、関連する税金などについての知識も必要です。
リスク管理について学ぶことで、予測不能なリスクに備えながら、将来の生活を充実させる方法を考えられるようになるでしょう。
金融資産運用
金融資産運用の分野では、将来に備えた資産の増やし方に関する知識を身に付けます。資産を増やす方法を学ぶには、資産運用の仕方だけでなく、経済や金融市場の仕組み、金融商品に関する法律などについての知識も必要です。
資産の運用には貯蓄のほか、株式投資・債券・投資信託といったさまざまな方法があります。株式を売買する方法から、相場指標の読み方・利回りの計算・取引で生じる税金まで、幅広い知識が必要です。
これらの知識を身に付けることで、資産運用に関するリスクやリターンの分析、適切な金融商品の選び方などが分かるようになるでしょう。
FPに必要な知識【税金・不動産・相続】

FPの資格を取得するには、税制や不動産取引、相続などについても学ぶ必要があります。具体的に、どのような知識が求められるのか見ていきましょう。
タックスプランニング
タックスプランニングの分野で学ぶのは、所得税を中心に、住民税や個人事業税などの税制に関する知識です。所得税は給与所得だけでなく、預貯金の利子や株式の配当金、不動産の貸し付け・譲渡などさまざまな所得にかかります。
それぞれの所得税の算出方法や、所得控除などについての知識を身に付けることで、税金対策に関するアドバイスが可能になるでしょう。
税金と聞くと複雑で苦手意識を持つ人もいるかもしれませんが、資産運用など他の分野にも関連する知識なので、しっかり学んでおくことが大切です。
不動産
FPの資格を取得するには、不動産の分野についても学ぶ必要があります。FPに求められるのは、主に不動産取引の仕組みや関連する法令、税金などについての知識です。
住宅の購入は、人生において最大の買い物ともいわれています。相続によって親から不動産を受け継ぐケースでは、処分に悩む人も少なくありません。
不動産に関する知識を身に付けておくことで、不動産の売買だけでなく、有効な活用方法においてもさまざまな選択肢を提示できるでしょう。また、賃貸借契約に関する法令なども学ぶため、不動産の賃貸についての知識も身に付きます。
相続・事業承継
この分野では、人が亡くなった後の相続や事業承継に関する、法令・税金について学びます。相続によって譲り受けた財産が一定額以上に達すると、相続税が課されます。
また、生前に財産が分けられた場合は、贈与税を納めなければなりません。相続税・贈与税を算出するには、さまざまな計算方法を学ぶ必要があります。
スムーズな財産分与や納税資金対策などのためには、しっかり学習して知識を身に付けておくことが大切です。また、遺産分割や遺言に関する定めについても学ぶため、遺産相続を巡るトラブルの防止にも役立つでしょう。
FP資格を取得するメリット【日常生活編】

FPの資格を取得すると、友人などからの相談に乗れるほか、自分自身の日常生活にも役立ちます。具体的なメリットを、3つ見ていきましょう。
家計管理に役立つ
FPの資格取得で得た知識は、自身の家計管理に生かせます。
例えば、ライフイベント表からバランスシートまで作成できるようになるため、教育資金・住宅購入などにどのくらいのお金を用意しておくべきか、把握できるでしょう。将来必要となる資金の目安が分かれば、資金運用を含めた計画が立てやすくなります。
また、目的やライフステージに合わない保険に加入していないか、無駄な支出がないかなど、現在の家計を見直すことも可能です。さらに、税制に関する知識は、節税にも役立ちます。
資産運用を始めるきっかけになる
「株式投資・投資信託などの資産運用を始めてみよう」と思う、きっかけにもなるでしょう。長寿・高齢化が進む中で、老後の生活費をどのように準備すればよいか、不安に感じている人は少なくありません。
将来の資金調達のために、投資信託などによる運用を始める人は増えているものの、何をどうすればよいか分からない人も多いでしょう。FPの資格では、金融商品の種類や仕組みなど、資産運用の基本知識を学びます。
正しい知識を得ることで、将来に向けた資産調達のための選択肢が広がり、実際に運用してみようという気持ちになるでしょう。
お金に関する漠然とした不安を解消できる
将来の生活が心配な人は、「いつ、何にいくらかかるか分からない」という漠然とした不安を抱えていることが多いものです。FPは、ライフプランに応じて必要となる資金の算出方法をはじめ、さまざまな「お金」に関する知識を身に付けています。
年金・保険などの公的制度に関する知識や、リスクへの備え方も学ぶため、むやみに不安になることから解放されるでしょう。
自分の将来にどのくらいの費用がかかるかを把握できれば、やみくもに保険に加入したり、必要な生活費の分まで貯蓄に回したりといったことも回避できます。
FP資格を取得するメリット【仕事編】

FPの資格は、仕事の場で有利に働くこともあります。どのような場面でメリットとなるのか、具体例を3つ見ていきましょう。
転職の際にアピールできる
まず、転職の際のアピールポイントとして役立つ点が挙げられます。特に、2級・1級のFP技能士資格を取得していると、金融業界や保険業界への転職で有利になることもあるでしょう。
金融業界では、個人向けに資産運用などを提案する「リテール」と呼ばれる営業の仕事もあります。FP資格によって専門的なアドバイスができることをアピールできれば、会社に貢献できる人材として評価される可能性があるでしょう。
また、不動産業界やコンサルティング業界などへの転職でも、FPの資格を取得していると評価の対象になる傾向にあります。
収入がアップする可能性がある
FPの資格取得が、そのまま収入アップに結び付くケースもあります。企業によっては、資格手当が支給される可能性があるためです。実際、金融業界や保険業界では、入社後にFPの資格取得を推奨している企業も少なくありません。
同じ業務を担当していても、資格の有無によって収入が変わるということもあり得ます。資格手当がない場合でも、昇進・昇給の評価対象となり、結果的に収入がアップする可能性もあるでしょう。
一般企業の場合でも、経理などの仕事をしている人にとって、取得しておくとメリットのある資格です。
独立・副業に役立つ
FPとして独立し、金融機関などと提携して顧客のライフプランに関する相談に乗ったり、保険・金融商品を紹介したりすることを収入源にしている人もいます。
自宅を事務所にすることも可能なため、大きな元手をかけずに独立できるのがFPのメリットです。未経験の場合、軌道に乗せるまでが大変ですが、最初は週末などの空き時間を利用した副業から始めるという手もあります。
クラウドソーシングを活用してFPとしての実績を作るほか、友人の相談に乗るなどしながら、少しずつ経験を積んでいくのもよいでしょう。また、資格の勉強で得た知識を生かして、お金に関する記事の執筆・監修をする方法もあります。
FP試験の概要
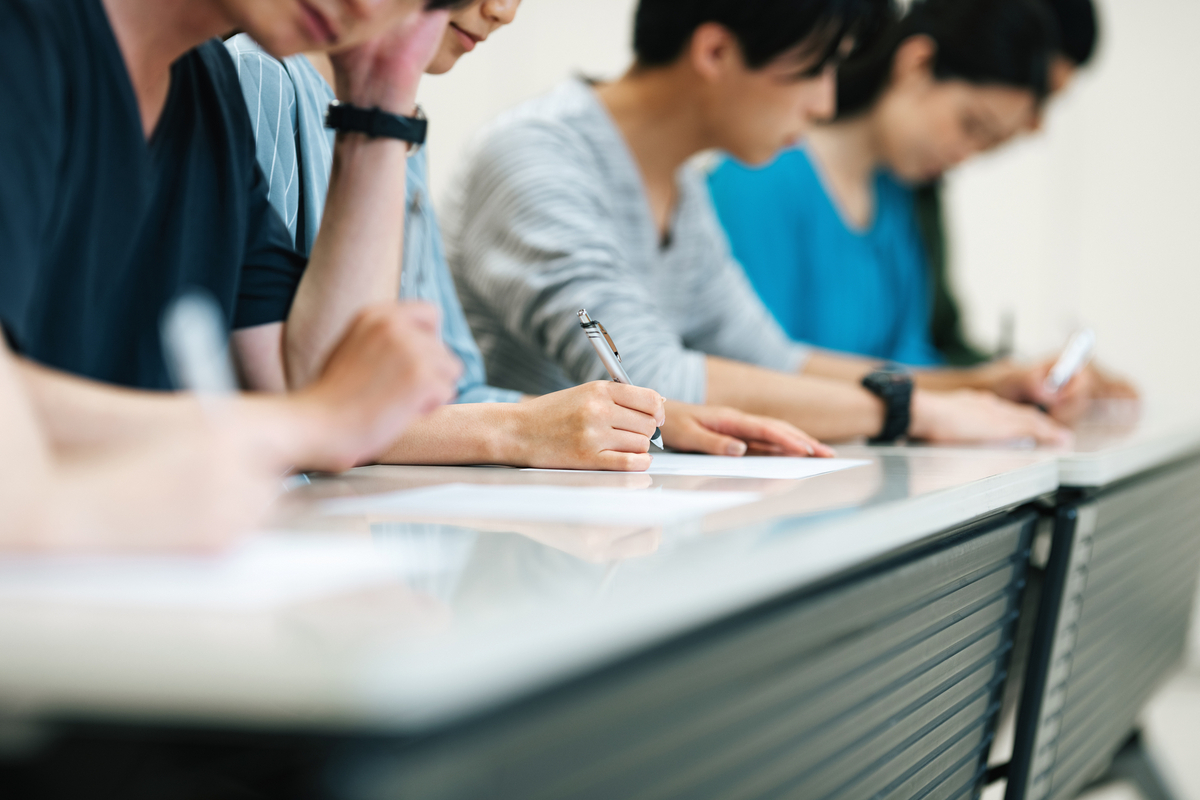
FPの資格試験(FP技能検定)の概要についても、確認しておきましょう。試験内容や、難易度について解説します。
試験内容
FP技能検定は、日本FP協会ときんざいの2団体によって実施されており、どちらでも好きな方を受検できます。試験は学科・実技の2種類があり、学科試験と実技試験は同日実施され、両方を受検可能です。
学科試験の内容は共通ですが、実技試験の方法は団体によって異なります。また、日本FP協会の場合、1級の学科試験は行われず実技試験のみが実施されます。
3級の受検資格は、どちらの団体でも「FP業務に従事している人、または従事しようとしている人」となっており、基本的に誰でも受検可能です。2級・1級を受検するには条件があるので、事前に確認しておきましょう。
出典:日本FP協会
難易度
FP技能検定の合格率は、日本FP協会ときんざいで若干の違いがあるものの、国家検定の中では比較的難易度が低いといわれています。2023年9月に実施された、日本FP協会のFP技能検定の合格率は以下の通りです。
- 1級:96.2%(実技試験のみ)
- 2級:学科試験53.54%・実技試験52.02%
- 3級:学科試験74.78%・実技試験77.67%
上記の結果を見ても、FPは他の国家検定に比べて合格のハードルが低めな資格であることが分かります。仕事に生かせる国家資格を取得したい人にとって、おすすめといえるでしょう。
出典:FP技能士の取得者数 及び 試験結果データ | 日本FP協会
FPの知識を生活や仕事に役立てよう

FPとは、お金に関する相談に対して、さまざまなアドバイスをする専門家のことをいいます。FPの資格を取得するためには、資産運用・保険・税制・不動産・相続などの幅広い知識が必要です。
しかし、資格を取得すれば日常生活のお金に関する課題解決に生かせるほか、転職などでも有利に働く可能性があります。国家検定の中では比較的難易度が低いため、仕事に役立てたい人は資格取得に挑戦してみてはいかがでしょうか。
FP資格を生かした仕事探しには、求人情報が豊富に掲載されている「スタンバイ」を活用しましょう。
