就労支援員は、どこでどのような仕事をしているのでしょうか?支援の対象者や具体的な業務内容、必要な資格について、詳しく知らない人もいるでしょう。年収事情や将来性も併せて、就労支援員を目指す上で押さえておきたい基礎知識を解説します。
就労支援員とは

就労支援員は、その名の通り就労を支援する専門職です。誰にどのような支援をするのか、役割と主な業務、職業支援員との違いなどを見ていきましょう。
就労支援員の役割
就労支援員の役割は、障害や病気、貧困などの理由で就労が困難な状況にある求職者に対して、就職活動を支援することです。
具体的には障害者・生活保護受給者・ひとり親世帯などが挙げられます。
支援内容は主に以下の3つです。
- 求職者の指導:履歴書作成や面接指導、技術指導など
- 関係機関との連携:ハローワークや就職先企業との調整、職場見学同行など
- 就職後のサポート:仕事を継続できるよう、定期的なフォロー
就労支援員は、単なる就職斡旋にとどまらず、利用者の自立と社会参加を促進する橋渡し役として、包括的な支援を提供します。
職業支援員との違い
就労支援員と職業支援員は、名前がよく似ていますが、その役割には明確な違いがあります。就労支援員の支対象は、障害者や生活困窮者など幅広く、就職活動から就労後のフォローまでを担当します。
一方、職業支援員が担当するのは、主に障害者です。児童養護施設などに入所している児童を、支援する場合もあります。支援内容も就職活動そのものではなく、企業で働くために必要なスキルやルール・マナーの習得など、就労準備に重点を置いています。
就労支援員の活躍の場
就労支援員の主な職場として、障害者の就労支援を行う「就労移行支援事業所」や「就労継続支援事業所」が挙げられます。
就労移行支援は、一般企業で働くことが可能な、65歳未満の障害者が対象です。就労継続支援は、一般企業で働くことが難しい障がい者に対して、ほかの就労機会や職業訓練の機会を提供します。A型とB型があり、それぞれ支援の内容や対象者が異なります。
生活保護受給者やひとり親家庭の親などをサポートする福祉事務所、児童福祉施設なども、就労支援員が活躍できる場所です。
就労支援員に役立つ資格
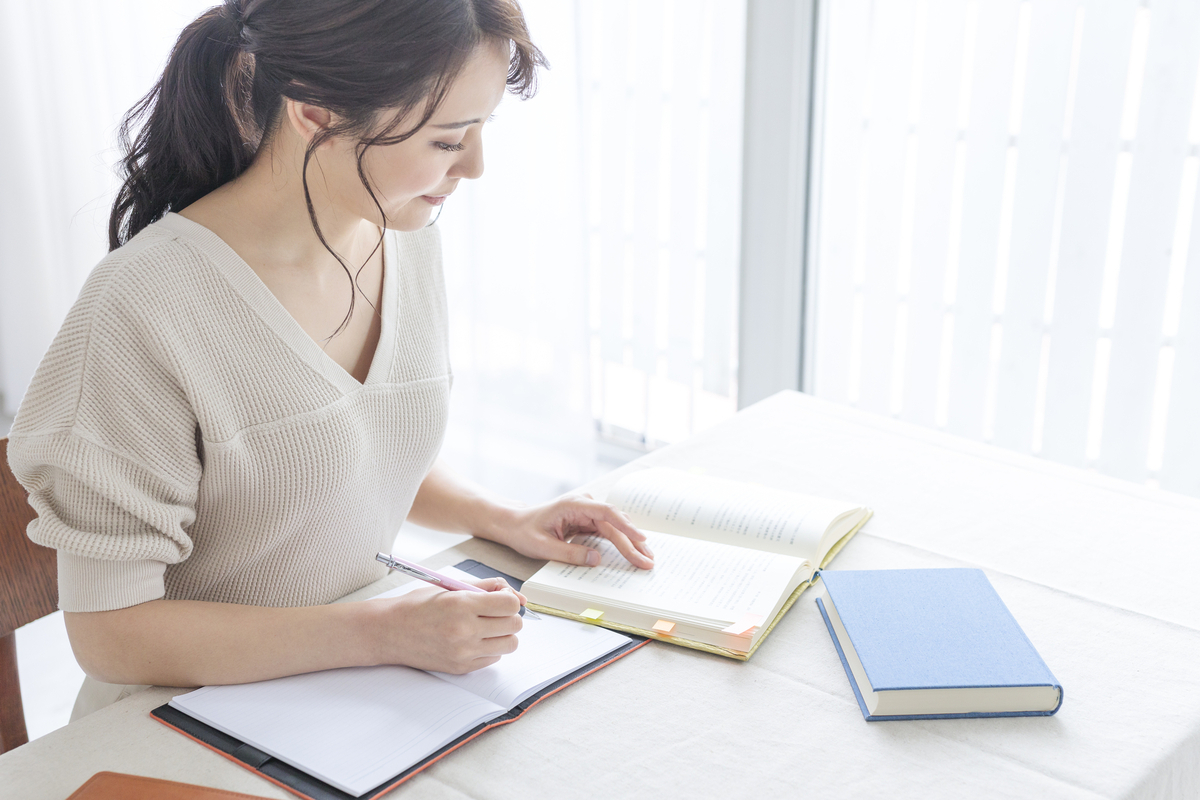
就労支援員になるために、特定の資格取得や研修の受講などは必要ありません。ただし業務に役立つ資格はいくつかあります。専門性を高め、効果的な支援を提供する基盤となる資格を3つ紹介します。
社会福祉士
社会福祉士は、生活上の困難を抱える人に対して、相談・助言・指導するスキルを証明する国家資格です。社会福祉士の知識と技能は、就労支援の現場でも、求職者の多様なニーズに応え、効果的な支援を提供する上で大きな強みとなります。
就労支援以外にも、社会福祉士の活躍できる場は多く、就職や転職においても有利といえるでしょう。
国家試験を受けるには、福祉系大学や短期大学での指定科目履修や、所定の実務経験が必要です。実務経験を積んだ後、養成機関で学ぶルートもあります。
出典:[社会福祉士国家試験]:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
社会福祉主事任用資格
社会福祉主事任用資格も、福祉の幅広い分野に対応できる資格です。就労支援員として働く上でも、福祉の基礎知識を身に付けられる点で有用といえます。
なお「任用資格」とは、その職種に就いている間のみ効力を発揮する資格のことです。
社会福祉主事任用資格も、地方公務員試験に合格した上で、福祉事務所や社会福祉施設に配属されると、名乗れるようになります。
試験はなく、以下のいずれかの条件を満たすことで、取得できます。
- 大学等で、社会福祉に関する科目を3つ以上履修
- 指定の通信教育・養成機関・講習会のいずれかを修了
- 社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を保有
児童指導員任用資格
児童指導員任用資格は、放課後デイサービスや児童養護施設などの、児童福祉施設で働くための資格です。児童福祉施設の子どもは家庭にさまざまな事情を抱えており、こうした子どもへの支援経験は、ひとり親世帯の就労支援に役立ちます。
社会福祉主事と同じく任用資格で、取得条件は以下の通りです。
- 4年制大学で教育学や社会福祉学などの学科を卒業する
- 社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかを取得
- 高校や中学を卒業後、2年以上児童福祉事業に従事
- 3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定される
- 幼稚園教諭・小中学校・高等学校の教員免許を所有し、厚生労働大臣又は都道府県知事から認定される
出典:児童指導員 - 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))
就労支援員の具体的な仕事内容

就労支援員の仕事は、求職者への指導・関係機関との連携や調整・就職後のフォローアップの3つの柱で構成されています。それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。
求職者の指導
就労支援員の主な業務の1つが、求職者に対する就職活動のサポートです。希望や適性に応じて求人情報の提供や企業とのマッチングを進め、就職に向けて、具体的にアドバイスします。
応募に必要な履歴書やエントリーシートの作成指導・面接対策・ビジネスマナーの教育なども大切な業務です。就労機会を増やすために、パソコンなどの機器操作・木工・園芸といった作業スキル習得の指導や訓練を実施することもあります。
関係機関との連携と調整
求職者のニーズに合った就労機会を見つけるには、ハローワークや受け入れ先企業といった、関係機関との連携が欠かせません。ハローワークなどの職業紹介機関には、求職者に同行し、仕事の斡旋を依頼します。
受け入れ先候補が見つかれば、職場体験や面接に同行し、就労できるように尽力します。障害者雇用を考えている企業に、従業員教育や職場環境の整備などについてアドバイスするのも、就労支援員の役割です。
就職後のフォロー
就労支援員の求職者へのサポートは、就職が決まった後も続きます。もともと就労が困難な状況にある人が自立するためには、職場に定着し安定した収入を得ることが重要です。
すぐに辞めてしまっては意味がないため、就労支援員が定期的に職場を訪問し、フォローする必要があるのです。
職場での人間関係や業務上の課題が発生した場合は、迅速に対応し、問題解決をサポートします。キャリア形成のためのスキルアップや、新たな目標設定について助言することもあります。
就労支援員の年収とキャリアパス

就労支援員になると、どのくらいの収入を得られるのでしょうか。より良い条件の職場に転職したり、昇進したりできるのかも、気になるポイントです。平均的な年収や、キャリアアップの可能性について解説します。
就労支援員の平均年収
厚生労働省の調査によると、障害福祉サービス等で働く常勤の就労支援員の月給は、2023年で23万4,408円です。同じく厚生労働省の職業情報提供サイトでは、就労支援員を含む「障害者福祉施設指導専門員」の求人賃金月額が21.5万円、平均年収が425.8万円となっています。
2023年の給与所得者の平均年収は460万円ですので、就労支援員の年収は、全国平均よりもやや低いのが現状です。ただし年収は、勤務先の規模や種類、経験年数によって異なるものです。
また、給与体系は多くの場合、基本給と諸手当で構成されており、役職や資格手当の有無によっても、支給額は変わります。就労支援員には無資格・未経験でもなれるため、特定の資格や経験が必要な職業に比べて平均年収が低くなるのは、仕方がないともいえます。
出典:令和 5 年障害福祉サービス等経営実態調査結果|厚生労働省
出典:障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等) - 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))
キャリアアップの可能性
就労支援員には、さまざまなキャリアアップの道があります。経験を積めば、チームリーダーやサービス管理責任者など、マネジメント職への昇進が望めます。
社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を取得すれば、より質の高い支援提供につながるだけでなく、資格手当が付くなど給与面でも優遇されるでしょう。
職員のスキルアップを目的とする勉強会や外部研修を実施する事業所も多く、未経験者でも働きながら専門スキルを身に付けられます。経験・資格・スキルを武器に、待遇のよい事業所へ転職できる可能性もあります。
就労支援員の将来性とやりがい

就労支援員の需要は着実に増加しており、将来性のある仕事といわれています。その理由と、仕事のやりがいを見ていきましょう。
就労支援員の需要
厚生労働省の統計では、何らかの障害を持つ人の数は増加傾向にあります。2006年と2018年を比べると、約300万人も増えているのです。諸説ありますが、医療の発達や障害への認知度が高まったことなどが、増加の主な要因とされています。
その結果、就労支援員の勤務先となる事業所も増えています。事業所には、利用者数に応じて一定数の就労支援員を配置する義務があるため、障害者の増加に比例して求人件数も増えると考えてよいでしょう。
就労支援員には無資格・未経験でもなれますし、先述の通り働きながらスキルを習得してキャリアアップも可能です。その点でも、将来性のある職業といえます。
就労支援員のやりがい
就労支援員の仕事には、大きなやりがいがあります。就労が困難な人が、希望の仕事に就き、自立した生活を送る姿を見られることは、この仕事の醍醐味です。
働いて収入を得る行為は、経済的な安定をもたらすだけでなく、社会に参加している喜びや、自分が成長できたことへの手ごたえを感じることにもつながります。
生活に余裕が生まれれば、諦めていたことを実現でき、さらに充実した人生を送れるかもしれません。就労支援員は仕事を通して、利用者の人生に寄り添い、可能性を引き出す役割も担っているといってよいでしょう。
就労支援員の仕事を理解しよう

就労支援員は、自力では就職が困難な人の就労をサポートする専門職です。障害者の就労支援事業所や、福祉事務所などに勤務します。求職者に適した職場を探し、就職後は職場に定着できるようフォローするのが、主な仕事です。
求職者の経済的自立と社会参加を実現するために欠かせない存在であり、需要は今後も増加すると予想されます。
就労支援員に興味がある人は、国内最大級の仕事・求人情報一括検索サイト「スタンバイ」を利用してみましょう。豊富な求人情報から、具体的な勤務先や、給料についての情報を無料で得られます。
